ずっと書いてきたけれど自伝じゃない。 実人生について書いた連中はみんな死んじまうのに気づいたんでね。
——JL、 一九七六年、 ファンの質問に答えて
好きなとこ行けない
タイムマシーンいらない
——The Birthday 「COME TOGETHER」
僕の家系は先祖代々の嘘つきだ。 大法螺を吹いて他人を笑わすのが大好きで、 日々の挨拶でさえ話を盛らずにはいられない。 芸術と辛辣な冗談を愛する母方の血かもしれないし、 酔っ払いの船乗りだった父方のせいかもしれない。 この僕にしても誠実さとはほど遠く、 度のきつい眼鏡で現実を捉えるよりも、 裸眼で薄らぼんやりした光を眺めて、 どんな世界だろうと夢見るほうが好みだったりする。 だから伯母によれば一九四〇年秋、 オックスフォード通り産院に五分おきに電話をかけつづけ、 男の子ですとの報せを耳にするや、 炸裂する榴散弾や散発的な銃撃戦をかいくぐって駆けつけ、 生まれたての甥を妹から奪って抱き締めて、 この子はあたしのだと心に決め、 戦時下の衝動的な愛国心から、 親父発案による祖父の名に、 苦虫を噛み潰したような首相の名を加えさせたことになっているのだけれど、 これはやがて街いちばんのガキ大将を自認し、 独創的な悪戯の数々で大人たちを戦慄させることになるその子が、 純真かつ品行方正な少年として回想されるのと同様に、 伯母が話をおもしろくしようと欲ばって、 しまいにはみずから信じ込むに至った一例にすぎない。 確かに夕暮れからはじまる空襲に備えて交通機関が停まっていたのも、 僕らの街が翌年の春にはすっかり跡形もなくなったのも事実だし、 そうなる前でさえ活力や希望のあふれる真新しい街とはいえず、 なんなら現在でさえ前世紀の疵痕が癒えぬまま、 老いぼれ四人組にすがって街興しを目論む体たらくではあるものの、 少なくともその日にかぎっては、 勤勉なドイツ人が珍しく日課をサボったのが記録上の事実なのだ。 僕の子ども時代が頑固で偏屈な読書家と、 恋と音楽を愛する享楽主義者、 ふたりの母によって形づくられたとするならば、 いわばその愛すべき子どもはこの世にまろび出た時点から真っ赤な嘘 (妻Yとわれらが友人Mによれば、 日本語ではそう表現するそうだ……嘘が血と革命の色だなんて皮肉じゃないか?) にまみれていたわけだ。
ありのままの声はつまらない。 いつだってエコーやリバーブをかけて、 だれか途轍もなく愉快な人物が、 別世界から語りかけてくるみたいにしたい。 僕がそうすることはみんな知っているし、 きみだってそうだろう (お宅の棚にだってJLやザ・Bの作品がきっと一枚はあるはずだ)。 ましてこの物語には、 僕には知りようもない出来事や、 知りようもない他人の内面を、 あたかも見てきたかのように描写するところがたくさんある。 でもこれだけは信じてほしい。 はじまりの日付が九、 時刻は午前六時三〇分——足すと九になる数字だったのは誓って本当だ。 終生つきまとい、 この物語で幾度となくくり返される魔法の数字である。 最初に住んだ祖父の家はリバプール、 ウェヴァツリー、 ニューカッスルロードと、 九文字で綴る地名の九番地だったし、 七二番バスに乗って通った学校で、 九文字の姓を持つ親友ふたりと出逢い、 その後もなんやかやと、 足すと九になる番地に暮らしたり、 思い出深い日付が決まって九日だったりしたものだ。 そんなのは偶然にすぎない、 こじつけだ、 ご都合主義の嘘っぱちだ……いやまったくごもっとも。 でも例えば殺到するファンから逃げ隠れるために付けひげをつけたり、 キャメラの前でその再現をさせられたりしたときには四人とも、 まさか好きこのんで自前の毛を伸ばすことになるとは思ってもみなかったし、 雪山で酔っ払って奇妙な鳴き声を披露したり、 南の島で女の子を演奏したりしていた時点では、 Gが演じた役そのままに、 インド音楽や危険な自動車レースに熱中するなんて、 大麻の夢においてさえも思い描かなかった。 ド近眼に映るぼやけた世界のほうが、 得てして真実に迫っていたりするものなのだ。 そしてこれからお聞かせする与太話も、 きみのところの歴史、 はたまた未来がいかなるものであれ、 二度と逢うことのない奇妙な友人と僕のふたりにとっては、 嘘偽りない真実なのである。
他人を笑わせるための駄法螺といえば、 わが全生涯を費やす娯楽稼業なるものがまさにそれで、 僕は貧しい港町から這い上がった、 労働者階級の英雄ということになっている。 出身地がお世辞にも豊かとはいえないのは事実だけれど、 育った家をそんなふうに評されては伯母は機嫌を損ねるだろう。 メンローヴ通り二五番地に構えた家は、 ほとんど戸建てといっていい準独立家屋で、 当時としては文化的で小洒落ており、 小さな庭には植木や芝生や物置があり、 浴室も屋内便所もあったし、 電話や絵を架ける横木やステンドグラスまであった。 僕が引き取られた頃には機能しなくなっていたものの、 召使いを呼ぶ電気式のベルまで備えていた。 何よりメンディップスと名づけられたその家には本がふんだんにあった。 パイプをくゆらす伯父の膝で、 地元紙を読み聞かせられるうちに文字を憶えた僕は、 求めるままに買い与えられた児童書を卒業すると、 古典や名作、 伝記、 回想録や歴史書にまで手を出した。 ろくでなしの父親と享楽主義者の母親、 双方のあいだを引きずりまわされるディケンズ的孤児は、 ついに伯母夫婦と本、 愛情と文字の世界に、 安住の地を見いだしたというわけだ。 続き物の小説をはじめて書いたのもこの頃で、 その物語は決まって 「また来週号をお楽しみに」 で終わった。 結末まで書き上げたかは思いだせない。 伯母の下宿人からハーモニカをせしめたのも同時期だったので、 音楽に関心が移って飽きたのではないか。 年相応の落ち着きをついぞ身につけなかった僕だけれど、 いまはもうこの世界にいないMとの約束だけは守りたい。 この物語はきっと 「めでたしめでたし」 で締めくくると誓う。 「そしてJはYといつまでも幸せに暮らしましたとさ」 と。
メンディップスに行き着くまでの事情を説明しようとすると、 つい感情的になり伯母に負けじと話を盛ってしまう。 父について行くつもりだったが土壇場で気を変えた話はやりすぎだった。 逆光に遠ざかる小さな背中や夕陽に長く伸びる影、 母ちゃんと叫んで駆け寄る幼い僕を描写したりなんかしてね。 実際はそこまで劇的でもお涙頂戴でもない。 両親とも責任を果たせるほど大人でもなければ金もなかっただけのこと。 何しろ父は育ちや頭が悪すぎて、 子どもには安定した暮らしや教育が必要だということを理解せず、 休暇旅行を口実に息子を伯母のもとから連れ出して、 船員仲間の家に居候したりしたあげく、 危うく外国にまで拉致するところだったし、 母は母で、 厳格な父親に反抗する十代の少女のまま成長していなかった。 なにせ母ときたら、 いくら貧しいとはいえひとつの寝台で、 顔面神経麻痺の愛人とのあいだに幼いわが子を寝かせて平然としていたのだ。 MとYにいわせれば、 かれらの故国では 「川の字」 (三本の線で水の流れを示す、 僕が憶えた数少ない日本語のひとつだ) といって別に珍しい習慣ではないらしいし、 確かに小津安二郎の映画でそんな場面を観たこともあるけれど、 奔放な母の生活を思えば、 伯母の判断はけっして杞憂ではなかった。 法的には離婚していない夫婦双方に幾度となく介入を試みた伯母は、 埒が明かぬと見てとるや、 公的扶助委員会の職員を引き連れて妹の家へ押しかけ、 ゲートエイカー地区よりウールトンのほうが養育にふさわしいと認めさせた。 かくして僕は兎穴に落ちたアリスやわんぱく坊主ウィリアム・ブラウンと親友になったわけだ。
当時の中流家庭にはよくあったことだけれど、 伯母は上昇志向の持主で、 暮らし向きの劣るひとびとをあからさまに差別して、 あの家の子とは遊んじゃいけませんなどと僕の交友を制限したり、 身障者とすれ違うたびに何か病気でも感染しかねないかのように顔をしかめたりした。 子どもというのは大人から教わったとおりに不幸を蔑むものだし、 禁じられたらなおさらやってみたくなるものだ。 焼け跡が残る港町では、 盗みや悪ふざけをする友人に事欠かなかったし、 街を歩けば片目や手脚を喪ったひととすれ違った。 僕は自然と悪童仲間とつるんで弱い者いじめをするようになった。 身障者を見かけるたびに物真似をして取り巻きを笑わせ、 どれだけ教師に叱られようとやめなかった。 あるとき片脚のない包帯だらけの物乞いが僕を見るなり想像もつかぬ機敏さでいざり寄り、 奇声をあげて抱きついてきた。 当時の物乞いの多くがそうだったように元は軍服だったらしい襤褸を身につけていて、 顔はケロイドでただれていて瞼がなかった。 腐った膿の臭いがした。 物乞いはなぜか僕の名を知っていて、 戦争がどうとか別の自分がどうとか支離滅裂なことを叫んだ。 僕は恐怖のあまり失禁し、 力をふりしぼってその狂人を突き飛ばして逃げた。 その記憶から逃れるために僕はますます身障者を残酷にからかうようになった。
甘やかしてくれる伯父がなんの前ぶれもなく急死してからは、 反抗期の息子を持つ家庭がどこもそうであるように、 メンディップスではいい争いが絶えなかった。 父も伯父も人生から去ったことで、 自分が一族の男たちに不幸をもたらす呪われた存在に思えた。 その不安と苛立ちを伯母にぶつけてもいたのだと思う。 下宿人たちにはさぞいい迷惑だったろう。 あんたのために人生をどれだけ犠牲にしてきたかわかっているのかい、 と責めなじる声がいまも鮮明によみがえる。 罪悪感につけ込もうとする手口には苦い気持にさせられるけれど、 育児放棄の両親から救い出してくれたことを思えば、 けだしもっともな主張ではあった。 だからこそ僕は女王陛下にいただいた勲章を、 よりふさわしい持ち主として伯母に贈ったわけだ (その勲章はいちばんいい場所であるテレビの上に飾られた)。 僕は長らく伯母のことを、 甥を枠に嵌めたがる堅物と見なしていたし、 最初の妻Cにしても頑固な姑にはずいぶんと苦労させられたようだ。 でもこの歳になって思うのは、 伯母のほうが実は妹よりも反抗的で型破りな女性だったのではということだ。 関係者もみんな鬼籍に入り、 さすがにもう時効だろうから白状するけれど、 伯父がまだ元気だった頃、 彼女が下宿人のひとりとこっそりつきあっていたのを僕は知っている。 当時の既婚女性としては珍しいことに結婚指輪もしていなかった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)









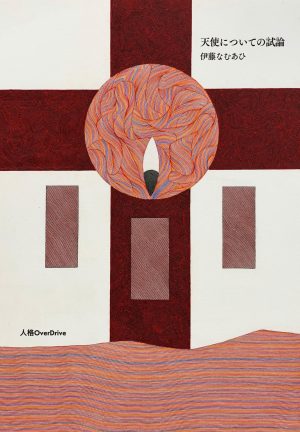
第一回がここから読めます
という投稿をしてrepostとfavoriteをすると、返信として投稿したものがコメント欄に、repostとfavoriteはヒーローヘッダの右下に表示される
これやってるやつ日本では見たことない
@ezdog えっ!これすごいです!(つい試したくなってしまいました……すいません)