まさにこの瞬間からBEの精神と前途は、 間抜けな笑みの東洋人と黒革上下の強面ロッカー、 ふたりの男に引き裂かれることになる。 恩知らずの僕らがとうに見限っていたマネージャから (おれみたいに痛い目を見たくなきゃしっかり契約を交わすことだな、 と忠告されつつ) その座を奪うことになるこの男、 最前列の女の子たちと同様に、 大股をひらいた僕の股間に釘づけだったとの説もあるけれど、 さすがにそれは眉唾だと思う。 別に友人だったから弁護するわけじゃない。 いくら僕の逸物が目立つといってもかれの位置からは単に遠すぎたからだ。 買い物中の僕らをいつも見張っている店主だと気づいたGが、 用向きを尋ねた。 ひがみ根性からの皮肉に育ちのいいBEは気づかず、 マイボニーを聴きに来たとばか正直に答えた。 かけてやってよとGは 「お父つぁん」 に頼んだ。 NEMSからお客さんです、 と司会者兼DJは回転卓に針を落として店内放送した。 聞きつけたMがあの間抜けな笑みで現れ、 やあBEさん、 あのときはどうもとか何とか挨拶し、 たいした縁なんかないくせに、 やけに深々と日本式のお辞儀をしやがる。 どうも何か意図があるようなふるまいに思えた。 というのは直後に僕のほうを見てニヤリと笑ったからだ。
気の早いことに翌日にはマネージャを買って出るBEは、 独グラモフォンのロンドン事務所を通してこの音盤を二五枚仕入れた。 注文分と予備の五枚を除いて陳列し、 「ザ・Bの音盤あり〼」 とみずから大書した紙を飾り窓へ貼りだし、 一歩退いて眺めて満足して肯き、 さてどうなるか見てみようじゃないのと事務室へ戻りかけたところ、 店の扉が勢いよくひらく音につづいて猿のような甲高い声が聞こえた。 振り向くとそばかすの少女が狂喜し商品を抱き締めるようにしてレジへ急ぐところだった。 その客と入れ替わりに数名の女の子たちが飛び込んできて商品をかっさらった。 噂が広まったらしく陳列した商品は数時間で売り切れた。 グラモフォンに電話して追加注文した五〇枚も入荷するなり飛ぶように売れた。 山師の気性のあるBEは商機を逃さじとばかり、 JVが撮ったアー写とともにこの音盤を携えて上京し、 大手小売店として多少のコネがあったEMIへ売り込んだ。 歌手ではなく伴奏を聴いてくれと無茶な注文をつけ、 その場で返事は得られなかったものの、 アー写の反応がよかったものだからプロにもっと撮らせようと思いついた。
新人マネージャが雇った禿頭の婚礼写真屋に、 僕らが黒革上下、 先の尖ったスウェード靴で気どってポーズを決めた翌週、 まだ調子がいい日もあったSは、 クリスマスを家族と過ごすためにAを連れて帰国した。 ロンドンに立ち寄った際、 Sは婚約者が贔屓にしていた演劇やバレエなどの舞台靴専門店で、 黒革のフラメンコ練習靴を買った。 痩せて背が低いのを気にしていたSは、 踵の高いその靴を履いて 「洞窟」 を訪れた。 僕とPはすぐさま奇妙な靴に目を留めた。 ピートBを牽引する足踏みはすっかりザ・Bの専売特許みたいになっていて、 床で打ち鳴らされるのを意図した踵は僕らの舞台によさそうだった。 どこで買ったのかNが尋ね、 教わった店名を僕らは心に刻んだ。 ファッションに目敏いGが最初に声をあげなかったのは思えばおかしなことだった。 Mの間抜け面を見るなりSの表情がこわばったのに気づいたのはGだけだったのだ。 僕は足許を見るばかりで親友の顔色に気づかなかった。 「洞窟」 の暗さはいいわけにならない。 医者でもなければまして未来の工作員でもない僕らには、 気づいたところでいかんともしがたかったのだけれど。
リザーランド市民講堂で地元人気を確実にしたそのちょうど一年後、 一一年ぶりの大寒波が訪れた夜に、 「洞窟」 で仲間のグループをいくつか招き、 僕らのファン感謝祭が催された。 華氏一六度の寒さにピートBは熱を出して寝込んでしまった。 そこで僕らはこれ幸いと、 たまたま体が空いていたハリケーンズのRに代役を頼んだ。 交互に舞台を務めた 「皇帝壕」 以来、 仲よくなっていたかれとは共演の機会こそ稀だったものの、 互いの公演を客として楽しむ間柄だった。 かれがドラムセットに座るとパズルの最後の一片が収まったかのように感じられた。 僕ら四人の演奏は最初からしっくりきた。 これだ、 と思った。 僕とPとGは互いに視線を交わし合った。 口に出さずとも思いは全員がおなじだった。 舞台が終わると僕らはRの背中をばしばし叩いて笑い、 四人で遅くまで話したり飲んだりした。 残念ながらこのときはそれ以上の縁がなく、 Rは三日後に 「先生」 こと先輩歌手との仕事のためにハンブルクへ発った。
大晦日に僕らはNが運転するヴァンに乗り合わせ、 吹雪と渋滞のただなかへ向かった。 十日ほど前にEMIから断り状が届いていた事実は知らされていなかった。 新人マネージャのBEは大舞台を前にしてわざわざ幸先の悪い報せを伝えたくなかったのだろう。 かれとはロンドンの宿で落ち合う約束だった。 いつもの小さなヴァンは助手席がいつも争奪戦で、 Mに教わった日本の遊び 「じゃんけん」 の勝者が座る決まりだった (「最初は石」 ってどういう意味だったんだ?)。 残りの三人は硬い後部座席、 さらに背後に楽器や機材が詰め込まれる。 ケースに収まったギターとドラムセットはともかく、 アンプやあとの荷物はハンドルが切られるたびにあちこち飛んでぶつかり合った。 どだい長距離移動に適した車じゃない。 そこで吝嗇家のくせに僕には甘いBEが気前よく大型車を借りてくれた。 さすが敏腕の商売人、 あいつのおかげでツキがまわってきたぞと僕らは思った。 クリスマスカードや目覚まし時計ばかりかデビューの好機まで贈ってくれた。 ついに夢が叶うのだ。 重役たちは僕らの演奏にきっと目を丸くし、 拍手喝采して高額の契約を結びたがるだろう。 Gなんか見るからにナーバスになり、 精神安定剤がほしいなどと弱音を吐いた。 帰国時に荷物に忍ばせて密輸した豆ッコは、 残りわずかだったので分けてやらなかった。
新人マネージャを僕らはまだ敬称で呼んでいた。 例によってすぐに一音節の綽名が定着し、 僕なんか好意につけ込んで無遠慮に、 あんたは音楽に口を出すな、 得意の金でも数えてりゃいいんだよおかまのユダヤ野郎め、 などと罵倒するようになるのだけれど。 その数日前、 かれが挨拶したがるのでメンディップスへ連れて行って引き合わせたら、 礼儀正しく機知に富んだ話し方をするこの男を、 伯母は拍子抜けするほどあっさり信用しちまった。 どうもうちの伯母は背広とネクタイと内羽根の靴に弱いらしい。 うちの子の面倒を見るのはあなたにとって、 ただの退屈しのぎかもしれないけど……と伯母はお茶を勧めながら釘を刺した。 万事失敗に終わって痛い目に遭うのは子どもたちのほうなんですからね。
あの気難しい伯母の信頼を勝ちとったのはMにつづいて二人目で、 しかもこの青年実業家の訪問目的を思えば、 これはたまげたことだった。 そこでこの僕も多少は信じてみようかという気になり、 「葡萄亭」 へ飲みに誘って、 秘蔵の豆ッコを気前よくご馳走してやった。 僕らは腹を割って話した。 MやKとそうしたようにだ。 当時違法だった性的指向を打ち明けられたのはそのときだ。 本人にしてみればトム・ティット・トットがその名をみずから差し出すかのような覚悟の告白だっただろう。 僕はといえばJVもAの師匠もそうだったし、 学生時代の友人にもいたから驚きはしなかった (驚かないからといって愚弄や嘲笑をしなかったわけではない。 ちなみにこの友人によれば統計上、 男のじつに四人にひとりは該当するのだそうで、 それを聞いた僕らは疑心暗鬼で互いの顔色を探ったものだ)。 公然の秘密としてだれもが揶揄しはじめるまで僕は口外しなかった。 というかわざわざ口外なんてしなくても香水つけて透明マニキュアなんて塗ってたら当時の英国ではバレバレだった。 我らがマネージャの存在が合法になるにはかれがうっかり度を過ごす一九六七年まで待たねばならず、 時代の変化はかれ——いや僕らにとって、 ちょっとばかり遅すぎた。
話を一九六一年の大晦日へ戻そう。 三二〇キロの旅路は順調にはいかなかった。 雪の吹きだまりに突っ込んだり、 凍結した道路にハンドルを奪われたり、 猛吹雪や濃霧に視界を覆われたり、 乗り棄てられた車に行く手を阻まれたりした。 一一時間もの長距離運転で、 しまいにはウルバーハンプトン辺りで道に迷った。 田舎者の僕らはロンドンの大晦日に憧れがあった。 鐘の音とともにトラファルガー広場の巨大な樅の樹のもとへ大勢が集まり、 蛍の光を歌って、 年越しの瞬間には僕らみたいな連中が噴水に飛び込んだりするものだと思っていた。 実際にはあまりの寒さに人通りは少なかった。 身を切るような寒さのなか、 僕らはチャリングクロス通りの楽器店を冷やかし、 アネロ&ダビデで一足の靴に群がって長時間見つめたあげく値札に首を振り、 食堂で一杯六シリングのスープにぼったくりだと騒いで店を蹴り出された。 酔っ払いふたり組にその車で草を吸わせてくれと頼まれてわけがわからず断ったりした。
靴屋で見たものを僕らは宿へ向かう車中で思い描き、 やっぱりあとで注文しようと心に決めた。 一足三ポンド一五シリング。 中央で縫い合わされた柔らかな黒革、 尖った爪先、 ゴム布で伸縮する履き口、 そして愛用のウェスタンブーツにも相通ずる、 傾斜した二インチの踵……この靴はやがて床で踵を打ち鳴らす僕らを、 虹の彼方へ連れて行ってくれることになる。 SそれにJVのおかげで、 三大登録商標のふたつまでもが物語に登場したわけだ。 残るひとつたる細い背広と、 それに付随したあれこれ——一曲ごとに深々と頭を下げるお辞儀やら、 舞台上での喫煙飲食罵詈雑言の排除やらで、 初期の僕らは完成する。 歳上の新人マネージャに躾けられた数々のうち、 背広については素直に受け入れがたい気持もあったけれど、 地元を一歩出れば黒革上下なんて古臭すぎてお笑い種でしかなかったので、 金のためなら何でもやってみようという気になった。 ガムを噛むのは前より控えたし、 最前列の常連を贔屓するのもやめた。 CやBEが困惑して眉をひそめ、 Mもまた憤然と説教を垂れてきた身障者の物真似だけは、 だれに何といわれようと断固つづけた。 それはある意味で僕自身を表現するものだったからだ。 階級の高い連中にも気に入られるように、 と叩き込まれたわざとらしい滑稽なお辞儀については、 いつか着想源を問い質してやろうと思ったまま六七年を迎え、 ついに機会を逃してしまった。
とはいえこの時点で僕らはいまだ黒革上下の臭い野郎どもに過ぎなかった。 宿に着くなりBEとの挨拶もそこそこに僕とP、 GとピートBの部屋に分かれて、 例の目覚まし時計をセットして寝台に倒れ込み、 翌日午前十時からの審査に備えた。 疲れ果てていて夢は見なかった。 それはあす現実になるのだ……このときはまだそう思っていた。 翌朝、 地下にある憧れのデッカ第二録音所に集結した僕らは張り切っていた。 都会人にリヴァプール魂を見せつけてやるぜ! 車から僕、 P、 Gはそれぞれの楽器を、 NとピートBは秘密兵器の 「棺桶」 を運び入れた。 おなじ地下でも 「洞窟」 の狭い階段と較べれば楽なものだ (ふたりは例によって文句を呟いていたけれど)。 準備万端、 腕が鳴るぜ! ところが責任者がいつまで経っても現れない。 僕らは木目の床に立たされたまま苛々しながら待った。 プロの録音ってそういうもんなのか? 何分はじめてでわからなかった。 BEは侮辱と見なして激怒した。 僕らと大差ない若さの責任者は二日酔いで現れた。 あけましておめでとう、 昨夜は噴水には飛び込まなかったみたいだけどとGが皮肉をいった。 その冗談は無視され、 ようやくマイクやら何やらが位置決めされて楽器はアンプに繋がれ、 窓の向こうで技師が調整卓に着き、 赤色灯がついた……。
いざ本番!
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)





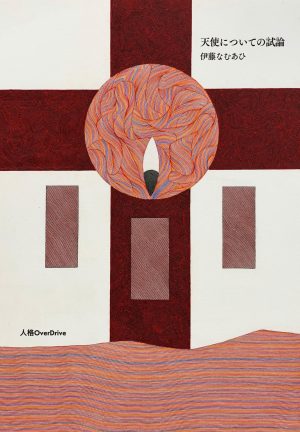




コメントテスト
@ezdog@ezdog.press Mastodonサーバから返信テスト