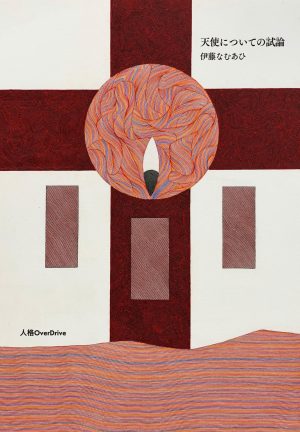幸福とはそのさなかにあっては気づけないものだ。 何年もあとになって僕は、 友人のように親しいファンだけに囲まれて演奏していた 「洞窟」 時代を懐かしむようになる。 あれがザ・Bの歴史でもっとも幸せな時代だった。 落ち着きのなさをたびたび伯母に叱られ、 ときにMにまで窘められた僕は、 おなじところに留まるのが極めて苦手だ。 僕はいつだって変わりたい。 でなきゃ退屈してしまう。 Mがずっと別人になりたかったと打ち明けてくれたことがある。 その願いは叶ったんだけどね、 ともいわれて困惑したけれど、 あれはきっと 「前世」 について語っていたのだろう。 あいつとちがって僕は自分が大好きだ。 JLであることに厭気がさすことはない (いや、 長い生涯に一度くらいはそんな瞬間があったかも……僕だって人間なのだ)。 変わりたいのはただ、 新しい世界を見てみたいからだ。 居心地のいい場所に安住するよりも、 茨の道でいいから次の舞台へ進みたい。
前章の最後にたわいない日常と書いたけれど、 あの頃の毎日は僕にとってあまりにもたわいなさすぎた。 妹や弟みたいな十代の子らに騒がれても地元を出ればまったくの無名。 リヴァプール中の会場をいくら巡回してみたところで、 単独での音盤デビューは夢のまた夢。 ビートブラザーズ名義のドイツでの録音はさっぱり売れなかった。 スコットランド民謡のロックンロール版なんて需要がなかったのだ。 そもそもどこでも扱っていない、 あたかもこの世に存在せぬかのように。 少なくとも地元じゃそうだった。 品揃えのいい 「北端音楽店」 略してNEMSのホワイトチャペル店でさえもだ。 僕らはそこへたびたび押しかけて舶来ものの音盤を漁り、 おいこれを演ろうぜ、 これも試したいね、 見てよこんなのもあったなどと試聴ブースで押し合いへし合い、 グリス臭い頭を寄せ合って、 まだ見ぬ大陸の音楽を乾いたスポンジさながら熱心に吸収した。 でもそれはあくまで一方通行。 僕らの音を世界が聴くことは決してなかった——この時点ではまだ。
僕やBEのように生活に倦んで変化を求める者もいれば、 そのたわいない日常を切望しながら死んでゆく者もいる。 Mが話していたのはきっとそういうことだったのだ。 Aの国では切り分けた取り分を巡ってケネディとフルシチョフが対立し、 敗戦まで首都だった街が深夜零時に突如として鉄条網で分断された。 やがてコンクリートの巨大な壁が築かれ、 そこに暮らす者はだれもが親戚や友人、 恋人、 たまたま境界を越えていた家族と引き離され、 越境を試みれば射殺されることになる。 そうしたことが二八年後の政治局員の失言までつづき、 SとAがともにその日を迎えることはなかった。 食材を抱えて市場から帰宅したAの母親が溜息をつくのでSがわけを訊くと、 顔なじみの八百屋の女将が、 親戚の子が東へ遊びに行ったまま戻らないと不安そうだったという。 Sの大学の同級生にも知人や親戚が東にいる者は多かった。 戦争は終わらないんだ、 とSは僕への手紙で書いている。 一度はじめてしまえば互いの土地から暮らしや人生を根こそぎ奪い、 何もかも変えてしまう。 僕がなんて返信したか憶えていない。 兵士にはなりたくないとか、 国境のない世界へ逃げたいとか書いたような気もするし、 そのことには触れずに下世話な冗談で笑わそうとしたようにも思う。 二〇歳そこそこの僕には難しすぎた。 正直にいえばいまだにわからない。 スーパーマンを撮った監督とスペインへ行って腹を撃たれて死んでみても、 幻覚剤をやって夢うつつにMの話を聞かされても、 幼少時に東京で空爆を経験した妻と寝台や袋に収まって報道陣に囲まれたり、 爆破テロで金を集める活動家らと政治集会に参加したり、 それらすべてを放り出して隠遁したりしてみても、 何ひとつわからぬままだ。
Sが不安げな母娘とともに屋敷のテレビを見つめた翌月、 正確には九月三〇日のこと。 二一歳の誕生日をひと月後に控えた僕は、 おいスペインへ休暇に行くぜとPに声をかけた。 は? 何いってんの、 そんな金あるわけないじゃんとP。 それがあるんだなと僕はニヤリと笑って札束を見せびらかした。 僕らが生まれてはじめてお目にかかる百ポンドもの大金だ。 あいつは息を呑んでどうしたんだよそんな金、 といいかけて、 まさかおまえ……と青ざめた。 僕は笑って、 親戚にもらった成人祝だと明かした。 Pはすげー、 おまえの親戚金持だな、 おれもおこぼれにあずかれるのかと昂奮し、 それから急に疑わしげな顔になって、 仕事はどうすんだよ、 GやMも連れて行くのかと矢継ぎ早に訊いてきた (常勤の付き人になったばかりのNはともかく、 ピートBのことは最初から僕らの頭になかった)。 いやおれとおまえだけだと僕は答え、 まずは山高帽を買おうぜ、 ヒッチハイクにはあれが必要だといった。
果物取引所の裏、 「洞窟」 入口の真向かいにある 「葡萄亭」 の奥部屋で、 僕らが 「お父つぁん」 と綽名したボブWと二対一の口論になった。 マホガニーの横木に木彫りの葡萄が吊されたパブで、 僕らはよく終演後にその店に入り浸った。 その日なぜピートBはともかくGが同席しなかったか憶えていない。 たぶん如才ないPが狙って段取りしたのだろう。 DJ兼司会者には何考えてるんだと当然のごとく猛反対された。 ファンってのは移り気なんだよ、 こっちのグループからあっちのグループへ簡単に乗り換える、 せっかく万事順調なのにひと月も不在にしたらこれまでの苦労が水の泡じゃないか、 あとのふたりはどうなる、 おまえらがいないあいだ収入が途絶えるんだぞ、 穴を開けた仕事はどうすんだ、 興行主たちが許すわけないじゃないか、 あまりに無責任すぎる……云々。 いいじゃん殺されはしねえだろハンブルクじゃないんだからと僕はいった。 そういう問題じゃない、 とひとまわり半歳上の 「お父つぁん」 は呻くように溜息をついた。 保護者気どりの説教を僕とPは煩わしく思いつつ、 かれが心からザ・Bを気遣ってくれているのを感じて、 いつものように耳を塞いでみせるような反抗的な真似はしなかった。 しまいに僕らは根負けして、 わかった二週間だけにするよといい、 十月一五日以降の出演は取り消さなかった。
殺されこそしなかったものの、 当時の相場としては法外な出演料を払っていた興行主らはひとり残らず激怒した。 Gも怒り心頭だった。 キャンセル一回につき五〇ポンド稼ぎ損ねたからだ。 かれは仕事も練習もだれよりも熱心に、 真摯に取り組んでいた。 音楽を辞めたらPには会社勤めに戻る道があったし (あいつなら重役になれたろう)、 僕はろくでなしの親父譲りの楽天主義でどうにかなると思っていた。 漫画だって得意だし、 それこそ親父みたいな船員になって世界中を旅したっていいし、 なんなら友だちを脅して金をせびる手もあった。 ピートBには母親の店を継ぐとか公務員になるとかがあったし、 現に僕らに馘にされたあいつは、 BEに紹介されたグループの仕事をわざわざ蹴って職安に勤めた。 のちに仲間に加わるRには役者の才があり、 ピーター・セラーズの養子になって金属下着のラクエル・ウェルチに鞭打たれたり、 人面機関車と化して子どもたちの英雄になったりの未来があった。 Sは画家だったし、 Nだって僕らに巻き込まれなければ会計士になっていたはずだ。 Gには音楽しかなかった。 映画のプロデュースもインドもF1も僕にいわせりゃ道楽でしかない。 強制送還のあと連絡を怠った僕を責めたのも、 もっと早く活動を再開できたのにという糞真面目な理由からだった。 なのにあの頃の僕とPときたら、 我らがリードギタリストをまだ幼い弟分のように扱っていた。 ましていつしかマネージャ役を押しつけられ興行主との交渉や日程管理をさせられていたピートBが、 いかに頭を悩ませようが知ったことではなかった。
水入らずの旅行に誘われたPは、 Mの邪魔が入るのを警戒していた。 僕はまるで気にしなかった。 金を出すつもりは毛頭なかったけれど、 来たければあの不思議な力で勝手についてくるだろうと思っていた。 Pの不安は杞憂にすぎず、 僕らはあの奇妙な日本人のことを旅行中ほとんど忘れていた。 あいつはきっと伯母とCのことで忙しかったのだろう。 伯母には描いた絵を外国に売りに行くと嘘をついた。 Mに声をかけなかったのと同様に、 Cを連れて行く発想も僕にはなかった。 おたわけ兄弟はどちらも婚約者をほったらかして平気だった。 そのように扱っていながら愛される特権が自分らにあり、 愛する義務が彼女らにはあるのだと当然のように信じていた。 Pは何度かの失恋を経て大人になり、 家族を愛することを知った。 僕はいつまで経っても子どものままで、 すぐ飽きて次へ行く癖はYに躾けられるまで変わらなかった。 そのことでMはずっと僕に腹を立てていて、 卵巣癌で死んだ歳上の愛人のことも渋い顔をしていたし (ハンブルク時代の狼藉には目を瞑っていたくせに!)、 一九六七年以降はYのことで幾度となく口論となった。 その三年後の決別もあいつが財務管理のことでPの、 収録曲と作曲能力のことでGの肩を持ったからばかりではなく、 女たちへの僕の態度のせいもあったように思う。
かつてGと試した経験から、 英国旗をケープみたいにまとったり山高帽を被ったりすると車に乗せてもらいやすいのは知っていた。 ナンパのときにはその帽子を脱いで隠すのだ。 僕とPが道ばたで親指を立てたり、 異国で裾広がりのパンタロンを穿いて美人に口笛を吹いたり (風呂や洗濯をきらう僕らのかぐわしき性的魅力は、 パリジェンヌにはいささか刺激が強すぎた。 歩くたびにはためく裾はすぐに針と糸でもって細く改造された) していた頃、 Cは伯母のいびりに耐えきれずメンディップスを出ていた。 ハンブルクから僕が書き送ったヘンリー・ミラーばりの、 長大にして大量の恋文を伯母に見られたからだ。 伯母がCの部屋に侵入して私物を漁ったとは思いたくないけれど……まぁ、 漁ったのだろう。 Cは涙ながらにリヴァプール北部の親戚の家へ転がり込んだ。 慰めるのはすっかりMの役割になっていた。 僕の嫉妬深さをよく知る連中から、 僕がふたりの仲を疑わないのは奇妙だと当時も婚姻中もよくいわれた。 それはMを知らないからだ。 あいつはなんというか……そういうのに縁がない人間だった。 きみも会ったことがあれば同意したろう、 あいつはただそんなやつなんだ。 そこを変に勘違いする輩もいて、 「お父つぁん」 やJVは単にああいうのが好みではなかったようだけれど、 BEの場合はいささか事態がこじれた。 被虐趣味でもあったマネージャは、 間抜け面の下に隠された臭いを本能的に嗅ぎとっていたのだ——自覚のあるなしは別にして。
ザ・Bの休業はさまざまな憶測を招いた。 ボブWが薄情な健忘症と決めつけた女の子たちは、 僕とPがあとのふたりを置いてパリへ演奏旅行に出かけたと信じた。 彼女らが噂する声は大きすぎてリヴァプール中を駆け巡り、 海を越えてハンブルクまで届いた。 Sは信じられないと首をひねった。 分裂はあり得ない。 まずいベーシストだった自分と同様にピートBを切ることはあってもGは残すだろう。 ザ・Bの核はあの三人なのだ (この事実がのちにRを悩ます)。 そんな騒ぎになっているとも知らず、 僕らは爆破テロや独立戦争のデモや抗議集会での銃殺に揺れるパリを、 ホテルから何マイルも闊歩した。 カフェで議論する芸術家にでもなった気分だった。 もちろん僕らに政治は無縁で、 仏語も解さないから、 パリ市民がなぜ電器屋のテレビに群がるのか、 ド・ゴール大統領が何を演説しているのかまるで知らなかった。 十月九日、 Pはハンバーガーを奢って誕生日を祝ってくれた。 僕らはあの街の何もかもが気に入ったけれど、 いずれ僕らに倣ってイエイエと呼ばれることになる紛い物のロックンロールにだけは感心しなかった。 フランス人に本物を教えてやろうぜ、 と盛り上がって劇場へ押しかけたけれど、 興行主との会見を取りつけるどころか警察を呼ぶぞと係員に脅された (ポリスとかポリシエといっているのは聞きとれた)。 スペインまで行くのは億劫になって挫折した。 どのみち金も尽きるし、 一五日の公演に間に合うよう帰国せねばならない。 パリで充分じゃんということになった。 代わりにセーヌ川から二百歩の高いビル陰にある、 ボーヌ通り二九番地のJVの下宿へ向かった。 夜間の訪問客を部屋にあげることは、 接客係の婆さんによって堅く禁じられていたけれど (JVが男で、 僕らも男だったからだろう) 昼間なら問題なかった。
実存主義への憧れから移住までしたJVは、 床屋を粛正したヒトラーみたいな髪型をしていた。 ジャン・コクトーの映画に出ていた役者 (兼愛人) の真似だ。 現地の女性に敬遠される理由に気づかぬ僕らは筋ちがいの改善に余念がなく、 ぜひその髪型にしてくれと頼んだ。 Sが婚約者にそんな頭にされたときには腹を抱えて指さして爆笑したくせにだ。 JVは困惑し、 無骨なロッカーのきみらが好きなんだよと渋った (臭いまで好きだとはいわなかった——尋ねたらたぶん、 風呂には入れと忠告されたろう)。 かれが愛したのがザ・BというよりGなのは公然の秘密だった。 僕らを差し置いてGひとりを呼び出して撮ったのを、 数日後にみんなでマイクに身を寄せ合う場面なんかを撮ってもらうまで、 僕とPはちょっぴり根に持っていたくらいだ (ちなみにこのときの一枚はのちに訴訟対策で製作したカヴァー集を飾った)。 ケチ臭いこというなよ、 おれらがいいんだからいいんだよと僕らは強要した。 グリスまみれの僕らの髪はぶった切られ、 寝台の下に掃き寄せられて、 翌朝、 掃除に訪れた婆さんを絶叫させることになる (女性を絶叫させることにかけちゃ僕らはプロだ)。 長年センターロールリーゼントに慣れきった髪の毛は分け目を拒否し、 櫛や手で幾度撫でつけてもすぐにまっすぐ整列した。 帰国したら案の定みんなに笑われ、 異国情緒に酔って浮かれていた僕らも正気に返って、 慌てて戻そうとしてみたけれど、 あいつらは持主同様に反抗的で、 今度はグリスさえも受けつけない。 どうでもよくなってそのままにした。 世界中の子どもたちに数年後、 鬘がばか売れすることになる髪型はこうして生まれたってわけだ。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)