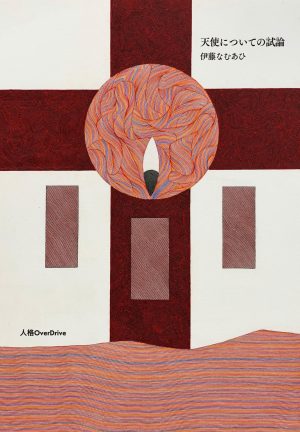Sは頭痛と眩暈に苦しみながらも、 寸暇を惜しんで情熱的な色をひたすら画布に叩きつけ、 ナイフで切りつけ、 粘土をこねてキャメラをまわし、 僕に負けじと長文の手紙を書き送った。 わずかなりとも治療費の足しにすべく、 楽器を借りて地元グループと舞台に立つことさえあった。 無理が祟ったか大学で受講中に卒倒し、 屋敷へ担ぎ込まれた。 Aの母親が呼んだ訪問医も過労のせいと診断し、 栄養剤を処方して、 煙草をやめて食餌療法をするよう説教しただけで帰った。 Aの母親はそれから毎日、 脂肪を丹念に取り除いた滋養たっぷりの料理に心を砕いた。 僕も次男を育てていた一時期、 パン生地をこねたり魚を焼いたり味噌汁をつくったりしていたからわかるのだけれど、 これは楽なことでない。 にもかかわらずSの病状は悪化する一方で、 発作のたびに婚約者とその母親に当たり散らすようになった。 母娘がかれを見放さず、 ひたすら耐えて介護したのは賞賛すべきか憐れむべきか。 Yに車椅子が必要になっただけで途方に暮れ、 手際よく世話をする次男や使用人に置いてきぼりを喰らったかに感じる僕には想像もつかない。
二月後半にSは数日間、 手術を終えたばかりの母親に会うために帰省した。 本来ならかれ自身が手術を受けてしかるべきだったのに。 僕らにとっての救いはこのときのSは病状が一時的に寛解していて、 ともに和やかなときを過ごせたことだ。 Gの家では夕食の席に温かく迎え入れられた。 僕とはむかしのように長時間話し込んだ。 頭痛のあまり窓から飛び降りそうになったことを冗談めかして話されて僕は困惑した。 立場が逆ならSはきっと心を軽くするようなことをいってくれたにちがいないのに。 当時ボーリングが流行っていて、 朝四時まで酒が飲めたので、 僕らみたいな商売の人間はよくたむろしていた。 そこでの集まりに元マネージャも呼んだ。 揉めた時期もあったけれどこの頃ではわだかまりも薄らぎ、 何よりかれはSとAのことを気にかけていた。 そのかれがSを見るなり愕然とした。 なんてこった、 おまえまじで具合悪そうだぞ。 それまであえて触れずにいたみんなは黙った。 僕が何もいわなかったせいだ。 前にも書いたけれど僕はひどい近視で、 しかも男子たるもの弱みを見せてはならぬと信じ込んでいたから、 映画で評判を取るまで人前で眼鏡をかけなかった。 親友が死にかけているのに気づかなかったのはそのせいかもしれないし、 気づきたくなくて見ようとしなかったのかもしれない。 そういうことは自分ではわからぬものだ。
みんなはおずおずと僕を、 それからSを盗み見た。 母や妹たちにも逢えたし、 とSは蒼い顔で笑った。 ハンブルクに戻ったらすぐに健康を取り戻しますよ。 Aが待ってますからね、 早く絵で喰えるようになって結婚してやらなきゃ……。 その夢が実現せぬことをSはどの程度わかっていたのだろう。 Aは生涯で何度か結婚することになる。 惰性のようにKと婚姻した時期さえあった。 でも最期まで忘れられなかったのは夫にできなかった男ただひとりで、 深夜のボーリング場にいた仲間でMだけがそうなることを知っていた。 知っていて僕に黙っていたのだ。 未来の医療でもSは救えなかったのだろう、 生前最後に会ったときのかれの態度からもそれはわかる。 でもなんの気遣いのつもりか知らないけれど、 肝心なことをいつも話してくれなかったあの男を僕は許すつもりはない。 ずっとあとになってPの弟に聞いたところによれば、 Sは婚約者を残してきたから早く帰りたいが、 ハンブルクに戻ればよくないことが起きそうな気がするとかれに話したという。 ピートBとの別れ際には、 逢うのはこれが最後になるとまでいったそうだ。
Sが画布にぶつける絵具は日増しに色を喪い、 血のように暗くなった。 つい数年前に僕が競売で手に入れた一枚には、 描いた若者を知る老人にとっては見るのが怖ろしくなるような禍々しい迫力がある。 毎年恒例の学園祭をAやKと楽しんでいたとき、 Sはまたひきつけを起こして卒倒した。 翌日にはそれまででもっとも烈しい頭痛に見舞われ、 目が見えないと騒いだ。 それきり大学は休学せざるを得なかった。 Sは僕への手紙以外にも大量の文章を残していて、 Aは亡くなる数年前にその一部を見せてくれた。 金属的な耳鳴りがして視界が歪み、 脳が潰されそうな痛みがつづくとかれは走り書きしていた。 後半が判読できなくなり蚯蚓のようになって途切れるその言葉を読んだとき、 僕はヘロインの離脱症状を思いだした。 僕のは自業自得だがかれのは避けられぬ不運だった。 Sはその苦痛を紛らすため、 獣のように吼えて頭を壁に打ちつけ、 筆やら絵具やら油瓶やら絵皿やらを手当たり次第に投げつけた。 病状を娘に告げぬようSに約束させられたAの母親は、 耳を塞ぎソファにうずくまって耐えるしかなかった。 娘のほうは婚約者が死にかけているのに忙しさのあまり気づかなかった。 JVがパリへ移住して写真館が人手不足だったからだ。 口止めされたのはKもおなじだった。 頻繁に見舞いに訪れていたかれは、 のたうちまわり部屋中に嘔吐する親友と、 懸命に介護するAの母親とを目撃している。 やがてSは一日の大半を寝床で過ごすようになり、 大きな画板に紙を留めておいて、 痛みが薄らいだ隙にそこへ絵を描いたり、 長文の手紙を大量に書き散らしたりした。 そのときの手紙を僕はまだ持っている。 Aに聞いた話では僕を主人公にした小説まで書いていたそうだ。 その物語にはMも登場するのだろうか。
Sは寝たきりになる直前まで按摩に通っていた。 それで少しでも症状がやわらいだのならいいのだけれど。 ある日その帰りに路地へさしかかった。 かつて黒い渦にMが消える幻覚を見て卒倒した場所だ。 不安と恐怖がよぎったが、 強迫観念を打ち消すためにあえて踏み入った。 あの不吉な子ども版ザ・Bはいなかった。 代わりに別の禍々しいものを目撃した。 宙に浮遊する器械だ。 深海に棲む海蜘蛛を思わせる形状で、 複数の脚に低く唸る回転翼がついている。 行き交う通行人に奇妙な目で見られながら追いかけた。 そうだおれはとうとう本当に狂ったのだ、 こんなものが見えるのだからとかれは思った。 葬儀屋の前で見失った。 Sは両膝に手をつき、 荒く息をしながら飾り窓へ顔を上げた。 骸骨のような蒼い顔が映る。 その向こうの白い棺桶をかれはじっと見つめた。 帰宅したSはあれがいいとAの母親に頼んだ。 とても美しくて気に入ったよ、 普通のはつまらない、 芸術家らしく葬ってほしいんだ。 ばかなことをいわないでとAの母親は窘めた。 あなたはまだ若い、 旅立つのはわたしのほうがずっと先よ。 気休めの嘘であるのは双方がわかっていた。 母国へ遺体を運ぶ段取りとなったとき、 Aの母親は狂ったようにこの白い棺桶に固執することになる。
一方そんなことになっているとは知らぬ僕らは、 三月六日 (足すと九になる) にバーケンヘッドの仕立屋へ出向き、 赤い格子柄のファスナーつきビニール鞄と引き換えに、 またしても悪臭を後に残してウッキウキで店を出た (背広はお気に召さないなんてだれがいった?)。 翌日にはマンチェスターのプレイハウス劇場でBBCラジオの初収録があった。 当時の国営放送には申込者に無料で出演審査を受けさせる義務があり、 無事に受かった僕らは収録に間に合うよう背広を仕立てたってわけだ。 このとき抽選で集められた観覧客が、 約一名を除いてグリスなんてつけず清潔に櫛を入れた髪の、 最先端モッズスーツとフラメンコ靴で決めた新しい僕らを初めて目撃することになった。 Pの弟は僕らの晴れ舞台を観覧席から激写した。 僕らとしてはずいぶんとお上品に変身したつもりだったけれど、 それでもお堅い国営放送では完全に場違いで、 プロデューサーや伴奏を務める一九人の楽団員は渋い顔をしていた。 司会者は僕の歌をリズム&ブルースと紹介した。 まだそんな言葉が英国では知られていなかった頃だ。 それどころかモータウンの曲が公共の電波に乗るのさえ本邦初だった。 六分間の放送を聴くためだけに僕らはピートBの家へ押しかけ、 モナB所有の高性能ラジオの前に陣取った。 VHF (いまでいうFM) の電波を高感度で受信するには普通のラジオじゃだめだったのだ。 僕らの演奏は今度こそ上々で、 居間のスピーカからはあの日あのときの歓声、 手拍子、 そして女の子たちの甲高い絶叫が流れた。 僕とPは顔を見合わせてニンマリした。 日頃は冷静沈着なピートBでさえ浮かれていた。 僕ら三人は互いに手を高く打ち合わせ、 おれたちはラジオスターだ! と叫んで飛び跳ねた。 この面子で意気投合したのはこのときが最後だったかもしれない。
地元ファンへのお披露目は四月五日 (これもだ)、 「洞窟」 のファン感謝祭でだった。 「お父つぁん」 が僕らのために考えてくれた演出はこうだ。 まず第一部では黒革上下のなじみ深い格好で登場する。 いつもの曲で盛り上がったところで楽屋へ戻り、 お召し替えののち再登場して、 自作曲とともに新しい僕らを披露するという段取り。 「洞窟」 には五百人いや六五〇人はいるだろう若者が詰めかけて、 チケット両面に刷られた入会申込書の記入と引き換えに、 ワラシーヴィレッジの禿げた婚礼写真屋に撮ってもらったブロマイドを受け取った。 数日後には全員に会員証と会報それに特典の案内が届くという寸法だ。 最前列では猫のように目を細めて間抜けに笑うM、 愛用の箱形写真機を手にしたPの弟、 僕とPそれぞれの婚約者、 ファンクラブ秘書のフリーダK、 及びボビーBと、 彼女の紹介で僕らと親しくなった逓信公社の電気技師、 僕らをエルヴィスの衣鉢を継ぐ英雄と仰ぐ、 心優しき眼鏡の大男マルE……といったいつもの面々が期待に顔を輝かせていた。 とりわけこの企画のために奔走してきたボビーBは、 新しい僕らが受け入れられるか否かを僕ら以上に気にしていた。 心配は杞憂だったものの彼女自身は思いがけない大失敗をすることになる。
半時間ほど前、 のちにBEの事務所に加わることになる前座グループが場を暖めるあいだ、 僕らはマルEとボビーBを楽屋へ招き、 こっそり持ち込んだウィスキーをまわし飲みした。 掃除用具入れほどの空間に付き人のNはもちろんMまでいたので身動きとれぬほどギュウ詰めだ (僕の婚約者とPの恋人は締め出されていた——いつものことなので彼女らは諦めていた)。 Mはきっと僕らと被らないようにしてくれたのだろう、 着たきりでくたびれはじめていた例の背広ではなく、 どこぞの古着屋で仕入れたらしい大学生みたいな薄いセーターとジーンズ姿。 二七歳の巨漢の電気技師も似たような格好で、 これまた学生そのものの格好をした一八歳のボビーBは、 不純異性交遊はおろか酒すら未経験。 大丈夫だって、 いいからこっち来て一杯やりなよと僕はしつこく誘い、 ついに口数少ない生真面目な彼女を酔っ払わせるのに成功した。 Mは明らかに悪乗りしておもしろがっていた。 やたら未来の倫理観を振りかざすくせに、 酒と薬にかんしては抑制の利かぬところがあいつにはあった。 Pは口こそ出さなかったものの心配そうに僕とボビーBを見ていた。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)