ひとたび滑り出すと商談はトントン拍子に運んだ。 ロンドンに呼び出されたBEはGMと握手を交わすや、 のちに僕らの音盤で世界中に知られることになる横断歩道を渡って、 サーカスロードにある聖ジョンズウッド郵便局で電報を打った。 僕らの返事はこうだ——P 「印税前金一万ポンド送金サレタシ」、 G 「ギター四本注文サレタシ」、 僕 「イツ百万長者ニナレルカ」 ……。 僕らはBEのいう 「新曲」 を文字通り、 いまだ世に存在せぬ曲の意味にとった。 ゴフィン&キングならぬおたわけ兄弟再始動だ。 実際EMIは演奏やタレント性ではなく楽曲に関心を持ったのだから、 まんざら見当はずれでもない。 僕らは 「風車ツイスト」 や 「九〇九のひとつあと」 よりマシな作品をつくるべく、 互いの頭と楽器を突き合わせて、 ああでもないこうでもないと奮闘した。 帰国の少し前、 例の先輩歌手と契約を消化するための追加録音があった。 もうデビューが決まったつもりでいる僕らは上の空で、 Pはかれのことをもう先生とは呼ばなかった。 その音盤が公式に発売されたかどうかすらも僕は知らない。 三度目のハンブルク滞在中、 故郷では僕ら以上にさまざまな変化があった。 僕とPそれぞれの婚約者は隣同士のフラットに住んでいたし、 ピートBに至っては母親のモナBは親友Nの子を妊娠中、 同居していた祖母は癌で亡くなっていた。 Pは弟への土産にAとおなじ写真機を買った。 僕は旅行鞄に隠せるかぎりの豆ッコを詰め込み、 Sの遺品をAに譲ってもらった。 紺と黄色の縞に編まれたマフラーでいまでも持っている。 Kのフィアットで空港まで送ってもらったGは、 いつか金持になってプール付きの家とそれに、 バス運転手の父親のために新しいバスを買うんだ……などと浮かれて話した (プールは当時の僕らにとって成功の象徴だった。 実際に手に入れてみれば維持が大変で何もいいことはなかった)。 そうして僕らはEMIでの録音と二度目のBBC収録のために、 得意満面でルフトハンザ機に搭乗した。 最初のときの強制送還とはえらい違いだ。
上京の前々日は 「洞窟」 で午後三時から六時半まで練習した。 その翌日は夜公演がなかったので七時から使わせてもらった。 練習場所を見つけるだけでもひと苦労だった学生時代を思えば、 経営者の厚意は身に染みた。 しかしいま振り返ればこれは善し悪しだった。 僕らの爆音は低い天井と岩壁に囲まれていてこそ特有の迫力が得られた。 何度も海を往復して地下の湿気のなかで酷使されてきた機材がすっかりだめになっているのに、 その効果に騙されて気づけなかった。 僕らは自分たちの持って生まれた才能と、 三度にわたる武者修行で培った演奏技術、 それにリッケンバッカーやグレッチ、 ヘフナーといった愛用の楽器を過信していた。 いかにそれらが優れていようと機材の欠陥は救えない。 悪天候や交通渋滞に巻き込まれてもいいように、 今度こそ何ひとつしくじるまいと前乗りするほどだったのに、 秘密兵器 「棺桶」 をはじめとする機材の数々が、 デッカでまともに機能しなかった意味を僕らは考えなかった。 技師や管理者の苛立たしげな溜息や、 収録所に転がっていた古い機材に有無をいわさず換えさせられた理由がわかっていなかった。
暗く垂れ込めた空と猛吹雪で白黒映画のようだった前回とは打って変わり、 六月上旬の空は明るく晴れ渡ってうだるように暑かった。 黒塗りのタクシー、 赤い二階建てバス、 緑豊かな公園の木々、 腕や脚を出して闊歩する女たち……。 瓦礫も妙な臭いのする空き地も崩れて煤けた建物も見当たらない。 真新しいぴかぴかの建物ばかりで、 故郷との差を見せつけられた。 僕らはまさしく絵に描いたようなお上りさんだった。 はぐれないよう本能的に固まって、 きょろきょろと落ち着きなく周囲を見まわして歩いた。 六月六日水曜日の夜、 Nはファンの落書きだらけのヴァンを駐車場へ乗り入れた。 収録のために来たザ・Bだとかれは守衛に告げ、 二度も聞き返された挙げ句に妙な顔をされた。 僕らは玄関ではなく、 古い民家後方の左手を降りたところから建物へ入り、 右へ左へ曲がって第二録音所へ機材を運び込んだ。 天井の高い広い部屋で窓はなく、 部分的に敷物がある寄木細工の床には、 さまざまな機材や巨大な白い衝立が並んでいた。 長い階段をのぼると四分の一インチのオープンリール機器二台を備えた調整室がある。 みんな虚勢を張っていたけれど内心ではデッカの悪夢がよみがえってビクついていた。 ホテルではちゃんと風呂に入ったし、 例の背広を着て髪に櫛も入れていたのに、 それでもEMIの連中は僕らを二度見した。 当時の基準では髪が長すぎたせいかもしれない。 なんでこんな訛り丸出しの田舎者が? とでもいいたげな顔でじろじろと見られた。
採用審査ともシングル制作ともつかぬ録音は七時にはじまった。 案の定、 和やかな空気とはいえず、 白衣の技師たちに囲まれた僕らは摘出される悪性腫瘍にでもなった気分だった。 苦楽をともにした大切な機材はまたしても侮辱的な扱いを受けた。 僕らの機材から連中が得たのはばちばち、 ぷちっという大量の雑音とぶーんというハム音、 それに異世界から響いてくるかのような、 ふぁんふぁんとかほえほえ……といった正体不明の音だけだった。 NとピートBが苦心して運び込んだ 「棺桶」 は、 Pが弦をちょっと弾いただけで重くて巨大なだけのガラクタと判明した。 どうにかテープに収められる録音レベルにするのに、 連中は地下の残響室から重いタンノイをひっぱり出してこなければならなかった。 振動して骸骨の歯みたいにカタカタ鳴る僕のアンプは、 誇張ではなく実際に紐で縛られた。 よく憶えていないけれど確かピートBのシンバルにも何か問題があったようだ。 最終的にはどうにか調整され (技師たちはまだ渋い顔をしていた)、 僕らは眠っていても弾けるおなじみの曲をひと通りおさらいして、 赤色灯がつくや一曲目のベサメムチョに取りかかった。 地元でもハンブルクでも聴衆の反応がよかったので当時の僕らはこれを代表曲と見なしていた。 しかし全英のお客さんが音盤で聴きたいかとなると話は別だし、 EMIが求めたのは僕らの演奏ではなく出版権だった。 「洞窟」 では大受けの合いの手ちゃちゃ、 ぶーむ! にも白けた反応が返ってきたばかりか、 それやめてといわれた。
書いたばかりの自信作 「ラヴ・ミー・ドゥ」 をやると調整室がざわつくのが見えた。 必死だった僕らはGMが下の食堂から呼び出されたのに気づかなかった。 この教師然とした居丈高な男は僕がラヴ・ミー、 とやって最後のドゥを慌ただしく切り上げ、 ブルースハープをぷひぃと鳴らしたところで調整室から降りてきた。 「ラヴミーぷひぃ」 はないだろとかれはいった。 同時には歌えないんだよ口はひとつしかないんだから。 もっともな指摘に僕らはしゅんとなった。 ベースのきみ歌いなさいといきなり指名され、 えっおれ? とPは度肝を抜かれて自分を指さした。 経費もかかってるし暇じゃないんだと急かされて、 生まれてはじめてのデビュー作の録音で、 突如として重責を負わされたPは、 なんの練習もさせてもらえずぶっつけ本番で歌わされた。 あいつが助けを求めて視線を合わそうとするのを感じたけれど僕はハープをしくじらぬよう必死だった。 連打するしか能のないピートBのノリがただでさえ馴染んでいなかった。 だからお願いぃ〜っ、 で伴奏が止まりフロアと調整室の視線が集中する。 果敢にもかれは歌った。 声が慄えていた。
窓を隔てたどちら側にとっても拷問のような時間だった。 デッカのときと違って僕らは調整室に呼ばれた。 あのときは相手にもされなかったけれど今度は直接、 叱られるのだ。 僕らは木目の階段を一九段のぼって裁きの場に出頭した。 その狭い水槽には、 お初にお目にかかる巨大な機材のあいだに七名の男が詰め込まれていて、 僕らは居場所を確保するのに苦労した。 向こうもこちらも喫煙したので照明をつけると空気は乳白色に見えた。 テープが巻き戻され再生された。 ぎくしゃくして何をどうしたいのか不明瞭なドラム、 つられてたどたどしくなるギターとベース……。 僕らはフラメンコ靴の縫い目や尖った爪先を見つめた。 ピートBは自分の演奏を上出来と感じたようだ。 求められる技術水準についてGMがうんざりした顔で説教をはじめた。 舞台の単一指向性と違ってここのは双指向性だからどちら側に立ってもいいんだよ……云々。 僕らは相槌を打ったり肯いたりすらできずに無言でうなだれた。 話の意味がさっぱりわからなかったからだ。 ひとくさりご高説を垂れたGMはさすがに気の毒になったか、 どうしたみんな黙りこくって、 何が気に入らないんだと問うた。 僕らは互いに視線を交わし、 もぞもぞと体を揺すったり脚を組み替えたりした。 こんなとき妙な発言をして空気を変えるのはだいたいGかMなのだけれど、 このときこの場にMはいなかった。 そこでわれらがギタリストが、 自分とおなじ名前のプロデューサーをじっと見つめてのたまった——あんたのネクタイ。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)

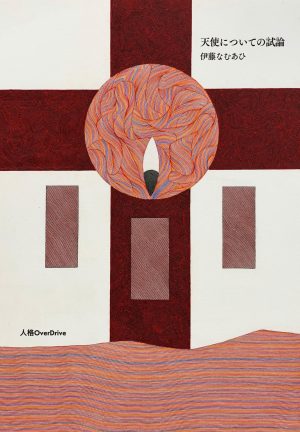








@ezdog ハンブルクからの晴れがましい凱旋。そして上京しての録音……。浮かれた気分が一転、こちらまで気まずくなってくる……。最後のひとことが、それでもメゲてないBのヤツららしいなぁ。この緩急の付け方がとてもいい。
気まずいシーンなのですが……ブルースハープのとこ笑ってしまう。「ラヴ・ミー・ドゥ」は知ってたけど、そんなことがあったとは。史実なのでしょうが描写がよすぎる。