翌日も暗いうちから列車で撮影した。 食堂車でAと昼食をとっていると年長の記者が近づいてきて、 僕の自宅で取材したいといった。 悪いけど家では仕事を忘れたいんだ、 Aだけ来てくれるかな、 Cも喜ぶし、 Mが晩飯をたかりに来ることになってるんだと僕は応えた。 四人での夕食は楽しかった。 女たちは学生みたいにはしゃいで語り合い、 男たちはなかば気圧されながら、 Mが土産に持ってきた葡萄酒を静かに飲んだ。 CとMが食器を洗って棚に片づけるあいだ、 もの問いたげなAに僕は気づかぬふりをした。 上機嫌の赤ん坊を抱き上げてドイツ語で何やら囁きかけるAと、 嬉しそうなCを眺めながら、 黒縁眼鏡の僕はソファでギターの弦を張り替え、 つくりかけの曲を調弦がてらに爪弾いた。 Mはインドの行者よろしく床に胡座をかき、 楽しげに眼を細めて僕の年代物ウィスキーを啜っていた。 ずっとこんな時間がつづけばいいのにと僕は思った。 映画の主題歌に書いたことは決して嘘じゃない。 当時の僕にとって不貞を重ねるのは仕事の捌け口にすぎなかった。 本心では家庭の平穏を求めていた。 狂った世間を締め出して妻子や信頼できる友人といつまでも静かに過ごしたかった。
そろそろお暇するよ、 あすも撮影だろといってMが立ち上がり、 台所でグラスをゆすいで玄関へ向かった。 じゃあわたしもとAがつづいた。 Mは酔いを醒ますかのように冷たい夜風を深呼吸し、 宿泊先まで送るよとAに告げた。 Aは知り合った当初からMが苦手だった。 東洋人を見慣れないせいばかりではない。 何を考えているか得体が知れず、 間の抜けた笑顔が逆にどこか信用ならない感じがしたし、 その正体をSが突き止めようとしていたことも気になった。 Mを追った先の路地で何を見たかSは決して話したがらなかった。 ふたりは無言で歩いた。 沈黙に耐えかねたAはかれがどこに住んでいるか尋ねようとした。 Mはその気配を察して遮るかのように、 今夜はありがとうとだしぬけに礼を口にした。 Jの様子、 なんだかおかしかったろう? ほしかったものをすべて手に入れてみたら思ってたのと違ったんだ。 Sがいてくれたらきっと肚の内を夜通しさらけ出していたろうに。 僕じゃ代わりになれないんだ。 婚約者だったきみが来てくれて、 きっと嬉しかったにちがいないよ……。
その言葉の意味を考えながらフラットへ戻ったAを、 Rと記者が出迎えた。 Gは? と尋ねるとふたりはニヤニヤした。 Gはついに意中のアイドル女優を食事に誘うのに成功したのだ。 やったじゃない! とAは歓声をあげ、 Rと手を打ち合わせた。 上機嫌のRは彼女をダンスに誘い、 でも苦手だから……と遠慮する彼女の手を取って踊りだした。 クラブ通いで鍛えた最新ステップをRは披露した。 両手両脚を大きく動かし、 跳んだり跳ねたり床に手をついたりのけぞったり。 巧みなリードでAも大いに楽しんだ。 年長の記者は絶好の機会とばかりに大喜びでシャッターを切りつづけた。 Mはどういうわけか写真というものに一家言あって、 僕もまた撮られる側からその説に賛同したものだけれど、 あいつがいうには写真とは思いのほか被写体との関係性や、 その場の空気が記録されるもので、 それは撮影者が世界をどう視ているかを表現するものだからだという。 Rと踊る写真は僕も見た。 少なくともこのときのかれは功利心や損得勘定からではなく被写体に夢中になっていたはずだ。 夢見心地のGが帰宅したのは深夜になってからだった。 かれはまだ起きて待っていたAとRに大いに冷やかされた。
高学歴の裕福な階級を読者とする 『星』 誌は、 国際政治や世界経済と同格に僕らを分析しようとした——というか、 売らんかなの体裁をそのように気どった。 ザ・Bとはいかなる現象か、 何が怪物を創り上げたのか? 高名な哲学者を父に持ち、 ロバート・キャパとも親しい年長の記者は、 その企画意図を僕らの地元へ向かう列車内でAに説明した。 この旅にはGも同行したがったが仕事とアイドル女優を優先して断念した。 数年ぶりのリヴァプールは一変していた。 もはや煤煙で煤けた爆撃跡に不良がたむろする寂れた港町ではなかった。 街じゅうに僕らの鬘やTシャツや靴下が売られていた。 懐かしい 「洞窟」 の前には昼興行のために長い行列ができていた。 二匹目の泥鰌を狙うグループが四〇〇は生まれ、 出演予定表にはAの知らぬ名前ばかり並んでいた。 グルーピーなるものが生まれつつあった時代で、 男の子たちは僕らを真似た髪型で革ジャンや襟の小さな背広、 爪先の尖った靴。 女の子たちは濃い化粧で髪を巻いていた。 そうした連中を記者は、 舞台や街の通りといった見栄えのする場所にひっぱり出してポーズを撮らせた。 伝説の一部であるAは地元では有名で、 彼女が頼むと若者たちは快く協力してくれた。
午後にふたりはRの実家へ向かった。 Gから毎日のように思い出話を聞かされていたRは、 仲間に加わるまでの遅れを取り戻そうと、 Aと仲よくなりたがっていた。 映画では主役級の扱いで多忙を極めていたにもかかわらず、 わずか二時間足らずのためにわざわざ帰郷してふたりを両親に引き合わせてくれた。 もっと広くて新しい家を見つけてあげるよとかれは幾度となく提案していたのだけれど、 両親には思い出深い家や昔なじみの隣人たちと離れるつもりは少しもなかった。 深い信頼と愛情でRと結ばれた男が実父ではないことを聞かされてAは感動した。 Gの実家は息子の援助をありがたく受けてウールトンに移っていた。 両親とふたりの兄はAとの再会を喜んだ。 無名時代からザ・Bを応援しつづけていたGの母親は、 あたかも実の娘にするように身を寄せて隣に座り、 ファンからの手紙や手作りの贈り物を大切そうに見せてくれた。 息子が家族全員にプレゼントしてくれたジャマイカ旅行に数日後に発つことを彼女は嬉しそうに教えてくれた。 三月のリヴァプールはまだ寒かった。 やもめ暮らしのPの父親はコーヒーを淹れてブラウンシュガーを足し、 ブッシュミルズを注いで軽くかき混ぜ、 生クリームを浮かべて温かい飲み物をつくってくれた。 かれもまた誇らしげに、 ファンから贈られたパイプや煙草、 手紙の数々を食卓に並べ、 この子たちはみんな息子の署名を期待しているんだよ……と照れ隠しのように笑った。 PやJから聞いて想像していた通りの父親だとAは思った。 かれにとっては男手ひとつでふたりの息子をどうにか育て上げたかと思ったらある日突然、 世界中に十代の娘ができたようなものなのだ。 Jの実家は気難しい伯母さんだと聞いていたので訪ねなかった。 ほかの家族のように快く協力はしてくれまいし、 何よりJが厭がると思ったから。 正解だ。
取材最終日に年長の男性記者は地元紙に広告を出し、 楽器を手にした僕らの後追い連中三五〇名を、 聖ジョージ・ポール広場の階段へ集合させた。 ひとり一ポンドの謝礼は必要経費として編集部に認められた。 そこにはRが抜けて人気の急落したグループの姿もあった。 そんな企画にですら世に認められる好機を期待するほどの、 あるいは一ポンドの稼ぎですら逃すまいとするほどの零落ぶりだった。 撮影のあいだ手持ち無沙汰だったAは子ども版のザ・Bを探し歩いた。 Sが狂ったように問い詰めた煤まみれの子どもたちが、 あのときと同じように自転車のチューブで遊んでいるのを期待したのだ。 子どもの成長は早い。 数年も経っていればすれ違ってもわかるまい。 案の定見つからなかった。
取材を終えて帰国した数日後、 Aは編集部に呼び出された。 一万五千マルクを受け取るつもりで出向いた彼女は刷り上がった版下を見せられた。 大半はAの作品が採用されていて、 新たなキャリアの可能性に彼女は胸を躍らせた。 ところが彼女の手になる巻頭の見開き写真の下には、 年長の男性記者の名のみが記されていた。 彼女の表情は頁を繰るごとに曇った。 Aの名前はどこにもなかった。 案内人としてさえもだ。 踊るRの相手を務めた名もない女としてのみ印刷されていた。 茫然と顔を上げたAに編集長は、 あんた素人の癖に出しゃばりすぎだ、 ザ・Bの私生活を記者にもっと撮らせるべきだった、 そのために雇われたんだからと横柄に応えた。 じゃあJが排便でもしている写真がよかったのと尋ねると、 そうだよくわかってるじゃないかと編集長は肯き、 これじゃ報酬は支払えないといいだした。 だって契約には……とAが反論するとかれは書類を広げ、 聞き分けのない子どもにいい含めるように、 規定の一文を苛立たしげに指先で叩いた。 そこには顕微鏡を要するような字で 「ただし乙の仕事が甲の期待に満たぬ場合は、 甲は乙への支払いを免除されるものとする」 と記されていた。
Aは絶句して年長記者の顔を見た。 最初から騙すつもりだったの? 言葉にされぬその問いに記者は、 恥じるように視線を逸らした。 編集長はなんだまだいるのか、 話はもうとっくに終わったとでもいいたげな顔を向けてきた。 Aはふたりの男を呆れ果てて見つめ、 碌に挨拶もせず憤然と席を立って足早に編集部を出た。 一秒たりともその部屋の空気を呼吸したくなかった。 一九六四年の若いドイツ女は所詮そのような扱いだった。 名高い男たちの髪を切ったとか写真を撮ったとか服を選んだとか、 踊りのパートナーを務めたとかいった逸話の添え物でしかなかった。 僕ら四人はてっきりAが報道写真家としての輝かしい道を歩みはじめたものと思い込んでいた。 夢を餌に釣られて大切な友情を見世物に差し出し、 大仕事をさせられた挙げ句に、 一銭たりとも報酬をもらえず、 現実を思い知らされて写真機を手にすることさえやめてしまったとは知らなかった。 それどころか彼女の成功の手助けをできたことを誇りに思ってさえいた。 結局のところ僕らは戦勝国の成功した男性の側にいて、 Aの境遇など微塵も想像できなかったのだ。 年長の男性写真家はその後 『大地』 や 『メリアン』 といった雑誌で副編集長を務め、 晩年は世界中で作品の展覧会を行って大いに名を高めた。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)
- Mother’s Little Helper(5)
- Flying(1)
- Flying(2)
- Flying(3)
- Flying(4)
- Flying(5)
- Setting Sun(1)
- Setting Sun(2)
- Setting Sun(3)
- Setting Sun(4)
- Setting Sun(5)
- Isn’t It A Pity(1)
- Isn’t It A Pity(2)
- Isn’t It A Pity(3)
- Isn’t It A Pity(4)
- Isn’t It A Pity(5)



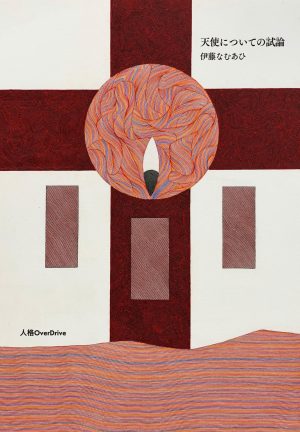






@ezdog Jの家での気心知れた仲間同士の晩餐、リヴァプールでのRやGやPの温かな家族達、取材旅行だったけれどAにはいい時間だっただろう。それなのに手柄を全部横取りされてしまったことが本当に悔しい。昔から狡い奴らほど得をしてのさばるものだよな……。
Jの家からの帰路にAにかけられたMの言葉が優しい。歴史に干渉しすぎるわけにはいかないだろうから、あれがAにしてあげられる精一杯だったんだろう。
Aのことは私まで悔しい気持ちになったのだけど、Rと楽しく踊るAの写真を撮ったときの記者はまだ本当に被写体に魅せられていたのだろうと思うと、少しだけ救われた気持ちになる。その場の楽しくキラキラした空気がしっかり記録されていたのだろうな。撮影者の視点からの心からの表現による写真だっだのだろう。Mの写真についての説、とてもそうだなと思う。