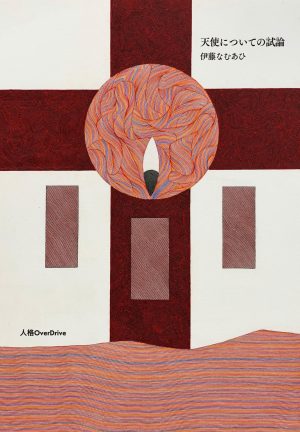歴史上もっとも大金を稼いだロックグループの自負はあるし、 また稼ぎませんかとの誘いを何度も断ってはきたけれど、 僕らだって最初から順風満帆だったわけじゃない。 いつの世の若者もそうであるように、 Mならぬ僕らには先なんて見えなかった。 もし仮にかわいい孫たちが、 当時の僕らみたいなろくでなしにうつつを抜かしていれば、 すでに半世紀は余計に生きた気がするこの老いぼれは、 卒倒してたちまちあの世へ召されるだろう。 八月中旬に夏服で渡独した僕らは、 暖房のない物置の、 打放しの壁や天井から結露がしたたる簡易寝台で、 セータを着込み靴下を穿いて凍えながら眠った。 給仕が武装するような店では演奏はときとして命がけだったし (敗戦国じゃ管理が雑だったのか、 除隊されたからといって素直に銃を国へ返すやつばかりじゃなかったらしい)、 栄養と睡眠を覚醒剤で補う毎日で、 興行主には気に入られるどころか、 前にいたストリップ小屋を大音量で営業停止に追い込んだことや、 舞台での常軌を逸したおふざけ、 客の乱闘を煽るような演奏や態度、 それにビール箱の舞台を踏み抜いたことで睨まれていた。 罰金として出演料の支払いを停められたことさえある。 格上の競合店へ先輩演者を観に行ったのが最後の決め手となった。 誘われて数曲だけ客演させてもらったのがばれたのだ。 実際それは口約束ながら採用試験も兼ねていた。 地下牢めいた店とはまだ契約期間が残っていて、 興行主にしてみれば裏切りに相当したのだろうけれど、 僕らにしてみればあんな奴隷労働に忠義立てする筋合いはない。
一一月末の深夜一時半、 興行主に事務所へ呼び出され、 他店出入り無用の契約に署名しなければ全員の指を折ると脅迫された。 メンバー全員が僕をじっと見た。 普段は口答えばかりするくせにこんな時だけ頼るのだから参ってしまう。 くそったれ、 もう二度とこんな店で演奏してやるもんか、 残りの契約期間なんか知ったこっちゃないと僕は告げた。 へっ、 やるならやってみやがれ、 この指をどうするって? と中指を鼻先に突きつけてやりもした。 PやGも加勢した。 こいつらはいつだって僕がどうするかを見定めてから動くのだ。 穏やかで建設的な話し合いにはならなかった。 喧嘩を好まないSとピートBはずっと困ったような情けない顔をしていた。 さっきの出演料は払わねえからなと興行主は怒鳴った。 その台詞を聞くのはこのときがはじめてじゃなかった。 あんたの汚い金なんて頼まれたって受け取ってやんねえやと僕ら (というか主に僕とPとG) は虚勢を張った。 一九六〇年のハンブルクである年齢以上の男が酒場を何軒か持っていたら戦争でいい目を見たやつに決まっていた。 そんな輩が人間の尊厳をどのように捉えているか、 喧嘩騒ぎで倒れた水夫を二度と起き上がれなくなるまで太い棍棒で滅多打ちにする場面を幾度となく目撃していながら、 このときの僕らはまだあまりよくわかっていなかった。 まして例の丸薬を嚥んでいた。 若さは無敵だ、 それが錯覚であるにしても。 会話は一方的に打ち切られ僕らは事務所から叩き出された。 指は全員無事だった。 当時はただの脅しだと思っていたけれど、 実際には、 残しておけばまだ使えるかもしれないと値踏みされただけのような気がする。 指は僕らの手に残り、 僕らはかれの手に残らなかった。
興行主は雇い入れた八月に僕らの誕生日を外国人警察へ届け出ていたはずなのだけれど、 鼻薬でも効かせていたのか、 それとも単に提出を怠っていたのか、 僕らがゲシュタポと呼んだ警官たちが毎晩二二時に見まわりに来て、 身分証の提示を要求してはスタッカートの利いた叱責で若い客を追い返していたときも、 Gはどうにか検挙を免れていた。 その書類がなぜか急に処理された。 Gは深夜労働ができない一八歳未満であることを理由に帰国させられ、 残りの僕らはリードギタリスト抜きの公演を強いられた。 別れの前日、 僕はかれのパートや旋律の引継を受けた。 あいつとは餓鬼の頃からずいぶんふざけ合ってきたし、 解散後も長いつきあいになるけれど、 今生の別れを意識したのはあのときがはじめてだった。 この歳になるとまたあんな思いをさせられる日も遠くないと覚悟している。 こないだ会議アプリで話したときに聞いたのだけれど、 Gが偏執的なまでに警備や健康診断にこだわり、 喉頭癌を早期発見できたのは、 一九八〇年末にMが僕のためにしてくれたことに加えて、 その頃からたびたびかれが夢に出るようになったからだという。 あの奇妙な日本人の忠告を真に受けず、 どちらかが狂信的なファンに襲われたり末期癌に侵されたりでもしていたら、 と思うとぞっとする。
もとより僕にむりやり引き入れられただけでロックンロールへの情熱もなかったSは、 あの映画館の便所臭い物置からひとりだけアルトナ地区アイムスビュッテラー通り四五番地a号の屋敷に移ったことで気持が離れ、 適性を見極めて画業へ戻ることにした。 残りの僕ら三人にはまだ仕事があったので、 代わりにAがSとともに車で中央駅までGを送り、 大きな袋に詰めたお菓子や林檎を持たせ、 フクファンホラント行き急行列車に乗せてやった。 ギターとアンプと数個の手荷物で潰れそうなGは、 別れ際ふたりにひしと抱きついた。 これは一九六〇年の話で、 いくら未成年とはいえ当時の男は普通そんなことをしなかった。 遠ざかる窓の彼は独りぼっちでなんとも心細そうだったとAに聞いた。 かれは異国の港町で奴隷扱いまでされて稼いだ全財産を、 帰国の旅費ですっかり使い果たすはめになった。 ひと旗揚げてやると大口叩いて家を出たのに、 這々の体で帰り着いたときには文字通り一文無し。 もう何もかもおしまいだとGは思ったそうだ。 ふたたび迎え入れられたとしてもザ・Bはどうせ故郷の港町でくすぶったまま終わる運命なのだと。 八年後にはGの曲を正当に評価していないとMに厳しく批判されることになる僕だけれど、 いかにあの才能溢れる抜け目ない相棒Pとであっても 「おたわけ兄弟」 なんて漫才めいたコンビ名で成功できたかは疑わしい。 残る僕とP、 プラス渡独にあたり急遽加わったピートBの三人では、 憧れの新天地での公演も先行きが怪しかった。
とはいえKとMを朝まで連れまわして宣言したように、 酔客が小用を足す隣で顔や足を洗う生活に僕はもううんざりしていて、 成り上がろうとする意欲は増すばかりだった。 僕らは競合店へ正式に移籍が決まった。 気の毒な本人は知らなかったけれど書類上はGの名も記されていた。 新しい店の最上階には二段寝台のある宿泊室があり、 GとSが抜けて独りで寝ていた僕は、 先輩演者をはじめとする出演者らが鮨詰めで寝泊まりするその部屋へ、 いそいそと荷物をまとめて引っ越した。 PとピートBはひと足遅れてねぐらに荷物を取りに戻った。 ろくな思い出ではないにせよ思い出深い場所といえなくもない。 じめじめした長い廊下に並んで立ち、 暗いな、 うん暗いとふたりはいつもながらの事実をいい合った。 その暗さにもついにお別れとの感傷がそのようにいわせた。 ピートBの荷物にPが避妊具を認めた。 この武者修行の地で売春婦や踊り子のお姐さん方に教わった必需品である。 妙案が閃いたPは明かりをつけようと提案した。 あうんの呼吸でピートBがそのゴム製品をいくつか、 壁から飛び出た釘の頭に刺し、 いしししし、 とふたりで卑しく笑い合ってPがマッチで火をつけた。 僕がそれなりにピートBとうまくやれたのに対して、 最後までぎこちないふたりだったけれど、 それでも寒くて臭くて狭い物置でともに寝起きした仲ではあったのだ。 避妊具はこの地の女の子たちほどには燃え上がらず、 タペストリーの表面をちょっと焦がしたくらいで鎮火した。 荷物をまとめるやふたりは部屋を振り返りもせず立ち去った。
こんなたわいもない悪戯が問題にされるとは、 というか絶好の口実にされるとはふたりとも思いもよらなかった。 僕らはあまりに世間知らずで、 その後も世故に長けた大人たちにさんざん喰い物にされることになる。
僕らは移籍先で初舞台を終えた。 Gがいないにしては上々の出来だった。 むしろG抜きでもこのままこの異国の港町でのし上がっていけるのでは、 とさえ夢見た。 翌朝まずPがレイパーバーン通りで逮捕され、 パトカーでダーフィットバッヘ署に連行されて、 酔っ払いや変質者と一緒に留置場へぶち込まれた。 それから僕とピートBがパクられた (おかげで冗談を落ちまで話せなかった)。 お尋ね者になったことを知ったSはAに付き添ってもらって出頭した。 容疑がボヤ騒ぎだったことはひと晩を豚箱で過ごし、 ドイツ語の供述書に署名し釈放されてから知らされたそうだ。 大抵の悪事では首謀者でありながらこの犯行には関与しない僕も、 早々に鉄格子から出してもらえた。 犯人二名はそうはいかなかった。 一度は釈放されたものの、 数時間後の早朝に二段寝台から引きずり出され、 連邦政府の犯罪捜査官から再尋問された。 英国大使館に電話をさせてくれ、 とPは映画で学んだ台詞をいってみたが受けるどころか冷ややかに無視された。 手錠をかけられて連れて行かれたのは、 かれらが畏れたような強制収容所のガス室ではなく空港だった。 ひと月以内に嘆願書を提出しなければ再入国すら禁じられる。 ふたりはゲートで旅券を押しつけられロンドン行きの飛行機に乗せられた。 往路は船だったので生まれてはじめての空の旅。 まったくもって心浮き立つ体験ではなかった。 Gが泣きべそかいて帰国したまさに九日後の話である。
おなじ無一文でも機材を持ち帰れたGはまだしも幸運だった。 元はずれ部屋コンビは捕らえられたときの着の身着のまま、 楽器から現金に至るまで全財産をレイパーバーン一三六番地に置いてきた。 ロンドン空港からケンジントンの西ロンドン発着所までは無料送迎バス、 そこからは地下鉄に無賃乗車。 ピートBがお袋さんに電話してユーストン駅の郵便局へ電信為替で送金してもらい、 翌早朝にやっとの思いでピートBは西ダービーの、 Pはアラートンの実家へたどり着いた。 のちに小人国の囚われの身となったガリヴァに扮することになるPの弟は、 兄が熱に浮かされたように早口で語る冒険譚に圧倒され、 男手ひとつで男児ふたりを育てあげた父は、 青白く痩せ衰えた長男の姿に動揺した。 幼い頃は肥りすぎを心配するほどだったのに! 独り息子を溺愛するライヴハウス経営者のモナBは、 革ジャンと破れたジーンズ、 ウェスタンブーツのピートBを見てその成長ぶりに感激した (Nをたらし込むほど若く精力的であったとはいえ、 うちの伯母とはだいぶものの感じ方が違うようだ)。 Gの母親は折悪しくカナダの娘夫婦のもとへ出かけていたが、 父親は末息子の帰宅をことのほか喜び、 この経験に懲りて今度こそ堅気になってくれるものと期待した。
さながら童謡のごとく五人のザ・Bはひとり減りふたり減り、 ついに創設者にして中心人物の僕だけになった。 Mによれば僕がいなければ何もはじまらないそうだし、 その評の正しさにも、 PやGに負けない曲づくりの才能にも強烈な自負はあったけれど、 海を隔てた異国の地に僕だけいても実際どうにもならなかった。 タップ一発でなんでも自動生成される現代ならいざ知らず、 打ち込みなんてものが出てきた一九八〇年代でさえ他人に頼んでやってもらっていた僕は、 どんなに強面ぶってみたところで、 苦楽をともにした仲間なしにはなんの役にも立たない。 PとピートBが強制送還されたその日、 僕とSは労働許可証と居住許可証を得るための書類に記入させられた。 Sには画業と現地人の婚約者があるし、 ドイツ語の会話力も少しあるけれど、 学校で仏語を選択した (そして落第した) 僕にはもはやアンプの月賦しかない。 五日後に審査の面談があってSは就労こそ許されなかったがもうしばらくは残れそうだった。 僕はあと四日以内にこの国を出ろと無慈悲に告げられた。 レギュラーの仕事を喪ったので食料を買う金もなく、 Aの母親の厚意にすがるしかなかった。 アイムスビュッテラー通りの屋敷で厄介になって数日を過ごした。 華々しい成功を収められたかもしれない店で、 先輩演者と共演させてもらって小遣いを稼いだりもした。 そこには舞台を踏み抜いたかどで僕らもろとも前の店を馘になったグループの歌手や、 前の店から引き抜かれた用心棒HFもいた。 宿泊所でファンの女と親睦を深めていたら出番になっても現れない僕を探しに現れて、 バケツの水をぶっかけて怒鳴りつけてきたHFだけれど、 このときは大いに同情してくれた。 ハンブルクの荒くれ者はじつに感傷的な連中なのだ。 僕らが有名になりはじめて最後に別れたときなんか、 涙ぐんで不器用に別れを惜しんでくれたほどだ。
一二月七日、 ついに僕は服を売り払って旅費を工面し、 僕ら自身はかっこいいと思っていた金銀のウェスタンブーツを履き、 月賦の残る重いアンプやリッケンバッカーのギターを背負って帰国の途に就いた。 よく舞台で真似をして残酷に嗤いものにしてきたせむし男そのままの格好だった。 Mなら罰が当たったと手厳しく評するだろうと僕は思った。 観客には大受けだったのにかれだけは気分を害したような顔つきをしていたから。 当時はそういうところが鼻持ちならないと感じていたけれど、 いまはもっと耳を傾ければよかったと悔やんでいる。 僕は大事な財産を盗まれまいと神経を尖らせながら、 船といくつもの列車とタクシーを乗り継いで、 八日深夜にどうにかこうにかメンディップスへ帰り着いた。 いうまでもなく伯母は甥を甘やかすつもりなどなく、 呼び鈴やノックや哀れな懇願の声を無視した。 苛立つ運転手を待たせて痺れを切らした僕は、 しまいに寝室の窓へ小石を投げた。 伯母はようやく降りてきて玄関の扉を開けた。 僕は労働者階級の英雄と呼ばれているけれど実際の育ちはそうでもない。 まして上昇志向のある中流階級の伯母はこんなに惨めな人間を生まれてはじめて見たにちがいない。 小言をいうつもりだった彼女は虚を突かれ、 おや、 まあ! とだけいった。 それからタクシー代を払う払わないで揉めた。 あんたの週百ポンドとやらはどこへ行ったんだいと伯母は怒鳴り、 こっちが知りたいと僕は思った。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)