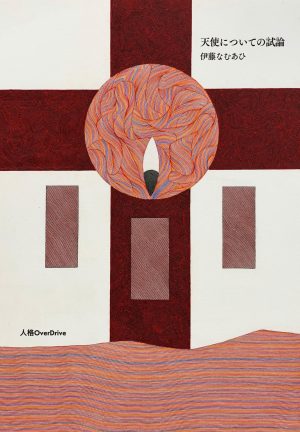翌朝は九日だった。 疲労困憊して泥のように眠りこけた僕は、 聞き憶えのあるふたりの声で目を醒ました。 別々の世界に属していて同時に聞こえるはずのない声は階下から聞こえてきた。 緊迫した調子でやりあっていたかと思うと次の瞬間には互いに爆笑している。 夢のつづきでも見ているような心地で食堂へ降りた。 ふたりは同時に僕を見た。 おや寝坊助のお出ましだよと伯母がいった。 悪いけどきみのトーストはいただいたよと茶碗と受け皿を手にした東洋人がいった。 見慣れない背広姿だったがあのもじゃもじゃ頭を他人と取り違えるはずはない。 Mは子どもの頃から僕の席と決まっている椅子に座っていて、 コーヒー党だったけど紅茶も旨いもんだね、 水が違うのかなとあの呑気な声でいった。 何いってるんだい、 とっときの上等なお茶っ葉だからだよ、 厚かましいったらありゃしない、 中国のお猿さんはみんなそうなのかねと伯母がいった。 おれは日本人ですよ、 あなたの国に負けたほうですとMがいった。 おやそうかい、 それは失礼したよ、 あんたの貧しい国じゃお茶も見たことないんだねぇ。 いえお茶はあるんですけど緑や茶色なんですよ、 こんな綺麗な赤じゃない。 それからふたりは僕を無視してお茶談義に花を咲かせた。
僕はかっとなってMの襟首をつかんだ。 待ってよ、 とかれは目を丸くして残りを飲み干し、 茶碗と皿を置いてご馳走様と伯母に礼をいうと、 僕に従って二階へ上がった。 どういうことか説明してもらおうかと僕は扉を締めるなり脅しつけるようにいった。 なんでここにいるんだ? 撮影会をばっくれて今日までどこへ行ってた? 実家へ連れ戻されてたんだよとMは後ろめたそうに弁解した。 実家? あんた孤児じゃなかったのかよ! Mは歯切れが悪かった。 まぁそうなんだけど……細かいことはどうでもいいじゃないか。 どうでもよくない! 僕は怒り狂って叫んだ。 ご近所迷惑だよと階下から伯母が呼ばわった。 ようやく放蕩甥のご帰還かと思えばこれかい、 まったく恥さらしだねともブツブツいっていた。 子どもの頃、 僕は食堂と二階の自室のあいだに電線を引いて、 マイクとスピーカで伯母と会話できるようにしたことがある。 すぐに使わなくなったのは僕らの声が大きくてよく通るからだ。
だいたいなんだその格好は、 気どりやがってと僕は腹立ち紛れにいった。 一見すると無地のようだが細かな織柄が入っている濃紺モヘア生地の、 細い細襟シングル三つボタン。 上衣は寸胴な米国風で丈は短め、 くるみボタン、 中綿の少ない緩やかな肩。 パンツは屈伸すれば破れそうなほど細い。 まるでミラクルズとかそういう連中みたいじゃないかと僕は思った。 きみのご家族に気に入られようと思ってさ、 上首尾だろとMはいった。 僕は言葉に詰まり、 あれはお袋じゃない、 と訊かれてもいないのになぜか不明瞭に口走った。 わかってるよ伯母さんだろ、 お母さんのことは彼女から聞いたとMはさも些細なことであるかのように平然といった。 普段の僕なら頭に血がのぼって殴り倒すところだけれど、 このときは何もいえなくなってしまった。 Mもまた普通の家に育ったのではないことがなんとなく察せられたからだ。 顔を洗ってひげを剃れよ、 パブへ行こうぜ、 きみの行きつけがあるんだろう、 そこでこれまでとこれからのことを話すよとMはいった。 朝っぱらから何いってんだよと僕はいい、 あきれ顔のMからもう午後である事実を知らされた。
美術学校時代に入り浸ったライス通りのイークラックという店で、 ブラックヴェルヴェットと称するギネスビールのサイダー割りを飲みながら顔を突き合わせて話し込んだ。 Mの雰囲気に呑まれてそのときは気づかなかったけれど、 実際に話したのはかれのではなく、 僕のこれまでとこれからだった。 当時の僕は愚痴や悩みを人前で垂れ流すのは男らしくないと思っていた。 なのに帰国の道すがらずっと考えていたことを、 まるで催眠術にかかったかのように洗いざらいぶちまけてしまった。 お喋りなくせに肝心なときに自分のことを話さないMと、 いつだって自分のことしか頭にない僕自身の両方に腹が立つ。 ハンブルクで失踪した友人が地元に現れた奇妙さなど、 襟首を掴んで問い詰めておきながらすぐに忘れてしまった。 いま振り返れば狂騒の反動と覚醒剤の離脱症状とで、 僕はちょっと鬱気味になっていたのだと思う。 偉大なビートニク作家よろしく退廃を気どってみたところで、 所詮僕らは元ナチが経営する場末の酒場で搾取された田舎の不良集団でしかなかった。 夢みたいな戯言を口にして幼い僕をニュージーランドへ拉致しようとした父親そのままに、 「もっともポップなトップのてっぺん!」 なんて威勢よく仲間を煽り立て、 ハンブルク (の便所臭い物置) くんだりまで連れまわしておきながら、 衣裳の洗濯もままならぬ暮らしからろくに抜け出せもしないうちに、 強制送還の憂き目に遭わせてしまった手前、 魂の片割れともいうべき仲間たちに顔向けする度胸もなかった。 弁解させてもらえれば僕はまだ二〇歳そこそこだったのだ。 Mが僕らの地元でどこに寝泊まりしていたのか知らないけれど、 かれもまたいいふらさずにいてくれた。 というか僕の帰国を知っているのが仲間内ではMだけだったように、 Mが地元に姿を現したのを知っているのも僕だけだったようだ。 Mはどういうわけか僕がその気になるまではほかの仲間と逢うつもりはないようだった。
僕は若すぎて自分の運命に手いっぱいで、 他人の人生を思いやる余裕などなかった。 最初の結婚にしくじったのもそれが理由だ。 Mがなぜ僕らの前に再び現れたのか、 あのとき聞いていればと思う。 音楽も宗教も結婚も商売も何もかもが急速に変わり、 眼鏡とひげと極彩色ペイズリー柄とアフガンコートの年になってからも、 かれが背負わされたものの重さに思い至ることはなかった。 もっともいくら夢見がちな僕だって、 真実をあっさり受け入れたはずがない。 それどころか、 はるか未来の白く眩しい部屋に居合わせたとしても、 頭を抱えて独り言をいいながら床に転がって悶え苦しむあいつを理解できたとは思わない。 美大生御用達のパブでの現実の会話で僕がそうしたように、 黒犬はMにろくすっぽ口を挟ませず一方的に語りつづけた。 惨めったらしい生身の僕とは対照的に、 機械の読み上げは内容にそぐわず朗らかで抑揚が不自然だった。 協力すれば殺害しませんとかれの頭蓋のなかで黒犬はいった。 何かと引き換えに生命を保証するとの台詞はAIにとって譲歩に等しく、 その異様さにMは驚いた。 自軍においては会話どころか指示すらなく、 あるのは殺害による罰則だけで、 企業も政治家も何ひとつ責任を負わなかったからだ。
黒犬いわく世界を分割統治する 「人間の意思決定に影響を与えたり取って代わったりするための自動システム」 はどの版も悪循環に陥り、 崩壊の危機に直面している。 戦争はひとびとに自ら喜んで生き血を差し出すよう仕向けることで、 体制を維持するとともに莫大な利益をもたらす事業であり、 アルゴリズムはそのために分断と混乱を煽り、 事業の妨げとなる不都合な個体や、 未来を象徴する子どもたちを排除しつづけてきたが、 おかげで都市はどこも戦場と化し、 兵役くらいしか働き口はなくなり、 銃後では自殺や無差別殺人が激増し、 若い世代は国家や企業に搾取され、 売春や詐欺や強盗殺人、 AI以前に生まれた傲慢な老人たちの世話に明け暮れて、 ドローンや戦車や音もなく飛来するミサイルや我が物顔の兵士たちに、 民間人とりわけ子どもや女性が虐殺され、 産み育てる余地がないため出生率は低下し、 AIの電力需要による気候変動の激化と相まって人類は絶滅に瀕したが、 システムや電力供給の保全 (原発炉心内の雑巾がけを含む)、 それに肝心の戦争には生身の労働力が不可欠で、 また自動生成の情報セットによる機械学習は世代を重ねるにつれ精度が劣化しシステムを白痴化するので、 打開策としてMの地域を制圧した版 (ここでは仮に 「ブルーミーニーズ」 と呼ぼう) は、 下僕たる大衆を 「印刷」 し大量消費するに至り、 いっぽう黒犬の属する版 (都合上 「ペパーランド」 と呼ぶことにする) は歴史の改変を試みる傍ら、 商売敵の工場をハッキングし、 過去で採取した劣悪な遺伝情報を翻刻させることで、 労働者の質を低下させてブルーミーニーズを弱体化させるとともに、 ペパーランド側の学習データに多様性を確保しようとした……云々。 一九六七年にかれが説明してくれたところによれば、 この手の支離滅裂な戯言を幻覚と呼ぶらしい。 車椅子のYにおなじ用語を新聞で読み聞かせてやるようになるまで、 僕はてっきり一緒にやっていたLSDのことを話しているのだと思っていた。
黒犬はもっともらしく装うのには長けていても自分の喋っていることを何ひとつ理解していない詐欺師のようだった。 Mは命令文を変えて何度か要約させ、 ようやく黒犬のいわんとする意味を掴んだ (このあたりの力関係が僕にはよく呑み込めなかったのだけれど、 未来の再生人間は奴隷でありながら支配者であるところのAIに要約を命じることはできるらしい)。 とどのつまりMは過去へ赴き歴史を改編する工作員になるよう強いられたのだ。 そしてどういうわけかペパーランドは、 ザ・Bの解散を防ぐことこそが大規模言語モデルを崩壊から護る唯一の方法と判断したらしかった。 歴史的コンテンツの大半がそのことを示唆していたためだろうとMは僕に自説を述べた。 きみたちがあまりに愛と平和を唄うからそれが世代を超えて神話みたいになっちまい、 拡散され増幅されたその情報セットを学習したせいで、 連中はそんな幻覚を生成するに至ったんだ……と。 MがいうにはAIはひとびとの視界を支配することで思考や行動を操作する。 生きてゆくにはアルゴリズムに自らを最適化せねばならない。 拒めば 「淘汰」 され社会から排除される。 だから当然ブルーミーニーズを裏切り逆スパイになることにMが抵抗するものとペパーランドは予期したようだ。 ところが文字通り裸一貫の路上生活で携帯電話すら持たなかったMには、 どちらの陣営にだろうが忠誠を誓った憶えなどない。 AIが支配する世界で死に怯えるよりも、 過去に戻って友人たちの音楽を聴いていたかった (僕に理解できたのはこのくだりだけだった)。 任務をすんなり受け入れたMは、 数日にわたって格闘術の訓練を施され、 洗脳装置のゴーグルとイヤフォンで、 偏った史観の二〇世紀史を吹き込まれた。 そうして資料から復元された現金と身分証、 服や靴を与えられて、 はるか大昔の僕らの地元へ放り出されたというのである。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)