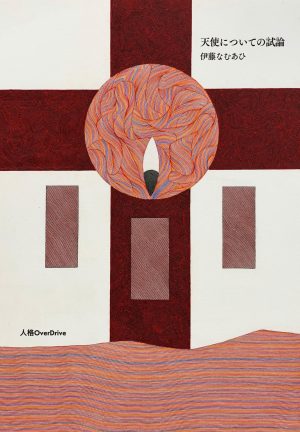日増しに悪化する頭痛や眩暈に苦しみながら、 Sは絵だけは休まず描きつづけ、 六月には返済不要の毎月百マルクの奨学金を得て、 ハンブルク美術大学に編入した。 時を同じくしてザ・Bには先輩歌手の伴奏役として録音する機会が訪れた。 ドイツ人にピーデルズと聞こえるグループ名はビートブラザーズなるださい名前に変えられたものの、 念願の音盤デビューにようやくありつけたのだ。 Sは参加しなかった。 先輩が演奏技術を認めなかったせいもあるけれど、 SはもうPとの乱闘騒ぎで腹をくくっていた。 僕らが 「先生」 と呼んで慕いつつ (Pなんか露骨にゴマを擂るもんで逆にきらわれていた)、 煩わしくも感じていたこの歌手、 先輩といっても僕と同い年で、 ザ・Bはかれに七度和音の押さえ方やマイクの前でどう立つべきかを教わったり、 Bフラットマイナーだ阿呆、 とかドラム速すぎる、 とかどうしてそんなこともできないんだ下手くそと罵られたり、 ときにはかれのほうが僕らのギターにまわってくれたりといった間柄だった。 あんなに威勢がよかったのにいまでは僕らとの録音でしか知られていない。 僕なんて十数年前にかれが亡くなったのすらウィキペディアで最近知った。
ちょうど三ヶ月目の土曜、 七月一日に契約が満了 (さて算数の時間です。 三足す七引く一は幾つでしょう?)。 Sはギブソン・レスポールのアンプをGに譲り、 大きすぎてかさばるヘフナー三三三は二百マルクでKに売った。 Pは最後までSにつらく当たり、 僕とGとピートBはいつも通り見て見ぬふりをしつつも、 おいおい今夜くらいはさ……と内心で思ったものだけれど、 SはSでいよいよ縁が切れるからなのか、 Pに対してあからさまに冷淡にふるまっていた。 ところがいざ舞台に上がると犬猿の仲のこのふたり、 目が合うたびに涙ぐむ。 教え教わる仲にしかわからない事情もいろいろあったのだろう。 Pにしてみれば損な役割を押しつけられたにすぎない。 Sの演奏の拙さはだれかが直してやらねばならなかったのだ。 押しつけられたといえばSだって、 僕の親友ってことのほかは何の関係もない画学生だったのに、 絵が売れた金でむりやりベースを買わされ異国へ拉致された。 三人がかりで寄ってたかって叩いたりひっぱったり踏んづけたりしてみたところで、 画家は最後まで画家でしかなかった。 僕が兵士や弁護士や会計士でないのとおなじだ。
舞台を終えると用心棒のHFとその兄弟たちが酒を奢ってくれた。 過失致死で投獄経験もある、 ハンブルクの無法者の代表格みたいな連中で、 僕らはあいつらが蹴った客の頭蓋骨がばきっと割れる音を聞いたことさえあるけれど、 それでいて妙に情に厚いところがあり、 二度の滞在ですっかり仲よくなっていた (Gだけは怖がって距離を置いていた)。 いつもなら早々に離脱するAもその夜は朝まで一緒にいた。 大量にふるまわれた酒と薬でだれもが泥酔し、 これまでの意地悪や厭がらせの数々について赦しを乞う言葉が、 Sとのあいだに何度も交わされた。 やがてみんな口数が少なくなり、 いつもの日曜のように朝飯を喰って魚市場をさまよい歩いた。 陽射しが強まり、 僕らは店の近所のタール通りで板きれに座った (A以外まっすぐ座っていられなかった)。 こうして酔いを醒ます習慣もきょうが最後か。 船と列車を乗り継ぐ長距離移動を思ってぼんやりしていると、 僕も連れてってくれとKに懇願された。 ベースなら僕だって弾けるよ、 仲間に入れてくれ頼む。 話はわかった、 落ち着けよと僕は宥めた。 そりゃまぁあんたが弾けるのは知ってるよ、 餓鬼の頃からピアノを習ってたんだし、 でもPはもうヘフナーを買っちまったからさ、 悪いな……。 Kはがっくり肩を落とした。 親友のJVは実存主義への憧れが昂じてパリへ行っちまうし、 交際していたAは英国人に奪われ、 人生を変えるほど夢中になったザ・Bはとうとう帰国する。 残るはいまや退屈に思えるグラフィックデザインの仕事だけ。 気の毒だったけれどPのベースは僕とGのギターにしっくりきていて、 いまさらほかの奴の出る幕はなかった。
だいたいこんなときいつも突拍子もないことをいいだす奴なのだけれど、 このときもMはだしぬけに、 安心しなよKといった。 きみがザ・BやJと仕事する機会は今後いくらでもある、 どれも歴史に残る仕事だ、 でもそれはいまじゃない。 僕ら全員がぽかんとしてMを見つめた。 何いってんだこいつ? やがてKが話題を変えようとして、 きみはどうするんだいと尋ねた。 もちろんザ・Bを追うさ、 それが僕の仕事みたいなもんだからねとMは答えた。 船でとも飛行機でともいわなかった。 だれも尋ねなかったのは答えを知るのがなんとなく怖かったからだ。 実際にはかれは僕らとおなじ列車と船を使った (かえってはめ込み合成めいた違和感があった)。 HF三兄弟は僕、 G、 Pを高々と肩車して、 中央駅構内を笑ったり叫んだりして練り歩いた。 Mは手を叩いて囃し立て、 SとAは涙ぐんだ。 本来なら静かな日曜午後のハンブルクで、 見送りの騒ぎは大いに注目を集めた。 そのようにして僕らは修行の地をふたたび離れた。 今度は強制送還なんかではなく、 まっとうに刑期を終えたのだ。
帰国のふた月後くらいだったと思う。 Cがメンディップスに下宿することになった。 母親が数ヶ月カナダへ行くことになり、 それまで暮らしていたホイレイクの家が賃貸に出されたからだ。 僕好みの女になろうと努めつつ、 未来の姑にも気に入られようとする彼女を、 伯母はあばずれと呼んだ。 本人の前でもだ。 僕がした仕打ちとは (Mや長男に指摘されるまでもなく) 較べようもないけれど、 よき妻よき母親であろうとした女の人間性を無視したことと、 思い込みの烈しさにかけて伯母はまさしく僕の原型といえた。
僕の 「仕事」 のことで幾分気まずくなってはいたものの、 「洞窟」 の昼興行と夜興行とのあいだの暇つぶしに、 そしてときにはただそのためだけに、 お茶をご馳走になりながら伯母とお喋りを楽しむのがこの頃のMの日課だった。 先日、 書きかけの原稿について話していたらMに会ったこともない次男 (かれはMの 「前世」 と同い年だ) に思いがけない指摘をされた。 Mは僕の母に似ていたのではないかというのだ。 ばかげていると一笑に付したものの、 こうして記憶を掘り返してみると、 ある意味では確かにどこかそんな側面もあった。 母と伯父の不在で心に穴が空いたのは僕だけじゃなかったのだ。 Mは未来の嫁姑のあいだを取り持とうともしていたようだけれど、 どだい無理な話だった。 メンディップスの食堂にこの三人で座ると、 Mがどれだけ取りなしても、 必ずCが泣きながら飛び出してしまう結果になった。 たちの悪い卑しい女 (学生時代の僕は生まじめな優等生の彼女をさんざんからかったものだったのに!) にたぶらかされて甥がおかしくなったと信じる伯母は、 僕が実際どんな仕事をしているのか、 しかと我が目で確かめてやろうと決意した。 そこへ間の悪いことにMが現れた。 かれは伯母に逃げられぬよう腕をつかまれ、 僕とそっくりな切れ長の目と有無をいわさぬいつもの調子で、 店へ案内するよう命じられた。
伯母の頼みを断れるMではない。 というか、 むしろわざと昼興行に間に合うよう狙って訪れたのだと僕は確信している。 マシュー通り十番の滑りやすい急な階段 (確か一九段あった) を降りきると、 赤いランプがあって狭い通路を左に曲がり、 さらに短い階段を降りたら消毒薬と掘り返した墓と下水の混合のような、 いわくいいがたい臭いの穴蔵がある。 夜には六百人がひしめくその場所には、 便所が個室三つと男子用小便器ひとつきり、 しかも下水管に繋がっておらず地下に垂れ流しで (当時の地下鉄が臭かったのは滲み出た汚物が原因だ)、 そこからの悪臭に地下特有のじめじめした臭い、 詰め込まれた客の汗と体臭、 近所の果物取引所や倉庫からの甘ったるい匂い、 充満する紫煙、 スナックバーの調理台から漂うスープの湯気やホットドッグの匂い、 などなどが幾重にも入り混じり、 強烈な消毒液を毎朝撒いてもどうにもならず、 ひとたび足を踏み入れれば服や髪へ永久に臭いが染みつき、 どこへ行ったか親や上司にバレバレで、 熱気で煉瓦壁や機材はつねに濡れ、 来店するなり客の眼鏡は曇り、 熱演した僕らのシャツなど汗が滝のように絞れるありさま、 なおかつ電圧は不安定で機材がショートしたりヒューズが飛んだりもしばしば、 漏電で出火しなかったのはいま思えば奇跡で、 もしそうなっていたら唯一の出口に客が殺到して阿鼻叫喚、 だれひとり助からなかったろう。 停電時はGやNが裏へまわって不具合を直すあいだ、 僕とPがラジオの長寿番組を茶化したおふざけをやったり、 観客を巻き込んで大合唱したり冗談合戦をやったりした。 これが大受けで、 電気が回復するとえーっと不平の声、 でもその後の烈しい演奏がまた最高潮に盛り上がる。
一九六九年一月末、 会社の屋上で演奏しながら僕とPの脳裏にあったのはこのときの思い出だった。 相棒が何を考えているかくらい互いに口に出さずともわかる。 最前列の子が競い合って手を伸ばす、 ちょっと指を絡めたりしながら受け取った紙を僕が読み上げる……Jに 「お金」 を歌ってほしいな、 顔が真っ赤になるのを見たいから。 いいとも、 僕はいつだってお金のために真っ赤になって働くのさ。 「きみに出逢うまで」 を演ってよ、 この曲を歌うPがすごく素敵だから。 すると僕は聞こえないふりをするPを指しながら観客にいってやる、 すかした顔であっち向いてるけど、 耳をそばだてて一語も逃さず聞いてるからな。 P、 いつものあれをやってよ……ええと、 あれはあれかな、 虹の彼方に? (そうでーす、 と何人かの声があがる) あれはきょうは演りません (えーっ、 と店中の不満の声)。 嘘です演ります (安堵に満ちた爆笑)。 「虹の彼方に」 はPの十八番で、 リクエストがなくたって必ず演ると決まっていた。 どぉーこかぁーあああぁ……でやたら引き延ばした挙げ句に溜めをつくり、 客が不安になったところでニッコリ笑って虹の向こぉーおー、 とやるのだけれど、 その無言の見せ場で僕がおかしな顔 (Mに教わったやつ) をしてみせ、 観客の笑いを誘うのが恒例だった。
常連客には暗黙の序列があって、 前の列に座れる子たちはいつも決まっていた。 たとえばのちにファンクラブ運営を無償で担うことになる一八歳のボビーBは、 中央二列目の席が定位置だった。 全員を見渡せるし、 とりわけPがよく見えるからだ。 Pは彼女によくリクエストを促した。 常連の子たちと交わすそうしたお喋りは、 最後列の客には聞こえなかった。 場ちがいな地獄に紛れ込んだ伯母にも聞こえなかった。 代わりに煉瓦壁に反響するやかましい音が、 頭痛を招くとともに石灰質の粉を彼女の帽子に降らせた。 ひしめく若者たちの頭の向こう、 狭いアーチの舞台に、 チーズ入りロールパンを囓ったり鼻をほじったりガムを噛んだり、 PやGとおふざけを演じたりしながら歌い演奏する僕が見えた。 「ベサメ・ムチョ」 を熱唱するPの背後で不定冠詞のギャグをやり、 Pが眉根を寄せて振り向くと、 知らん顔で演奏に戻ったりした (もちろん事前に打ち合わせた)。
見るからに血圧が上昇中の伯母をMは宥めようと腐心していた——というか、 いかにも家庭内の揉めごとに巻き込まれて困惑するふりをしていたものの、 内心ではおもしろがっていたにちがいない。 たまたま近くの席にいてあいつがほくそ笑む瞬間を見たという客の証言もある。 僕らは 「ホワッド・アイ・セイ」 で観客にふーとかほーとか、 ほにゃとかふにゃとか叫ばせて第一部を締めくくり、 楽屋へ引っ込んだ。 僕らのいちばんのファンであるGの母親が気づいて嬉しそうに手を振り、 声をかけてきた。 あら珍しいこと、 あの子たちとっても素敵でしょう! すると伯母は眉を吊り上げ、 あなたがけしかけるからうちの子は道を踏み外したのよ! と事実といささか異なる暴言を吐くなり、 びっくりする相手を残して僕らを追った。 Mは申し訳なさそうに日本風のお辞儀をしてGの母親に詫び、 掃除道具入れと同サイズの楽屋へ向かった。 伯母は怒りでほとんど泣きそうになりながら僕に吐き棄てているところだった——まぁ結構なことだわ、 ほんとうに結構だこと! そしてMにぶつかりそうになりながら出て行った。 僕がどんな表情をしていたか自分ではわからない。 Mはただ苦笑いして肩をすくめてみせた。
別れてからのこんなたわいない日常のすべてを、 僕は海の向こうのSへ書き送った。 ちょうどいまの僕が、 未来のMやいま世界のどこかにいる 「前世」 のMへ向けてこの本を書いているように。 洗濯屋への苦情でさえ便箋が分厚くなるほど手紙魔の僕だけれど、 この本に取りかかるまであれだけ大量の文章を書き散らしたのは、 あとにも先にもあの時期だけだ。 知人や友人に取材した資料を積み重ね、 スポティファイであの頃の音源を再生して原稿に取り組みながら、 何度もそのことを思い返す。 ひたすらふざけて地口を重ね、 独り言や日記みたいな戯言が、 いつの間にやら詩に変わっていたりする僕。 窘めるような突っ込みや鋭い批評、 そして温かい応援の感想を返してくるS。 あの夭折した天才画家にしてまずいベーシスト、 華奢なそばかすジェームズ・ディーンは、 いわば僕のはじめての読者にして編集者だった。 言葉だけの懐かしい、 ふたりだけのやりとり。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)