ハンブルクのAが週刊誌の連中に手柄を奪われていた頃、 ロンドンでは僕の最初の本が出版された。 地元音楽誌に寄稿した雑文を読んだ編集者が、 こういうのはもっとないかと打診してきた。 熱狂する観客がおぼろになるほど視力を損ねるまで読んできた人間にとって夢のような経験だ。 僕は多忙の隙を縫ってルイス・キャロルやおまぬけ一座になりきり、 イングヴェイ顔負けの高速打鍵で韻文、 散文、 冗談、 駄法螺、 もじり、 模倣、 言葉遊び、 落書きの類いをノリノリで書き散らした。 溜まった原稿の束を編集者はホクホク顔で抱えて持ち去った。 Mには冷やかされたくなくて発売直前まで黙っていた。 Pには序文を書いてもらった。 僕のことを昔からよく知る相棒ならではの心温まる文章だ。 僕としてはちょっとした思い出づくりのつもりだった。 有名になればこんな役得もあるんだな、 くらいに思っていた。 ところがどうせ売るなら半端なことをしてはいけないとBEがいいだし、 テレビやラジオで朗読させられるはめになった。 やけに強気な出版社に、 ちょっと刷りすぎじゃない? と不安にさせられたもののいざ書店に積まれると飛ぶように売れて品切が続出。 その週のうちに二度も増刷された。 『メロディメイカー』 でも 『タイムズ文芸別冊』 でも 『日曜テレグラフ』 でも書評家から絶賛された。 不良とか問題児などと罵倒されて四半世紀近く生きてきて、 先生と呼ばれる連中から褒められたのは生まれて初めてだった。
女優宅の地下室でPと書いた曲が一位を獲得するのとはまた別の嬉しさだった。 豊富な蔵書で僕に読書の悦びを教えた伯母も、 口先ではまたこんなくだらないものを、 恥さらしだねぇ……なんていいつつ誇らしげな笑みを隠さなかったし、 僕が音楽以外のささやかな夢を叶えたことをCも心から喜んでくれた。 でもだれよりも喜んだのはMだった。 まるで自分が書いたかのように得意げにニヤニヤして、 どこへ行くにも持ち歩き、 楽屋や移動中に頁を繰り、 声をあげて笑っては、 書いた当人に向かって聞けよこんなことが書いてある! とでもいいたげに、 気に入った箇所を幾度となく読み上げた。 挿絵がまたいいねぇとも、 日本じゃハナモゲラ語というんだともいった。 だからいったろう、 きみは作家だって! ともいった。 こっちが恥ずかしくなるほど……というか、 通り越してむしろ冷静にさせられるほどの、 常軌を逸した喜びようだった。 犬猿の仲であるはずのPの序文までも絶賛して、 よせよ気色悪いといわれていた。 いつも間の抜けた薄笑いを浮かべたMを、 僕は感情の起伏の穏やかな男だと思っていた。 思い違いだったかもしれないと気づいた。 実のところMは、 僕やBEに負けず劣らずの激情家だったのだ。
チャリングクロスの巨大書店フォイルズが祝賀会を開いてくれることになった。 大変な名誉だと編集者に聞かされてはいたものの、 異業種からの新参者である僕にはことの重大さがさっぱりわかっていなかった。 Mが英国人であったなら大騒ぎしていたにちがいないのだが、 あいにくかれもまたこの国の出版事業における商習慣に疎かった。 業界の筋を通すための野暮用は有名になるにつれて増えていた。 ちょっとしたご馳走の前で文壇や出版界の著名人と、 いかにも文化人らしく気の利いた会話を交わし、 お褒めの言葉をいただく自分たちを僕とCは想像した。 翌日には顔も名前も忘れるようなお偉方にザ・Bとして媚を売る、 そのひとつとしてはまぁ悪くない。 堅苦しい会合の前に景気づけが必要だった。 お祝いしたいとMがいうので僕ら夫婦は息子をCの母に預け、 翌日の撮影は僕抜きでやるよう監督とBEに話をつけて、 友人たちを誘って飲みに出かけた。 お気に入りのナイトクラブでばか騒ぎしたところまでは憶えている。 どうにか粗相もせずに帰宅して寝床まではたどり着いたのだろう、 数時間後にふと目を醒ますとまるで別の惑星にいるかのようだった。 割れんばかりの痛みは頭に鉛でも詰められたかのようで、 重力は十数倍に増加していた。 ううん何時? と隣でCが呻いた。 僕はBEに贈られた目覚まし時計によろよろと手を伸ばし、 どうにかつかみ取って、 二日酔いに霞む近眼に文字盤を近づけた。 数秒の沈思黙考ののち目を剝き、 がばっと飛び起きた。 運転手が迎えに来るまであと一九分しかない! 僕らは大慌てで人前に出られる最低限の身支度をした。 見栄えのする服や靴を選ぶどころじゃない。 目は充血し隈ができて手も慄えていて、 文化人どころか文明人としてさえ認められるか怪しい。 祝賀会とはいえ昼のパーティだから時間はさほど取られまい、 愛想笑いでやり過ごしてさっさと帰宅し、 あとはバタンキュウだなんて自分たちにいい聞かせて家を飛び出した。
ドーチェスターホテルの会場に一歩踏み入るなり、 数百人もの財界人や芸能人に拍手喝采され、 えっえっと戸惑ううちに頼りの妻と引き離され、 主賓席に座らされた。 僕の愛想笑いはこわばった。 蒼ざめていたのは二日酔いのせいばかりではない。 なんだか雲行きが怪しくなってきた……。 さながら自動操縦のごとくお偉方と当たり障りない会話をかわしながらも内容が頭に入らない。 司会者の言葉に耳を疑った。 主賓がスピーチをするという。 当然そのつもりで準備してきている前提の進行だった。 僕は追い詰められた獣のようにほかの主賓を探した。 万雷の拍手と期待のまなざしを一手に浴びた。 大成功した流行音楽家であり、 いまや新進気鋭の作家ともなったJLそのひとを囲み、 だれもが固唾を呑んで静まりかえった。 そいつはきっとだれも思いつきもしないような革新的で創造的な、 すばらしくおもしろい演説をするにちがいないのだ。 報道陣もその歴史的瞬間に備えて機材やペンを構えた。 僕も聴衆の側にいられたらどれだけよかったか。
僕には知るよしもなかったのだけれど、 そこにいたのは地位も名誉もありながら、 僕の話を聞きたい一心で、 なりふり構わず切符の争奪戦を勝ち抜いたひとばかりだった。 この身に降りかかった災いを知るのはCただひとり。 近眼を必死に凝らして見つけると彼女もまた僕とおなじ表情をしていた。 確かに僕は人生の喜怒哀楽を妻と分かち合うと神の前で誓った、 でもこんな恥を味わわせるためじゃない。 男らしいところを見せて安心させてやらねば。 覚悟を決めて勇敢に立ち上がり、 決然と口をひらいた。 この天才に不可能はない……はずなのに興に乗って執筆していたときや、 標的と定めただれかをいびり倒すときのような言葉の奔流は、 二日酔いのどす黒い渦に呑まれてちっとも出てきやしない。 僕は水面に浮上した酸欠の魚のようにもう一度口をひらいた。 喋れ、 喋るんだJL! と自分にいい聞かせた。 そして裏返った声を発した、 あっ……。 数百人の目に戸惑いの色が走った。 あっあっ……ありがとう神のご加護を、 とだけ僕はいって茫然と着席した。 小学校の教室で失禁したときとおなじ気分だった (あのときは笑いすぎて洩らしたのだがこのときは笑えなかった)。 「或人生の一日」 の最後の和音は、 あのとき永遠につづくかに思われた会場の沈黙から着想したといったらきみは信じるかい? 各界の名士の前でそのような破壊力あるふるまいをした僕は、 不遜な反逆児の評判をまたしても高めた。
いささか脱線したけれど、 とにかく僕のいいたいのは、 Mは僕にやたら書かせたがったということだ。 出版社の依頼があろうがなかろうが、 Mに天性の作家だとかなんとかおだてられ、 しつこくそそのかされなければ、 あんな目には遭わなかったしこの本を書いてもいなかった。 かれは数年後にLSDの時代になると、 僕らの解散を防ぐために未来から派遣されたと主張するようになるのだけれど、 その任務と僕の執筆にどんな関係があったやら皆目見当がつかない。 なかった、 といまでは確信している。 「人間の意思決定に影響を与えたり取って代わったりするための自動システム」 とやらに負わされた、 人類の命運を左右する重大な使命とやらには関わりなく、 かれはただ純粋に僕の書くものが好きで、 ただ純粋に読みたかったのだ——おそらくはこの物語を。
Mは軍隊経験のある警護係である以前に、 どこまでも文句をいわずについてくる飲み仲間であり、 僕ら四人のだれかが愚痴を吐きたいときには都合のいい聞き手でもあったけれど、 NやマルEのような付き人でもなければGMのようなプロデューサでも、 ジェフEのような音響技師でもない立場をわきまえていて、 Gの成長を認めさせようと苛立つ最後の二年ほどを除けば、 音楽のことには滅多に首を突っ込んでこなかった。 例外はジェフEを引き入れたときくらいで、 その交代劇にしてもPやGMの思惑を通すためでしかなかった。 実際もしあいつが演奏や作曲に余計な口を挟んできたら、 僕ら四人は全力で辛辣にやり込めていたろう。 それでいて僕らは舞台に立ったりテレビやラジオに出たりするたびにあいつの意見が気になって仕方なかったし、 とりわけ音盤の収録中は一緒にいてほしかった。 Sを喪ったいまでは、 Mは下積み時代からずっと僕らを傍で見つめつづけてきた唯一の男だったからだ。 NやマルEですらハンブルクの地獄は知らなかった。 僕らを取り巻くものが何もかも急速に目まぐるしく変わり、 名声は高まる一方でありながら、 どの公演でも客の声しか聞こえず、 だれひとり音楽にも、 僕らひとりひとりの本当の人間性にも関心がない状況で、 僕らがだれよりも何よりもMの讃辞を必要としていたまさにそのときに、 あいつは舞台の袖に立ちながらも、 明らかに警護のことしか頭にないかに僕らの目には映った。
映画のための新作には自作曲ばかり収録した。 当時そんなことをやるグループはなかった。 それどころかバンドなんて単語さえホークスが改名する頃まで一般的ではなかった。 悔しくて口にこそ出さなかったものの、 僕は初対面のMにいわれたことがずっとひっかかっていたのだ。 Pだって心のどこかには、 ぎゃふんといわせてやる、 との意気込みがあったはずだ。 完成したマスターテープを聴かせてやったときには僕らふたりとも、 どうだ畏れ入ったかと勝ち誇る思いだった。 なのにあいつの反応は薄かった。 うん、 いいね、 気に入ったよ……などと気の抜けた返事。 ふざけるな、 気に入るなんて当たり前だろ、 なぜ 「皇帝壕」 や 「洞窟」 で客席から声援を送ってくれたときみたいに、 われを忘れて熱狂しないんだ。 煮え切らぬ態度に業を煮やし、 襟首をつかんで壁に押しつけ、 がくがくと揺すって問い詰めてやったところ、 歌詞がさ……とあいつは本心を白状した。 十代の恋愛なんておれにはよくわからないんだよ、 きみらだってもう大人だろ、 もっといろんなことを書けるんじゃないかともいいやがった。 それでいて僕らがバラエティ番組に出演して脚本通りのくだらぬ寸劇を演じたり、 数組の芸能人を引き立て役に従えて、 冠特番で 『真夏の夜の夢』 の劇中劇を演じたりしたときにはあいつは大喜びで、 四人とも喜劇役者の才覚があるよとかなんとか太鼓判を押しやがったのには、 映画撮影を前にして自信がつくような情けないような、 どうにも複雑な心境にさせられた。 とりわけ女装した僕のシスビーとPのピラマスが接吻寸前まで顔を近づけ、 客席の女たちから歓喜の悲鳴を浴びた演技なんか、 ああいうのを日本語でBLと呼ぶんだとご満悦で (Yの前でうっかりこの口癖を洩らして馬脚を現すまでもなく、 この頃にはすでに僕ら四人ともがどこか胡散臭いと感じていた)、 おもしろがったPがのちに飼い猫をシスビーと名づけたりした。 確かに音盤を売るためなら何でもやる覚悟だったし、 ラジオの 『おまぬけ劇場』 なんかで育った僕らは、 この手のおふざけを演じるのもやぶさかではなかったけれど、 できればそんなもの抜きで演奏だけを評価してほしかった。 それも口パクなんかじゃなくてだ。 音楽のことなど何ひとつわかりもしないくせに、 雑文集や芝居といった余技ばかり褒めるMを、 ここらでちょっとばかし懲らしめてやる必要があった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)
- Mother’s Little Helper(5)
- Flying(1)
- Flying(2)
- Flying(3)
- Flying(4)
- Flying(5)
- Setting Sun(1)
- Setting Sun(2)
- Setting Sun(3)
- Setting Sun(4)
- Setting Sun(5)
- Isn’t It A Pity(1)
- Isn’t It A Pity(2)
- Isn’t It A Pity(3)
- Isn’t It A Pity(4)
- Isn’t It A Pity(5)









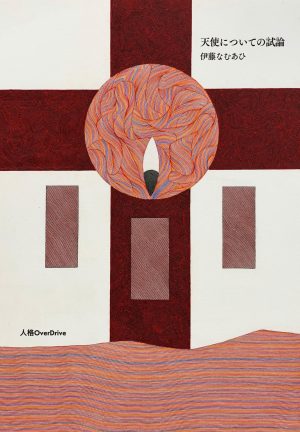
@ezdog 声出して笑ってしまった!二日酔いのJとCのなさけない顔を想像するとお気の毒にと思いつつ面白い。ジョンレノンったら現代のバンドマンと全然かわらない、なさけないところもある普通の青年だったんだなぁ。
本が出たときのMの喜びようがほほえましい。そして映画の音楽があまり気に入らなかった理由もわかる。十代ならいいけど大人にはね……。でもその素直な感想が、Bがもっといい作品を作ろうとする原動力になりそうだな!続きがますます楽しみになった!