録音所を襲撃したテロの狂気は新型感染症のごとく急速に広まった。 異常事態に世間がようやく気づいたのはデビューから一年後の一九六三年十月一三日。 毎週日曜にロンドン・パラディアムから生放送されるATVの長寿番組に出演した夜だ。 運転手付きのオースチン・プリンセスで到着した僕らに群がるファンと、 音が大きく反響する劇場で生じた事態について、 月曜の朝刊はこぞって書き立てた。 ほかにはどこぞで死んだ驢馬の話くらいしかネタがなかったからだ。 いつもの汚いヴァンで事足りるのにBEがわざわざそんな高級車を借りた理由が腑に落ちた。 かれの見栄っぱりもたまには役立つ。 Bマニアなる単語を発明したのは確か 「ミラー日報」 だったと思う。 この話題は当日夜のITVのニュース速報でも取り上げられた。 エリザベス皇太后とマーガレット王女の前で毎年催される演芸会への出演が報じられたあとは、 どの公演も大事件なみに報じられるようになった。 初めての海外ツアーはスウェーデン、 わずか一週間に九回の公演と数々のメディア出演という強行軍だった。 言葉の通じないこの国にも病的な熱狂は波及していて、 ストックホルムではGが危うく舞台から引きずり落とされるところだった。 十月三一日の帰国時には烈しい暴風雨にもかかわらず、 悲鳴を上げる三百人と報道陣百人ほどが空港でひしめいて待ち構えていた。 屋上に群がるファンの金切り声は離着陸の騒音さえも掻き消した。 その全員が僕らの髪型を真似ていた (幸い近視の僕には見えなかった)。 当惑してタラップを降りると盛大にフラッシュが焚かれた。 国は違えどいつも通りロックンロールの演奏で出稼ぎをしてきただけだ。 なのに尻を蹴られて追い出され、 這々の体で帰り着いたあの日が嘘のような、 あたかも英雄が月からご帰還あそばされたかのごときこの歓待ぶりはなんだ? 愛想笑いで手を振りながらも、 うぇ気持悪いと僕らは思った。 毎度恒例の儀式になるとはまさか思いもよらなかった。
一一月四日に王室が主催した演芸会では、 劇場の外で警官隊が鎖のように互いに腕を組んで、 押し寄せる少女たちに突破されまいと決死の努力をすることになった。 王室関係者の到着さえも人目を惹かなかった。 社交界の名士やら王室関係者やら、 高価なドレスや宝飾を身にまとった淑女やらの前で、 ツイスト&シャウトをぶちかまし、 その糞忌々しい宝石をじゃらじゃら鳴らしてみやがれ、 とでも放言してやるつもりだったけれど、 BEがいまにも泣きださんばかりに懇願するので穏当な表現に丸めてやった。 振り (最後の曲になりましたのでご協力を、 お安い席の方は手拍子で……) とオチ (その他の方は……) のあいだに溜めをつくったのは、 受けを狙った効果というよりハラハラして見守るBEをからかうためだ。 僕らにしてみればいつもの辛辣な悪ふざけにすぎなかったけれど、 初めてこの手の冗談に接した連中にとってみれば、 思いがけぬ方向から愉快な玩具が飛び出してきたようなものだったろう。 女王陛下にもお気に召していただけたようだ。 このあとどこに出演なさるのと訊かれてスラウですと応えたら、 あらうちの近所ねと陛下は微笑んで仰せになった。 なるほどウィンザー城は近所だなと僕らは笑い合ったものだ。
翌日にはBマニア現象を時事問題として扱う番組に出演し、 その先はもうだれにも止められぬ狂騒の幕開けとなった。 クリスマス公演の入場券十万枚はわずか二五日間で売り切れた。 三四会場をまわる予定の秋公演の前売りがはじまると、 全英各地で数千人が寒空のもと徹夜で行列し、 連日のように一面で大々的に報じられた。 二枚目のアルバムは予約だけでも二七万枚、 一週間で五〇万枚を売り上げた。 八月に出たEPは二五万枚、 その頃から売れつづけて百万枚を突破したシングルは、 一二月第一週に五枚目のシングルが出るとようやく第一位の座を譲った。 その頃Pはお嬢様女優の邸宅に間借りしていたのだけれど、 そこの地下倉庫で僕とあいつがサシで向き合って書いた 「抱きしめたい」 は、 予約開始の翌日時点で五〇万枚も売れ、 しまいには百万枚も注文されたので発売後にはさすがに売れ行きが鈍るだろうと思っていたら、 クリスマス商戦を通じて六週ものあいだ一位を保った。 僕らの髪型を真似たがために放校になった生徒や、 僕らを引き合いに出して人気取りする牧師や政治家、 ロンドン公演の警備費が国会で問題にされたとかいったくだらない話題が、 連日のように紙面を賑わせた。 この騒ぎは北米でも徐々に報道されはじめた。
思うにあれはナチスの党大会やMAGAの暴動のような集団ヒステリーの類いだった。 教師然としたGMでさえ、 夫婦で僕らの公演を客席から見たら正気を喪って、 周囲の少女たちと一緒に立ち上がり目を見ひらいて全力で叫んでいたというから、 その感染力は半端ではない。 全世界へ蔓延したその騒動についてMは、 イエスの墓から遺骸が消えたのもこんなことだったんだろうね、 などと冒涜的な冗談を吐いた。 あるいはそれは信心深さの裏返しだったかもしれない。 他人事だったら笑えたろうが僕らには深刻な問題で、 表へ出るには念入りに変装せねばならなくなり、 住まいは四六時中監視され、 楽屋からは服や楽器が盗まれ、 ついには僕らや家族を誘拐しようと企む輩まで現れた。 ジェリベイビーズが好きだとGが冗談を洩らしたが運の尽き、 赤ちゃん型ゼリー菓子が雨あられどころか機銃掃射のごとく舞台へ降りそそぎ、 演奏は妨げられ怪我まで負いかねない惨状となった (ストックホルムの件にせよドラマー交代劇で殴られた件にせよ、 当時Gはいつもそんな貧乏くじを引いてばかりいた)。 秋の巡業ではMの差配のもと、 のちに映画で再現されるように、 付けひげやら眼鏡やらの変装や偽名を用いて、 さながら特命を受けた諜報部隊のごとく、 こそこそと物陰に身を隠して街から街へと移動し、 建築現場の鉄骨をよじ登って会場の屋根に渡り、 天井裏から舞台袖へ降りたり、 秘密の地下通路を使って劇場からテレビ局へ移動したりさせられた。 またまたお得意の誇張かよと思われそうだが本当の話だ。 不安定な足場でいかに体重を分散させ筋肉を使うかを、 僕らはMから軍隊式のスパルタで教わった。 おかげでそれまでだれに助言されても、 観客なんて見えなくて結構だと痩せ我慢していたのに、 とうとうコンタクトレンズに頼らざるを得なくなった。
Mにあれこれ指図されなければ、 絶叫する群衆に何をされるかわからない……という極限状況は、 僕ら四人とあいつとのあいだに緊張を生んでもおかしくなかった。 ひとは生殺与奪の力を握る相手を憎むものだし、 Mのやったことは、 それまでただ悪ふざけをする仲間にすぎなかったのが、 GMやBEといった 「教師側」 の人間としてふるまいだしたようなものだからだ。 ところが会場から会場への命がけの移動は、 それが危険であればあるほどふざけた大冒険に思えて、 僕ら四人は悲鳴を上げたりぶーぶー不平を垂れたりしながらも、 実はそれほど苦にならなかった。 やっとのことで劇場へたどり着いても今度は楽屋に缶詰で、 舞台じゃ客は絶叫するばかり。 演奏なんてだれも聴いちゃくれず、 むしろそのほうがしんどくて、 プロ意識の強いGなんかいつもぼやいていた。 十代向けの幼稚な愛の唄なんぞ歌う代わりに、 腐れ×××! なんて罵倒してやったところで、 客は目を剝いて叫びつづけるのだからめちゃくちゃだ。 年末にやった握手会では、 会場の経営者が設備を破壊されるのを畏れて、 僕らのまわりに金網を張り巡らしたほど。 三千人の熱狂的な客は頬や手や全身を金網に押しつけて叫んでいた。 舞台袖でその様子を見た僕は、 あいつら漫画みたいにフライドポテトになって出てきちまうぞと笑い、 Mは日本じゃトコロテンというんだ、 格子から海藻ゼリーをにゅるっと押し出して、 ソースをかけて辛子を添えて喰うのさと教えてくれた。 僕は響きがおもしろくて客めがけて何度もその日本語を叫んでやった。 トコロテン! きゃーっ!
興行主やBE、 それにMがやたらファンを畏れるのを、 僕ら四人は大げさだと笑っていたけれど、 いま振り返れば少しも被害妄想とは思われない。 ロックンロールを生んだ国の大統領が、 二枚目のアルバムが発売されたまさにその日にダラスで受けたような歓待を、 次は僕ら四人が受けたとしても不思議ではなかったのだ。 Pは世間で何が起きているか知るために、 だれかが楽屋で読み棄てた新聞でも平気で読む。 僕ら四人が米国の人種差別に異議を申し立てたのは、 仲間内に日本人がいたせいもさることながら、 主にPの意見にひっぱられてのことだ。 よそで他人がどう扱われようが無関心だった三人も、 リトル・リチャードやチャック・ベリーに相応の敬意が払われないとPに聞かされ、 そんなのおかしいと憤った (黒人街まるごと虐殺しておきながら何もなかったことにした国だからなぁ、 ジム・クロウ法や敵性外国人法なんてのもいまだにあるし……とMは感想を述べ、 四〇年前にオクラホマ州で起きたことや二〇年前の強制収容について話してくれた)。 Gは映画撮影で知り合ったアイドルとの恋に夢中で、 新聞なんか読む暇はなかったし、 小学校すらまともに通えなかったRは漫画くらいしか読まない。 僕はといえば届いたばかりの朝刊を伯父の膝で読み聞かせられて育ったせいか、 マルEに買ってこさせたばかりのパリッとした新聞を、 いつも楽屋で舐めるように読んでいた。 かといって社会にはPほど関心がない。 知らない世界への空想をかき立てられるのが好きなだけだ (Mは僕がどの記事に関心を抱いたかをいい当てる遊びを好んだ。 当たることもあれば外れることもあった)。 いつか自分もおなじ目に遭うかも……なんて白昼夢に耽りはしたけれど、 現実の問題とは捉えなかったし、 まして僕らの運命に大きく影響するなんて思いもしなかった。
そうした騒ぎのすべてから僕はCを締め出し、 思い出深い 「洞窟」 での最終公演にすら立ち会わせなかった。 妻子の存在は昔からの地元ファンにこそ知られていたものの、 世間には依然として秘密にされていた。 僕の妻かと問われるたびにCは懸命に否定して、 こそこそと乳母車を押して立ち去らねばならなかった。 初対面からBEを侮って反抗的だったPは、 お嬢様女優といるところを撮られても平然としていたけれど、 波に乗っている商売が台なしになったら仲間三人にどう顔向けすれば……と思うと、 僕にはいいつけを無視する度胸がなかった。 おかげでCはいまでいうワンオペのシンママのごとき暮らしを強いられた。 しかも体調が悪いとか二階に追いやられたとか被害者ぶって四六時中、 不平をこぼす強烈な姑と同居だ。 ひっきりなしに泣く長男をCはおくるみに包んで乳母車に寝かせ、 庭のいちばん遠いところに停めて、 声が二階へ届かぬことをひたすら祈るしかない。 僕は秒刻みに詰め込まれた予定を縫って、 なるべく頻繁に帰るようにはしていたものの、 狂騒から隔てられた安らぎの場を求めたところで、 家庭内の空気は張り詰めている。 何しろ僕の育ての親、 伯母のこだわりの強さは生まれつきだ。 何をいっても無駄なのは子どもの頃から身に染みていた。 僕は日々疲れきっていて妻子がされている仕打ちに見て見ぬふりをした。 成功すればするほどCと僕を結びつけていたはずの、 この騒ぎが過ぎ去ればともに穏やかに暮らせる、 と信じる気持が薄れ、 せっかく手に入れた家庭が指のあいだから砂のようにすり抜けていくのを感じた。 ロンドン・パラディアムに二度目の生出演をしたとき、 やたら押しの強い年増歌手と知り合ったのもその頃だ。 翌年までつづいた関係にCは気づかぬふりをした。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)






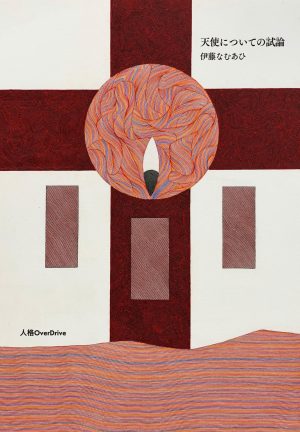



@ezdog 本人達の意思とは関係なく時代の熱狂に巻き込まれていくB。音楽なんて誰もろくに聴いていないキャーキャー言っているだけの騒ぎが虚しい。
トコロテンのところは実に皮肉が効いている。Mの活躍は愉快なのだけれど。大切なはずの家庭もうまくいかないJの虚しさが伝わってくる。