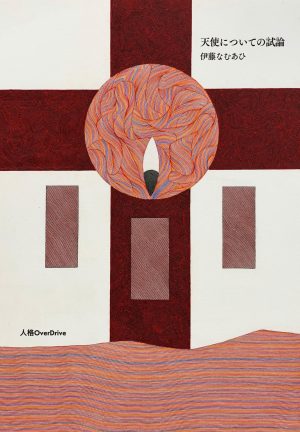まったく奇妙な体験だった。 僕、 P、 Gの三人ともが本来の人生とは異なる時間を生きはじめた気分になったのだ。 このことは何度も話し合って意見が一致している。 あるいはそれまでにも無数の小さな歯車が機能していたのだろうし、 その後もこれが分岐点だったと思える出逢いはいっぱいあったけれど、 ハンブルクの友人たちの存在は別格だった。 独創的な髪型や衣裳。 ファンを大切にし楽しませること。 半身が闇に溶け込む写真やKの不条理イラスト、 録音技術を駆使した前衛的な音づくりといったロックと芸術の融合……。 世界が僕らをザ・Bとして記憶するすべてがその夜からはじまったのだ。 Kとはいまに至る長いつきあいになるし、 Mとも一九七〇年に喧嘩別れするまでずっと僕らと一緒にいて、 読んだばかりの本を薦め合ったり支離滅裂な言葉遊びを交わしたりする仲になった。 運命は翌晩さらに明確になった。 ドイツ美男のKが自分とよく似た身なりの美男美女を連れてきたのだ。 まんなかの女が見るからに気が進まぬ様子だったのを憶えている。 世の女たるもの従順で色っぽい銀幕のブリジット・バルドーみたいでなければならぬと決め込んでいて、 やがて最初の妻となる恋人にもそうあるよう強要していた僕は、 自己主張の烈しそうな、 短い髪に中性的な服装の女にびっくりした。 若い頃の僕のそんなところを一九六〇年代にはMに、 一九七〇年代にはトッド・ラングレンに説教されたものだけれど、 そんな気配を察したのか、 いかにもアーリア人風に整った女の顔にあらわれた恐怖と嫌悪は、 懸命にマックシャウする僕を見るなり、 もう耐えられない、 とばかり露骨になった (のちに本人がそう述懐していたから被害妄想ではない)。 このときのAと僕はまさしく水と油で、 やがてSを巡って争って同時にかれを喪い、 しまいには親友になって、 二〇二〇年に彼女が亡くなるまで連絡を取り合う仲となった。 男女のあいだにそんな友情が成立するなんて、 第二次大戦後のマチズモに汚染された僕には思いもよらなかった。
Aは甘やかされて育った女王のような傲慢さと、 女性解放運動以前の女に特有の気後れとを併せ持つ女だった。 破局寸前だった恋人のあまりのしつこさに根負けしたのに加えて、 かれがならず者の巣窟みたいな歓楽街に出入りするばかりか、 怪しげな東洋人と親交を結んだようなことまでいいだしたので心配にもなり、 美大時代からの友人にして同僚のゲイについてきてもらうことにしたのだ。 最近孫に聞いたところによれば日本の若い女の子は韓国のアイドルグループの公演でメンバーの顔写真を貼りつけた団扇を振ったり 「誰某愛してる」 と書かれたプラカードを掲げたりするそうだけれど、 そういうことを世界で最初にはじめたのがこのJVだ。 親世代がやらかした悪行の数々 (敗戦がなければかれ自身、 両親の密告でガス室へ送られていたかもしれない) にほとほと厭気がさしていたかれは、 フランス実存主義に憧れて何度も渡仏し、 パリ最先端のファッションで身を固めていた。 のちに僕らを模した鬘が世界中の子どもたちにばか売れするようになるけれど、 あの髪型を考案したのがほかならぬかれで、 ジョージ・オーウェルのSF小説の年に僕らとおなじ会社名でパーソナル・コンピュータを売り出した男が好んだ黒ハイネックも、 元はといえばかれがパリの蚤の市で仕入れてきた流行なのであって、 この夜に訪れた美男美女三人は、 揃いも揃ってその格好をしていた。 まさに掃き溜めに鶴。 がさつな店にそこだけスポットライトが当たったかのようだった。 演奏しながら僕らはKに片目を瞑ってみせたり、 いい女連れてんじゃんと口笛を吹いたり、 笑わそうと変な顔をしてやったりした。 これがザ・Bさ、 と得意げにKが友人たちに説明するのが見えて僕らは誇らしかった。 最前列に陣どって待っていたMの席にかれらは加わり、 ずっと前からの友人のように挨拶し合って、 やがて休憩時間になった僕らも仲間入りした。
この夜を境にかれらが連れて来るようになった大勢の仲間を、 僕らはジツゾンと呼んだ。 からかい半分、 憧れ半分のこの綽名のニュアンスをおわかりいただけるだろうか。 実際に実存主義にかぶれていたのはJVくらいで、 あとは政治にも哲学にもデモにも討論にもだれひとりなんら関心がなかった。 油脂で固めた頭に革ジャン、 ジーンズ、 潰れた鼻のならず者たちが、 僕らの大音響に負けじと大声で話したり、 喧嘩したり踊ったりビールをその場で戻したりする、 熱気で結露した酸欠の店に、 型破りな服装とドライヤーでブローした清潔な髪の、 いかにも芸術家然とした美男美女がお出ましになったら……そうらジツゾン一派がやってきたぞ、 となるわけだ。 犯罪と肉体労働しか生計手段を知らないロッカーや水夫や湾岸労働者と、 似たような環境に育って音楽にしか適性のない僕ら (画業で成功しつつあったのはSだけで、 僕もPもGも故郷ではどの職もすぐに馘になった) にとって、 知的で洗練されたかれらは眩しく見えた。 ジツゾンはジツゾンで僕らに綽名をつけた。 Gは 「いけめん帆耳」、 Pは 「セクシー坊や」、 そして僕は 「親分」 だ。 「のんびり忍者」 とか 「冴えない三船」 とか呼ばれたMをジツゾン一派に含めるか否かは迷うところだ。 日によっていうことが違うかれは、 田舎の三流大学を出たとも路上の孤児だったともいっていて、 どちらかといえば後者が真実に近そうな気がした。 この頃は夜行性の路上生活をしていたのは確かで、 にもかかわらず飲み代に不自由していなかったのはすでに述べた通りだ。 やがてAやJVに服装や髪型を見立ててもらったのに、 路上暮らしの薄汚い不良みたいな品性は隠せなかった。 むしろ僕らとお揃いの格好だったSのほうがずっとジツゾンっぽく見えた。
やがて客層の変化に気づいたのか、 前の店で僕らと寝る機会を競い合っていた女学生たちもこの店に集まりだした。 短いフレヤスカートを硬いペチコートで膨らまして跳ぶ女の子、 ゴムみたいに柔らかく開脚して受け止める男の子。 救命艇席にひしめいて酒を奢り合い、 背中を叩き合って大笑いするロッカーとジツゾン。 我が物顔にふるまう英国人の水夫たちや、 女を連れてきては恫喝したり殴ったりほかの客に絡んで揉めごとを起こしたりするポン引きは、 用心棒HFや武装した給仕たちにすぐさま叩き出された。 夜通し働く僕らの最後の客は清掃係だ。 学生客のほとんどは週末の一五時から楽しんで早い時間で引き上げたけれど、 平日にまで現れたり、 二二時に追い出されるまで粘ったりする追っかけもいた。 あの子たちは金をどうしていたのだろう。 この頃には僕らは交代で演奏するグループと打ち解けていて、 とりわけドラマーのRとはよくつるんだ。 休憩時間に僕らにリクエストしてくれるこの小柄な男はみんなに好かれていて、 とりわけGは技術と人柄に一目置いているようだった (メッシュなんか入れてて最初はいけ好かないやつだと思ったんだけどね、 とGは照れ隠しに弁解した)。 こいつがうちのドラマーだったらなぁとPやGとよく話したけれど (うっかりKの前で洩らしたこともある。 かれは口外しないでくれた)、 仕事仲間のグループから引き抜くわけにもいかないし、 波長が合わないとはいえ渡独の直前に仲間に入れたピートBがいるので叶わぬ夢想だった。
Rといえば、 あれは確かジツゾン一派と知り合う前の週だったと思う。 のちにその四人で世界を股にかけた大冒険を繰り広げることになるとも知らず、 ハウフトバーンホーフ駅前の小さな録音所に仲間たちと押しかけ、 B面に広告が入る七八回転のアセテート盤に、 ガーシュインの 「サマータイム」 を吹き込んだことがある。 Rがいたグループのベーシストが歌手気どりで提案し、 僕らはかれらのギタリスト二名とともに伴奏を提供してやったのだ。 家族や恋人や友人にメッセージを吹き込むのが本来の使い途で、 いまでもチョコレートの個包装に孫の写真を印刷するような、 似たような商売がある。 その二年前に故郷でも似たような自主録音を経験していたけれど、 大勢でやったこのときは楽しかったな。 ベースはふたりも要らないんでSは見学した。 Rのグループ連中はあと二曲吹き込んだはずだ。 僕らの自作曲も録りたかったけれど、 二〇時の開演に遅れるのを畏れたマネージャに止められた。 高い金を払って九枚 (そう、 この数字だ) もプレスしたのに惜しくも紛失してしまった。
つらいけれど愉快な日々だった。 出逢いから十日も経たぬうちにAがKと別れてSとくっついたのに全員が気づいた。 空爆の経験から善良なドイツ人は死人だけと決めつけていたSの母親にとってはおもしろくないことだったろうけれど、 あっぱれなことにKは英独カップルをさながら兄のごとく祝福しているようだった。 学生時代、 些細なことで最初の妻を疑って暴力をふるったことさえある僕には死ぬまで理解できない感情だ。 むしろ嫉妬に狂ったのは僕ら三人のほうだった。 知的で洗練されたプロの写真家で、 コンバーチブルの国民車ビートルまで持っている歳上のドイツ女に、 一蓮托生でやってきた不良仲間を奪われたのだ。 みそっかすのSはいまや別世界へ行ってしまい、 大人の恋愛を楽しんでいる。 僕らだけがゴミ溜めみたいな暮らしに取り残され、 英国海員組合でありつく故郷の朝食と新聞や図書室とをわずかな楽しみに、 ならず者相手に便座を頚にかけてマックシャウしている。 Sにベースの補習をしてやっては憶えの悪さに苛ついていたPなんか、 ジツゾンの扱いが王子様のS、 辛辣で威張っている 「親分」、 最年少で愛され上手の 「いけめん帆耳」、 無口でモテるピートBに次ぐ最下位であることに、 憤懣やるかたない様子だった。 Yと並ぶ生涯最高の相棒にこの言い草もなんだけれど、 この頃のあいつが少々つきあいにくくなっていたのは否めない。
魂の片割れのようにも思えたSをドイツ女に奪われ、 僕の手綱を握るはずのPがどうにも偏屈になるのと反比例して、 僕とK、 Mとの距離は日増しに近づいた。 その土曜の僕が何に腹を立てていたのかはもう思いだせない。 とにかく猛烈に不機嫌で、 舞台を終えて足音も高くふたりのテーブル席へ近づいた。 ほかのメンバーは雲行きを察して救命艇席へ逃げ、 Kはやばいときに捕まっちまったなという顔をした。 Mは何も感じていないふうで、 レモンを垂らしてグラスの縁に塩を塗ったシュナップスを啜っていた。 その頃のかれはいつもそんな酒を好み、 僕はといえばコークハイで、 Kはたぶんビールだったと思う。 僕がかれらの席にどっかと座って給仕に三杯頼み、 豆ッコを三つテーブルへ叩きつけるなり、 Mはろくに見もしないでそのうちひとつをひょいと口に入れた。 もうひとつは僕の口へ消えた。 Kは見るからに怖じ気づいていたが、 ええいままよとばかりに最後のひとつを呑み込んだ。 僕はコークハイを立てつづけに干し (豆ッコは喉が渇くのだ)、 最後のグラスを叩きつけるように置いて、 もうこんな暮らしはうんざりだ! と叫んだ。 Kは僕が奢ってやったグラスを握りしめ、 ぎょっとして身をすくめた。 Mはわかっているのかいないのか、 あたかも英語を解せぬ日本人が適当に調子を合わせるかのように肯いて酒を啜った。
それから英独日の三国同盟はしばらく黙って、 僕の差し出すダイエット薬をそれこそ豆みたいにアテにして飲み物を煽った。 Mがどうしていたかはともかく、 少なくとも夜ごと僕らに朝までつきあうKは、 僕ら同様いつも数時間しか寝ていなかったはずで、 それをこの丸薬が可能ならしむることになる。 覚醒剤というものが概してそうであるように、 この可愛らしい豆粒には口渇や依存性のほか、 苛立ちや怒りを増幅する副作用があった。 そして世の若者がいつの時代も概してそうであるように、 僕らには先行きの見通しがまるでなかった。 あるいはMにはあったのかもしれないけれど、 自分が何者であるかを理解したのはずっとあとのことで、 この時点では記憶喪失さながらに未来どころか過去すらなかったはずだ。 僕ら三人は朝まで飲んだくれ、 店を出て肩を組んでよろめき歩いた。 明け方の空気は凍ったウォッカのように冷たく澄んでいてネオンが眩しかった。 ストリップ小屋になだれ込んで全員しこたま殴られ、 襟首掴んで放り出された。 Kがいうにはそのとき僕は、 来いよ空飛ぶ円盤野郎ども、 もっと愉快な場所へ行こうぜと叫んだのだそうだ。 もしかしたら潜在意識下でMの正体を察していたのかもしれない。 立ち飲み屋で隣の客がグラスに小便するのを見た僕らはたまらず便所に駆け込み、 ひとつの便器に三つの頭を突き出してゲーゲー吐いた。 店を出る頃には茜色の朝日が射していた。 ハンブルク警察とホルステン醸造所を通りすぎた。 日曜の市場は賑わっていた。 盗んではみたけれど喰う気が失せて投げ棄てた僕のバナナは、 魚屋のトラックの屋根に落ちた。 水兵や酔っ払い、 外套を着込んだ家族連れ、 リンゴ箱に脚を突っ込む野良犬、 赤い手で魚を抱えた肥った女……。
石畳の階段に冬の朝日を浴びて並んで座り、 眼を閉じて喧騒を聴いた。 それは一九六〇年のハンブルクにしかない音楽だった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)