伯父の膝で新聞を読み聞かせられて育った僕は、 他人の不幸話を読むのが好きだった。 犯罪や事故で大切なひとを亡くした人間は、 翌朝どうやっていつもの職場に出勤するんだろうとよく空想したものだ。 自分がその立場になってみると無知がいかに残酷な暴力であるかを実感する。 どうやって乗り越えたかって? そんなことできるものか。 縫い合わせた疵をかさぶたが覆い、 醜く盛り上がった痕になって、 でも奪われた臓器は二度と戻りはしない。 それでもひとたび幕の上がった舞台は最後まで演じなければ。 三度目のハンブルク公演初日は一三日の金曜日だった。 ドイツ人のユーモア感覚はどうも理解しがたい。 スター倶楽部を経営する風俗王は僕らの音楽を愛していて、 自分みたいにだれもが僕らを好きになると信じていたから、 記念すべき開店日をどうしてもザ・Bの演奏で飾りたかった。 僕らとしても金をもらうからには仕事はきちんとやり遂げるつもりだった。 泣きはらした目で狂ったように練習に打ち込むGを見たら、 僕もPもピートBも今夜くらいは……なんて糞みたいな弱音は吐けなかった。 自分の死を口実にサボるなんてことは何よりSが許さなかったろう。 だから濃紺の背広に丸襟シャツ、 細い黒ネクタイ、 細いパンツにフラメンコ練習靴で決めた僕らは、 ひとの心がないと誹られようがなんだろうが、 水着女とフィルムをあしらった 「官能映画館」 なるネオン脇に店名と星印、 それに 「ロックの祝賀行進一九六二」 なる看板を掲げたその店で、 安っぽいビニールの黄色い幕がひらくなり、 いつものように足を踏み鳴らして四つ数え、 痛烈なロックンロールをおっぱじめたのだ——それぞれの負い目に取り憑いた亡霊を追い払うために。
その数分前 (いや、 ここは九分前ということにしておこうか)、 僕は楽屋で出番を待ちながらこいつは仕事だ、 仕事なんだと自分にいい聞かせていた。 「もっともポップなトップのてっぺん」 を見せてやると約束し、 便所裏の掃除用具入れやら犯罪者が跋扈する地下牢やらを経て、 いまだ全国音盤デビューの夢こそ叶わぬまでも、 絶叫を浴びつつ集客の目玉を務めるまでにのし上がり、 三度目の正直でここまで連れてきた仲間たちの前で、 デッカのときみたいな弱気な顔は見せられなかった。 まさしく通夜そのものといった空気に耐えられなくなり、 ちょいと失敬と断って、 互いに視線すら交わさず俯いたり壁の一点を見つめたりしている三人から離れた。 全身黒のMが便所の前で腕組みし壁にもたれて立っていた。 春だというのに襟にボアのついた革ジャンとセーター、 コーデュロイの細いパンツにウェスタンブーツ。 縮れ毛の頭は後ろへ撫でつけた髪型に戻っている。 生きたSに二度と会えないなんて僕らが思いもしなかった五日前、 海を隔てて五三五マイルも離れたモナBの店で、 Gの病欠を心配したりPの熱演に歓声をあげたり僕の冗談に腹を抱えたりしていたあいつが、 当然のような顔でそこにいることにいまさら驚かなかった。 切迫していた僕は横目で一瞥すらせずに、 よおと声をかけただけで通りすぎようとした。 Mは疲れたようにニヤッと笑うと、 意外な力で僕の肩を掴んで、 あの間抜け面を近づけてきた。 近ぇよ、 といつもなら殴ってやるところだけれど見つめ返すことしかできなかった。 僕の近眼にはあいつがなんだか二〇歳は老けて見えた。 Mはあいつらしくないしわがれた声で、 こいつで元気をつけろよと耳元に囁き、 僕の手に何かの粒を握らせてきた。 なんだ気色悪いな、 と僕はあいつに眉をひそめながら身を引き剥がし、 便所へ入った。 別の手で逸物を引っ張り出しながら掌をひらいてみると黒い錠剤だった。 大量のビールによる内圧を解放しながらそいつを口へひょいと放り込んだ。 消し炭みたいな味がした。 濡れた手をパンツにこすりつけながら便所を出ると (Yに叱られるまで僕は小用で手を洗ったことがなかった) あいつは姿を消していた。
そのあとに起きたことは誇張抜きでまるで憶えていない。 Kは最前列でSのいない広すぎる舞台を挑むように睨み、 いまのこの状況でおれとあんたら自身を楽しませてくれるのか、 さあ見せてもらおうかと待ち構えていた。 最新モッズスーツで登場した四人はかれの絶望を軽々と裏切った。 かれがいうには僕は陽気な獣のようにロックし、 ロックし、 ロックして、 哀しみに呑まれまいと懸命に演奏していた仲間を、 雪だるま式に増大する心意気に感染させ、 煽り立てて、 ドイツ人が初めて出逢う音の塊で聴衆を圧倒したという。 NEMSの餌箱で新たに仕入れた豊富なネタ元、 豊かな旋律を奏でるPのベース……これまでの渡独とは較べ物にならぬほど技術は向上し、 かつてKを夢中にさせた荒削りな感覚、 刃物のように暗くヒリつく破壊衝動は、 温かく包容する強い光に取って代わられていた。 満員の観客は地獄の底が沸き返るかのように熱狂した。 後戻りのきかぬ変化に気づいたのはKただひとりだった。 かれは動揺した。 帰国中あいつらに何があった、 何がザ・Bをこんな風にしちまったんだ?
テッズもモッズもご存じない商業デザイナーのKは、 意匠としての黒革上下に退廃的な異国情緒を見ていた。 かれにしてみれば背広や丸襟や細いネクタイなんてのは、 歳のいったお母様方にきゃーカワユイと頭ナデナデされようとする軟弱な媚でしかなかった。 僕はかれの前では金のために魂を売ったかのような強面な態度を装わねばならなかった。 しかし違うんだKよ、 英国じゃあれはあれで正統な不良の制服なんだ、 襟んとこに別珍の喪章が縫いつけてあるだろ、 あれは反抗心の象徴でさ……。 空港で逢った品のいい背広の男をKは思いだした。 握手のときJが手紙で暴露した指向を裏づけるかのように顔を赤らめたあいつが? それともSの死か……。 黒い錠剤のことをかれは知らなかった。 知っていたら上辺の装いには騙されなかったろう。 一九七〇年に終わりを迎えるまで、 そしてそのあとも僕らは愛と平和を歌いつづけ、 その音楽が世界へ広まるほどに、 まるで裏腹な暴力が僕らを蝕むことになる。 脅迫され音盤は焼かれ、 飛行機は撃墜されかけ、 暴徒は押し寄せ、 諜報機関に盗聴され尾行され……そして最後にはMがああなった。 そのすべてのはじまりがSであり黒い錠剤だったといまならわかる。
三度目のハンブルクで酒と薬が僕の正気を保たせたのはその夜に限ったことではないけれど、 Gにいわせればその夜もそのあとも、 僕はさっぱり正気なんかではなかったそうだ。 ある夜など終演後にくたくたに疲れたみんなが寝床につくなり、 目を剝き泡を吹いた僕が奇声をあげて乱入してきて、 Pと寝ていた女の子の服を鋏で細切れにしたあげく、 恐怖に慄くその子の鼻先で、 枕へ力任せに突き刺したという。 別の夜には疲れたBEが数杯で潰れて居眠りをはじめたところ、 その襟首に僕がいきなりビールをどぼどぼと注いで、 飛び起きて激怒したあいつを凄まじい勢いで罵倒したとか何とか……これはHFの証言だ。 ザ・Bが退場して次のグループの出番になるや、 僕は頼まれもせぬのに掃除婦の扮装で、 バケツとモップを手に再登場した (たぶん気の毒な中年女を死ぬほど怖がらせて強奪したのだろう)。 僕は例によって身障者の物真似をしながら、 畏れ慄く地元グループや、 困惑する観客をものともせず舞台をうろついて床や機材を磨きはじめ、 あまつさえ歌手を磨きベーシストの靴を磨き、 叩かれそうになるのを左右へひょいひょいとかわしながらドラムを磨いた。 改築したばかりで資材置き場のようになった舞台裏へようやく引っ込んだかと思えば、 安堵の間もなく再登場。 今度は工事現場みたいな作業着姿で、 ばかみたいに長い板を担いでいる。 あたかも自分が邪魔になっているのに気づかぬ風を装い、 がに股でひょこひょこ舞台を横断し、 歌手に咎められて振り向くや、 板の両端でマイクをなぎ倒しベーシストをのけぞらせ、 その結果にわざとらしく驚いてみせてまたもや板ごと振り向く。 演者は楽器や機材を護ろうとして打ち倒されたり、 舞台上を右へ左へ逃げ惑って、 配線に足を絡めて転んだりと大騒ぎ。 元ベーシストの死どころか、 そんな人間がいたことすら知らない観客は大爆笑だった。
Kによればかの有名な便座事件もこのときだという。 便器から剥ぎ取ったU字型のそいつをハワイの観光客用の花輪みたいに頚にかけ、 下着一丁で何喰わぬ顔で演奏したらしい。 HFにいわせればこれは別の夜で、 開演時刻になっても現れない僕を宿泊所へ迎えに来たら、 女とくんずほぐれつの真っ最中、 ひっぱがそうとしても互いにしがみつきどうにもならず、 バケツで水をぶっかけたところ (逸物をひっぱり出して小便を……とあいつは吹聴し、 ピーデルに尿とかこれ見よがしの便座とかがおもしろいんで信じたやつも多いけれど、 いくらなんでも話を盛りすぎだ)、 ずぶ濡れで舞台へ上がった僕がその格好だったという。 ……いや、 それともあいつがいってたのは別の夜のことかな。 便座を頚にかけるなんて毎日やってた気もする。 いずれにせよこの頃の僕が狂っていたのはまちがいない。 とどまるところを知らぬ奇行の数々は、 幸福や笑顔なんてものが地上から消失したかに感じていたKの腹をよじらせ、 思ってもみなかった別の涙を流させると同時に、 その背筋をどこまでも暗く凍らせた。 黒革時代の僕らは強面を装いながらも陽気だった、 それがどこか裏返ってしまったのだ。 ハラハラしながら二階席から見守っていた風俗王は、 舞台が収拾のつかぬ大混乱に陥るのを見てとって幕を引かせた。 観客の視線から隔てられても僕はまだ騒ぎまくっていた。 あれぞ舞台芸人の性だよな……とKはのちに僕に語った。 その闇の深さに自分がザ・Bに加われなかった理由を悟ったとまでいわれ、 おいおい大げさだよと怖くなっていい返したけれど、 そこまでいわれると当時の自分がどれほど危うい瀬戸際にいたか思わずにいられない。
とはいえKの記憶も混乱していて鵜呑みにはできない。 ドタバタ喜劇さながらの寸劇は捏造とはいわぬまでも誇張がすぎる。 二千人を収容できる元映画館はその夜上々の客入りだったはずなのに、 その逸話を語るのはいまだKただひとりだからだ。 あいつの隣でいつものように腹を抱えて朗らかに大笑いするMを、 僕は舞台から確かに見た。 なぜかわざわざいつもの背広に着替え、 もじゃもじゃの髪を再び下ろしていたのを鮮明に憶えている。 何もかも忘れようとするかのように顔を歪めて笑うKとは対照的で、 あれはまちがいなく新規開店の夜だった。 なのにKはあの夜Mがハンブルクにいた事実などなかったといい張るのだ。 そればかりかPやGまでもが一九六二年春の滞在中、 あのおかしな日本人は一度も姿を現さなかったと口を揃える。 大昔のことだからね、 別の夜と混同してもおかしくないよとKに慰められて僕は大いに不満だった。 あいつのほうが歳上なのに惚け老人扱いされちゃたまらない。 この頃のMの逸話はだれに聞いても違っていて、 経験を共有するはずのひとびとからまるで異なる歴史が語られ、 だれもが別の平行宇宙を生きたかに思わされる。 そして奇妙なことに僕自身、 あの便所前での邂逅を別にすれば、 あの春のハンブルクでMを再び目撃した記憶はないのだ。 たった一錠飲んだきりの効き目は強烈で、 しばらくそのことしか考えられなくなったのだから、 夢や幻なんかであろうはずはないのに。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)









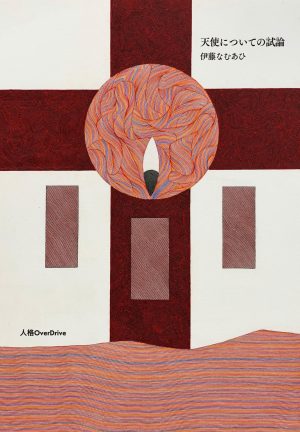
親友の死の悲しみになんとかのまれまいとするJやBの面々の気持ちが痛いほど分かる。出番の前の重い空気が伝わってくる。……というところで久々のMの登場!あの杜作品の数々で騒ぎを巻き起こしてきた「黒い錠剤」も登場!Jの奇行には呆れてしまうけれど、あの黒い錠剤のせいなら致し方ないかと思えてしまう。物語にいよいよ未来からの策略が絡んでくる予感!この後半の流れがとてもいい。杜作品のこういう余韻とか空気の作り方が好きなんだよなぁ。