Pとあいつの誕生日の二週間ほど前、 朝から米国の 『土曜夕報』 誌の撮影があった。 お気に入りの短篇がいくつも掲載された雑誌だというんでMは前から楽しみにしていた。 僕らは古めかしい山高帽なんか被らされ、 喪服みたいな背広の胸にハンカチを覗かせて、 太いネクタイに内羽根の靴、 手袋といった英国紳士の扮装をさせられ、 傘まで持たされて滑稽な写真をいくつも撮られた。 そのうちひとつは僕らが背中と腹をぴったりくっつけてムカデのごとく列をなして闊歩する図で、 マッドネスの振付を二〇年は先取りしていた。 普段は表情を消してまわりに気を配るMが、 このときはハンブルク時代に戻ったかのように腹を抱えて笑っていた。 写真家や助手があんたうるさいよ撮影の邪魔だと苦情をいいつつ、 つられて笑い出すほどだった。 膝をもっと上げてくれよとか錦蛇がどうとか口走るもんで、 またお得意の日本語か? といってやるとMは急に真顔になって慌てたように、 いやこれは英語だ、 忘れてくれなんていいやがる。 こっちが元ネタだよなとも呟いていたのは確かな記憶なのに、 六年後のお笑い番組にびっくりして電話に手を伸ばしたものの、 三人の仲間とは一時的に疎遠となっていたし、 肝心のMは姿を消していて連絡先もわからなかったのでだれにも確かめようがなかった。
記憶といえばこのあとに起きたことほど納得いかず、 わが正気を信頼できなくなる話もない。 ちょっと調べればわかることだけれど、 どの本にもどの記事にもどの記録映像にも、 出てくるのはMの代わりに知らぬ男の顔と名前ばかり。 ともにあの時期を過ごしただれに尋ねてもそれが事実で正しい歴史だという。 PもGもRもはじめは僕がふざけているのだと思い、 次に一九八〇年の事件がもとで頭がおかしくなったのではと心配し、 しまいには気味悪がってその話題を避けるようになった。 惚けたと家族に思われるのが癪でいまでは自分でも口にしなくなった。 一九七四年の夏にベランダでUFOを見た話のほうが証人もいてまだしも耳を貸してもらえる。 〇〇七シリーズのとある一作の結末やC3POの配色には世界中のだれもが記憶違いをしているというけれど、 この僕の実体験ってやつはいまだだれとも共有できない。
英国紳士に扮した僕らにMが笑い転げるのとは対照的に、 Rは撮影中ずっと不機嫌そうにむっつりしていた。 話を振られてもだんまりでお得意の奇妙な冗談も出てこない。 どうしたと尋ねると喉に手を当ててドドがイダいと別人のような声で訴えた。 大丈夫か、 イヤ大丈夫ジャダイってんで額に手を当ててやると高熱だ。 哀しげな眼はどんよりと潤んでいる。 おいおい、 こないだのGとおんなじ流れかよと僕は思った。 BEが大慌てでゾディアックにRを乗せ、 大学病院へ連れて行った。 医師の診断では一週間は退院できないという。 前にも書いたけど、 どうもこの頃の僕らは疲労で免疫が弱っていたらしく、 代わるがわる流感で倒れていた。 病院から戻ったBEはデモ音源を録っていた僕らにそのことを報せて弱りきったように溜息をついた。 翌日から世界公演へ発つ予定だったからだ。 Rのドラムは僕らの音楽のいわば心臓、 そいつが入院じゃどうにもならない。 どうすんだおまえのせいだぞと僕はMを罵った。 おれが? なんでよとあいつは目を丸くした。 おれらが必死こいて働いてるってのに指さしてゲラゲラ笑ってたからだと僕は理不尽にいい募った。 罰としておまえ代わりに叩け。 はぁ? 付き人ふたりもGMも僕が何をいいだしたのか計りかねる顔をした。 PとGだけは僕の意図に勘づいたようで悪ふざけに乗ってきた。 あいつをとっちめたかったのは連中もおなじだったのだ。 Rのラディックなら慣れてんだろ、 お手のもんだよな? おれらの音楽を子ども向け呼ばわりするからには当然それなりに叩けるんだろ? 三人でニヤニヤ笑ってMを取り囲み、 顔を近づけて口々に煽り立てた。 子ども向けなんてひと言も……。 いいや、 いったね。 いったいった、 おれらは忘れてないよ。 さあ叩いてみろって、 お手並み拝見といこうや。 僕らはあいつを奥のドラムセットまで追い詰め、 座らせて枹を握らせた。
僕らが困惑させられたのはここからだ。 ハンブルクからずっと一緒にいてレパートリーを熟知しているMは実際そこそこ叩けたのだ。 なんだ全然だめじゃんかと三人で指さして嗤って、 身の程を思い知らせてやるつもりだったのが当てが外れた。 どんな言語でも数分ほど話しかけられると片言ながら返事ができるようになる特技をあいつは持っていたけれど、 これもそのひとつのようだった (日本のことわざに門前の小僧というのがあってね……とあいつは説明した)。 かといって音がまるで聞こえぬ状況で僕らの背中だけを頼りに当意即妙に叩けるほどでもない。 即座に椅子から引きずり降ろすにも、 僕らの看板を負わせて世界中の舞台に立たせるにも中途半端だった。 視線を合わせまいとするPを僕はじっと見つめてやった。 あいつは溜息をつき、 またこの役回りかよ、 といってMに稽古をつけはじめた。 僕とGも小一時間ほど練習に協力してやった。 僕らの酔狂に珍しく黙って付き合っていたGMが苛立ちはじめた。 不安げに成り行きを見守っていたBEが、 口出しを僕に咎められるのを覚悟の上で、 もう時間がないから代役を探そうと提案した。 例によって僕はかれを睨みつけてやりながらも、 内心では渡りに船と喜んだ。 ただの悪ふざけのはずがその頃には引っ込みがつかなくなっていたからだ。 するとMが急に立ち上がって僕らに告げた、 五分ほど待っていてくれ。 どこへ行くんだ? とGが尋ねた。 十字路と応えてMは厚い扉から出て行った。 泥臭いデルタブルースよりモータウンの女声コーラスが好みだった僕にはその冗談がわからなかったけれど、 Gはその不吉な元ネタを知っているようで、 笑ったものかどうか戸惑うような、 気味悪がるような表情をしていた。
数分後に戻ってきたMは出て行く前よりもどこか少し老けて見えた。 ちょっと歳下だったのが僕に追いついたかのような。 じゃ、 もっかいおさらいだってんで四人で音を合わせた。 どの曲も完璧だった。 まるで別人だ。 そう指摘してやったらあいつはそうだよと肯いた。 十字路というのがどれだけ遠いか知らないけれど、 Mの叩き方はRにそっくりでありながら何かが致命的に異なった。 まるで少し前Mに読まされたジャック・フィニイの莢人間だ。 生身の人間ならだれにもあるはずの一貫した癖のようなものが感じられない……というか、 フランケンシュタインの怪物よろしく継ぎ接ぎにして、 もっともらしく装って騙そうとするかのようだった。 その不自然さにPは気づかぬようだった。 わずかな時間で素人を、 世界の舞台に立たせられるまでに仕上げた手柄で鼻高々だった。 ヘフナーを弾きながら例のチャーミングな笑顔をMに寄せて何かいい、 話しかけられたほうも苦笑しつつ叩きながら何か返事をしていた。 僕はGと視線が合った。 おなじ考えのようだった。 R不在の急場はしのげる、 でもこれは音楽じゃない……。
きみらの死から数十年後には、 とMは数年後のある晩に語ったことがある。 きみらの音源を学習した機械がきみらをそっくり真似た 「新作」 を出すだろう。 生身の人生で積み重ねた実感のようなものはそこにはない。 でも客は違いになんて頓着しない。 その頃には大衆は、 資本家と結託した政治家に調教されて、 人間性なんてものは社会の生産性を損ねるとしか見なくなっている。 それが世間の求めるきみらだ。 そうなりたくなければいつまでも健康に生きつづけることだねとMはいった。 このときのMの演奏はそんな 「街が盗まれる」 未来を先取りしたかに思えた。 問い質したことはないけれど、 いまではGも似たようなことを考えているのではないか。
僕ら四人は意見を求めてGMを見た。 かれは渋い顔でまぁいいだろうと肯いた。 BEはまだ渋っていた。 保守的な海外では東洋人が受け入れられるはずがないというのだ。 そりゃそうだと思いつつ、 つむじ曲がりの僕はBEを困らせたいとか、 弱みを当てこすりたいとかいった衝動をこらえきれず、 化粧でどうにかなるだろと口走った。 われながらばかなことをいったもんだ。 Mを代役にする珍妙な案はそれで一笑に付されて流れるものと思ったのに、 何を考えたかGが真顔で、 怪奇映画の特殊メイク係を呼ぼうといいだした。 BEは大慌てで手配に走った。 おなじ手間と金でセッションドラマーでも呼ぶべきだったのに! いまさら冗談だったとはいいだせない空気になった。 僕はGをまじまじと見つめた。 正気か? 声には出さなかったが伝わったようであいつは肩をすくめた。
急遽呼ばれた職人はラテックスでRを模した付け鼻を作成した。 まるでミンストレル劇そのものの醜悪さだ。 普段は意識しないがこうして見るとMはやはり骨格のつくりが僕らとは違う。 のちに僕が人前でも眼鏡をかけるようになるとあいつに羨ましがられたものだ。 顔が平坦なので白人用の眼鏡はずり落ちてしまうのだという。 欠陥遺伝子の修正とかいう話はどこ行ったんだよとも思うけれど、 直してあの程度のご面相だったのかもしれない。 もじゃもじゃ頭には直毛の鬘が被せられた。 いいだしっぺのくせに僕はこらえきれずに爆笑した。 腹を抱えて指さし涙を流し、 こんなんでごまかされる客はおかしいだろといった。 いけるって、 どうせだれもドラマーなんて見てやしないとP。 あいつら叫んで失神したいだけだからなとG。 頭越しに僕らが喧々諤々の議論を繰り広げるあいだ、 当人はずっと不本意極まりないといった風の仏頂面だった。
コペンハーゲンの客はパリと同様、 野太い声援が目立った。 そして取り澄ましたフランス人よりも情熱的だった。 恒例となった空港のお出迎えは六千人。 交通を麻痺させた一万人は地元警察と、 独特の制帽を被り燧石式マスケット銃を携えて視察に訪れていた英国陸軍のフュージリア連隊によって、 どうにか暴動に至らず抑え込まれた。 急ごしらえの新編成で僕らは演奏曲のおさらいをした。 Rの持ち歌を外すために入れ替えられた曲順を、 マルEがそれぞれの楽器に貼りつけてくれた。 英国大使の訪問を受けたあと四四〇〇人がぎっしりの会場で二度の公演をこなした。 付け鼻にヘルメットみたいな鬘のMは、 警備係とRの贋物の二役を務めた。 しかしどちらかといえば演奏のほうに気が行って本業がおろそかになっていた面は否めない。 緊張で蒼ざめたあいつはフォイルズの昼食会での僕に似ていなくもなかったので、 僕としてはしてやったりの気分だった。 技術的にはピートBより遥かにマシで、 四六時中ひっついて飲み歩いた仲だけあって息も合ったけれど、 やはりどこか薄気味の悪い演奏だった。 遅ればせながらPもその違和感に気づいたようで、 寂しいから早く復帰してくれとRに切実な電報を打っていた。 僕らが去ったあとの舞台で終演が告げられると観客は怒り狂って騒然となった。 ロビーにあった鉢植えが司会者に投げつけられて砕け、 紫の花と土が舞台へ飛び散った。
アムステルダムでは伝統衣裳の娘たちから花束と帽子を贈られ、 記者会見がひらかれた。 舞い上がったMは何度も余計なことを口走ろうとし、 僕ら三人は襤褸を出させまいと必死で取り繕った。 付け鼻がずれて外れそうになる一幕まであった。 その後ヒルレーゴムまで二六マイル移動してトレスロング喫茶食堂でVARAテレビの収録を口パクで行った。 踊る客たちが一曲演るごとにじりじりと迫るのに不安を憶えていたら、 ついに終演間際に雄叫びをあげて乱入してきた。 マルEは殺到する野郎どもを舞台から降ろそうと奮闘したけれど、 いつもの客層とはわけが違う。 どうせ聞こえるのはRの録音なのに、 Mは演奏をトチるまいと必死で何も指示を出せなかった。 Nが悲鳴のようにだめだこりゃ、 逃げろ! と叫んだ。 僕らはプラグを抜き、 大切な楽器を抱きしめて命からがら逃げ出した。 鬘と付け鼻で一心に叩きつづけるMが舞台に残された。 その姿は暴徒に呑まれて見えなくなった。 僕らのいない舞台に音盤だけが騒ぎなど知らぬげに鳴りつづけた。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)
- Mother’s Little Helper(5)
- Flying(1)
- Flying(2)
- Flying(3)
- Flying(4)
- Flying(5)
- Setting Sun(1)
- Setting Sun(2)
- Setting Sun(3)
- Setting Sun(4)
- Setting Sun(5)
- Isn’t It A Pity(1)
- Isn’t It A Pity(2)
- Isn’t It A Pity(3)
- Isn’t It A Pity(4)
- Isn’t It A Pity(5)





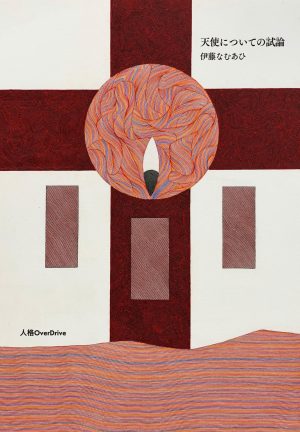




@ezdog Mが大活躍だ!Pに稽古をつけられるM、変装させられるM、面白い!……んだけど、Mの完璧な演奏が象徴する未来にうすら寒いものを感じる。叩き続けながら群衆の波に埋もれていくMの残像、彼の伝えたかった警告が胸に残る。
Bの英国紳士の扮装とか、舞台に散った紫の花と土とか、映像が目に浮かぶ。美しいなぁ。杜昌彦氏のいいところはたくさんあるのだけれど、この描写の綺麗さ、余韻の残し方は特に素晴らしい。