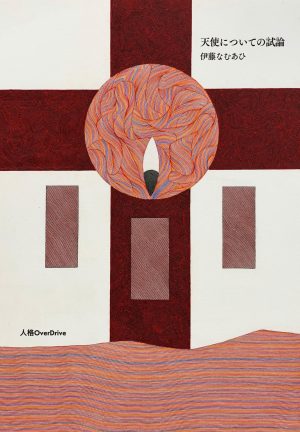同級生から母のことを持ち出されて、 死んだよとだけ告げたように、 なんにも知らない脳天気な連中にSがどうしているか問われて、 脳出血で死んだよ、 とだけ答えた僕の脳裏には、 かけがえのない親友の頭を力任せにこっぴどく殴りつけた場面や (僕だって殴り返されたのだが)、 将来を嘱望された若手画家には縁もゆかりもないはずの、 ストリップ小屋での興行に異国の港町まで連れまわしたり、 そこでできた恋人と引き離したりしておきながら、 連れの女に色目を使ったと誤解した連中に、 レイソム講堂の便所でかれが袋叩きにされたとき、 独りにしてしまったことなんかが巡っていた。 遅ればせながら騒ぎに気づいて割って入り、 僕が右の中指をへし折られ、 Gが全身に打撲を負い、 ピートBが目のまわりに青痣をつくるなどして助け出したものの (未来の軍隊で格闘技の訓練を受けたとのちに明かすMは、 こんなときにかぎって数日姿を見せず、 Nは通信講座の学習のため一時帰宅中、 君子危うきに近寄らずのPは遠巻きに眺めていた)、 ドイツ人婚約者のこともあいまって、 Sの母親が僕らを憎むのは無理からぬことだった。 そしてその頃からSは胸焼けや頭痛を訴えるようになり、 愛息を悪い友だちに永遠に奪われるのでは、 とのかれの母親の不安は的中してしまう。 体調がすぐれないことは知っていたし、 手紙の文面にキリストを自称するなど奇妙な傾向は認めていたものの (そんなら僕は洗礼者ヨハネだな、 と初対面のMの言葉を思いだしながら返信してやった)、 上り調子の若い僕らに死は遠く感じられ、 脱退した仲間を気にかける余裕はなかった。
AによればSは失踪した東洋人のことを案ずると同時に疑ってもいて、 僕に報せずに正体を突き止めようとしていたらしい。 親交を深めた女たちをもう用は済んだとばかり厄介払いし、 朝までふざけて飲み騒いだ僕らが、 豆ッコの昂奮をなだめすかして惰眠をむさぼるあいだに、 アイムスビュッテラー通りの屋敷で暮らしはじめたSはずっとひとりでMを探していたという。 Sはそういうやつだった、 僕やKほどにはMと親しくなかったはずなのに。 そしてそのことを僕らにはひと言も話さなかった。 Mは僕らが想像していた通り、 安宿や橋の下を転々としていた。 治安の悪い裏通りでSは丹念に聞き込みをして歩き、 ときには聴きとれないドイツ語で住民に罵倒され追いかけられもした。 僕らが強制送還された数日後、 Sは東洋人を見たという子どもたちから話を聞くことができた。 ハンチング帽を被り長靴を履いて自転車のゴムチューブを得意げに見せびらかす生意気そうな子。 重ね着した半袖シャツに玩具の保安官バッジをつけた鳥の巣みたいな髪の子。 前髪を切りそろえて顔の下半分を煤で汚したチェックのズボンと編み上げ靴、 だぶだぶのセーターの子。 少し離れた背後で半ズボンの子が愉快そうに笑っている……。
ゴムチューブの子はなんだかJみたいだな、 その隣にいるのはさしずめPやGか、 背後にいるのはピートBやおれよりも、 ハリケーンズのドラマーRみたいだとSは思った。 子ども版のJは 「わんぱく坊主ウィリアム」 さながらに東洋人のことをまくしたて、 隣の仲間たちがやかましく口を挟んで訂正や補足をし、 半ズボンの子はただ離れて笑っていた。 子どもたちの話によれば東洋人はいつも酒臭い息を吐いて朝に現れては、 新聞紙にくるまって午後まで寝ていた。 どこかへ出かけていって血を浴びて帰ってきたこともある。 それがある日、 急に姿を消したという。 正確な日付を子どもたちは憶えていなかった。 撮影会の日にちがいないとSは思った。 Mの足取りはそれきり途絶え、 なんの手がかりもなく途方に暮れていると呑気な手紙がGから届いた。 凱旋公演はどこでも好評だとか新しい楽器がほしいから金を融通してくれとか音盤を買ったとか、 故郷での仕事や暮らしぶりについて書かれたなかに、 僕の実家にMが出入りしていたこともついでのように触れられていた。 まったくいい気なもんだよな、 さんざん心配させやがってさ……とか何とか (膨大な手紙でひたすらボケ倒し、 老成したSにいちいち突っ込んだり窘めたりしてもらっていた僕は、 なぜかMのことを書き洩らしていた)。 拍子抜けしたSは、 住所不定無職のMがどうやって英国へ渡ったのか訝るとともに、 そんな些事に頓着しないおおらかな仲間たちを羨んだ。 あいつらきっと長生きするよ、 とかれは思った。 Mの謎を解き明かさねば親友Jの身に何かよくないことが起きる、 との得体の知れぬ強迫観念は、 手紙のおかげで雲散霧消した。 ばかげた探偵ごっこも、 自分が狂いかけているのではとの不安も忘れて、 新しい人生へ気持を振り向けることにした。
いっぽうザ・Bは老成していようが天才画家だろうが写真家の美しい婚約者がいようが何だろうが、 客に背を向けて黒眼鏡で俯くベーシスト抜きでもなかなかうまくやっていた。 その場しのぎに雇ったベーシストは二週間で大学へ戻った。 僕はリードギタリストだとGは主張し、 おれもやんねえと僕が宣言して、 無口のピートBがドラムセットから動くはずもなく、 僕ら三人はじっとPを見つめた。 Pはぶつくさ不平を述べたけれど、 あれだけ難癖つけてたんだからおまえやれよ、 との内心の思いを口に出す代わりに、 僕とGが以心伝心で口々に、 ルート音をなぞるのがやっとのだれかさんと較べてPのベースはメロディアスでいいよな、 うんそうだそうだとおだててやると、 まんまとその気になってくれた。 高価なフェンダーではなくヘフナーのヴァイオリン型ベースでPが妥協したのはこのときではなく、 ハンブルクのスタインウェイ&サンズの店でだったか。 いずれにせよ音楽の申し子たる我が相棒Pとは正反対に、 Sの才能が画業にあるのはだれの目にも明らかだったし、 教えるより自分で演ったほうが早いとPが考えるのも自然な流れだった (のちにGやRに対してまでこの態度を見せたのはいただけなかったけれど)。
ピートBのお袋さんの店で一九六〇年を締めくくった僕らは、 うちの息子のグループをよろしく、 との彼女の熱心な売り込みの甲斐あって、 新年早々リザーランド市民講堂、 聖ジョンズ講堂、 エインツリー会館、 レイサム講堂それにまたモナBの店と、 来る日も来る日も演奏に明け暮れた。 アレクサンドラ講堂に出演した翌日の一月二十日、 帰国したSに再会した。 親友としては嬉しかったものの、 Pのベースで軌道に乗りはじめたグループとしては微妙だった。 Sにしても微妙だったのだろう、 この時点ではまだ本来のベーシスト復帰ってことになっていたものの、 徐々に僕らと距離を置くようになる。
寒空のもとMを探し歩いたSは風邪をこじらせていた。 扁桃腺を腫らしたSを船に乗せたくなかったAは、 撮影助手の給料から大枚はたいて航空便の搭乗券を買い与えた。 生涯に影を落とす貢ぎ癖がこのときすでに表れていたわけだ。 いま思えばこれは母親からの遺伝で、 当時は気づかなかったけれど僕らがあの屋敷で受けた歓待も実はそうした浪費の一環だった。 幼すぎた僕らはもちろん、 実の娘のAですらその金が宝石や食器を売って得られたとは夢にも思わなかった。 異国の港町での武者修行で、 汗水垂らして稼がなければ切れた弦一本すら買えないのは身に染みていたのに、 いまだどこかで金というものを自然に湧いて出るかのように錯覚していたのだ。 資産家の出自ゆえの才覚でザ・Bに富をもたらしたYにいわせれば、 僕らはいまだにそうだという。 相棒のPは金になる曲をいくらでもひねり出せるし、 僕がそうしないのは単にその気になれないだけ。 酒に溺れた一時期を除けばRはいつだって現状に満足していて、 締まり屋ときたらGくらい (GとそれにMだけは、 悪い大人たちに騙されぬよう当時からAにたびたび忠告していたようだ)。 金にまつわる幼さはBEを亡くして会社を興したときにも付きまとい、 僕らを離別へと導くことになる。
Mやジツゾン一派と出逢った 「皇帝壕」 にせよモナBの店にせよ、 北海のどっち側にも地下室が多かったのは、 欧州がいまだ戦後を引きずっていたせいだと思う。 防空壕を改装した 「洞窟」 にザ・Bとしてはじめて出演したのはこの年の二月九日だ。 僕とPは学生時代にロックンロールを演奏して叩き出されたことがあったけれど、 GとSには初舞台。 お洒落のためには他人の常識など頓着しないGは、 お気に入りのジーンズに革ジャンで現れ、 案の定、 用心棒と押し問答になった。 経営者や演目こそ替わっていたものの、 当時はまだ気どったジャズクラブ時代の名残があったのだ。 反抗を気どりながらも多少は空気の読めた僕とGとSは、 別珍の襟がついたドレイプジャケットや排水管に喩えられる細いパンツ、 ひとり我が道を行くピートBは黒シャツにネクタイといった格好で、 みんなそれはそれで大人たちに眉をひそめられ、 この不良どもめ、 おまえらのために戦争で闘ったんだぞ、 と罵られる代物ではあったけれど、 泥や埃や機械油を連想させる労働着に較べれば、 少なくとも喧嘩騒ぎは起こすまいと思ってもらえた。
こんなくだらないことで仕事をふいにしたんじゃたまらない。 僕やPが焦って苛々していると、 出演者なんだからいいじゃないの、 と聞き憶えのある声がした。 僕ら五人はびっくりして振り向いた。 あの間の抜けた笑顔でMがそこに立っていた。 メンディップスに通っていた頃とおなじ背広姿だ。 まるで伯母や僕と別れて家を出て、 すぐにまた戻ってきてそこに立っているかのようだった。 なんだなんだ、 と騒ぎを聞きつけて経営者まで顔を出した。 乞食の衣裳がまずいからってブレヒトの舞台を演らないなんてことがあるかい、 とMは珍妙な屁理屈を開陳した。 変な日本人に煙に巻かれた経営者は目をぱちくりさせ半開きの口からおお、 とかうう、 とか曖昧な声を漏らして僕らを通した。 用心棒は世にも奇妙な珍獣でも前にしたかのような目つきで僕らを見ていた。 あのブレ何とかの乞食ってのは何なんだ、 と楽屋へ向かいながら僕は尋ねた。 知るかよとMは肩をすくめた。
リヴァプール中心部のビジネス街にあり大きな商店街にも近かった 「洞窟」 は、 客層が 「皇帝壕」 とはまるで違った。 秘書、 事務職、 会社の雑用係、 郵便配達不、 電話交換手、 店員、 美容師見習い……みんな背広にネクタイ、 スカートやワンピースの、 きちんと学校を卒業した十代後半の若者ばかりで、 水夫も港湾労働者もナチ上がりのごろつきもいなければ、 工場地帯から離れているので職工さえ見かけない。 僕らの出演回数をかぞえた物好きがいて、 それによればザ・Bは一九六三年八月までに少なくとも昼に一五五回、 夜に一二五回はこなしたのだそうだ。 不定期で催されていた昼興行は、 僕らが出はじめてから噂が広まり、 やがて平日の定番となる。 酒の代わりに安い軽食 (スープつきロールパン九ペンスとか紅茶五ペンスとか) が出て、 会員になれば昼休みに最大二時間まで僕らの演奏を楽しめる。 二時間も昼休みがあるやつなんていないから、 みんな時計を気にして後ろ髪を引かれながら職場に戻った。 遅刻して上司に叱られたり馘になったりした子もいたようだ。 贔屓客はそれまでにもいたけれど、 僕らがお目当てで満員御礼なんてのははじめてだった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)