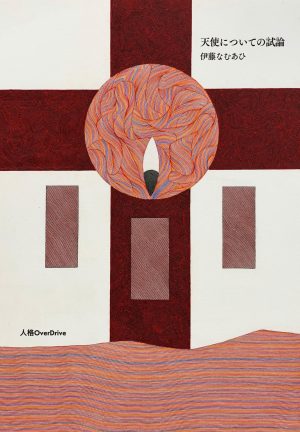しかし一九六〇年一二月九日の夕方にそんな途方もない幻覚はひとつも話題に出なかった。 甘ったるい酒で口の軽くなった僕は独り言のように喋りつづけた。 Mはあの間の抜けた顔で肯き、 相槌を打ち、 先を促したり僕のいわんとすることを整理して要約したりした。 のちに大金を払ってYと受診した高名な精神科医よりもあいつのほうがずっと聞き上手だったな。 そんな日が三日間つづいた。 Mは午後になると必ず現れて一時間ほど伯母と茶飲み話をしたのち、 僕の様子を見に上がってきてはイークラックへ連れだした。 僕らはザ・Bのことを議論したりくだらない冗談をいい合ったりした。 Mが僕に何かを書くよう薦めたのはこのときが最初だったのを憶えている。 曲でもハンブルク回想記でもいいから、 とにかく何か書けよとかれはいったのだ。 数世代にわたるレノン家の年代記を書いてみたいと打ち明けた気もするけれど、 それがまさかこんな本になるとは思ってもみなかった。 四日目に僕はようやく婚約者と逢う気になり、 Mが訪れる前に出かけていった。 そのことを伯母に聞かされたMはもう大丈夫と判断したのだろう、 翌日は現れなかった。 それどころかあの撮影会の日と同様に、 またしても僕の前から姿を消したのだ。 連絡先を聞いておかなかったのを悔やんだけれど、 グループを再開してやることが急に増えたので、 ほどなく心配するのを忘れてしまった。
数年後あのとき何を話していたのか伯母に尋ねた。 経理や法律の勉強をするようMからしつこく薦められていたという。 Jの成功に備えておかなければと力説されたそうだ。 途方もない夢物語だし、 女しかもすでに若くない下宿経営者が学問をするような時代でもなかったので、 伯母はもちろん本気にはしなかったけれど、 甥のばかげたお遊びが実を結ぶとか、 知識で甥を護るとかいった考えはまんざらでもなかったようだ。 いわれてみれば当時、 伯母の蔵書にはその手の本が急に増えた気がする。 前にも述べたように伯母は古風なようでいてその実、 型破りで先進的なところもあったのだ。 そこはやはり僕の伯母でありあの母の姉でもあった。 そして僕や母と少しだけ異なり、 それでいて僕に少なからず影響を及ぼしたのは、 知識は人生を豊かにすると固く信じていたことだ。 だからメンディップスには本がふんだんにあったし、 女として生まれたがために知識から隔てられ、 それゆえに男のような就業機会に恵まれなかったことを、 伯母は内心で悔しがっていた。 彼女もまた人前で弱みを見せるのはみっともないと考えていて、 実の息子も同然に育てられた僕でさえ、 その傷ついた自尊心と劣等感に気づかなかった。 それをMは初対面で見抜いたのだ。 一九六九年、 会社の財務管理をだれに任すかで揉めた際、 Mが持ち出した突拍子もない案はこのときすでに種が蒔かれていたわけだ。
いま思うとちょっと笑えるのは、 帰国しておきながら仲間にいっさい連絡をとろうとしなかったのは僕だけじゃなかったということだ。 だれもが互いを薄情に思いながら自分からは電話をしなかった。 便所臭い楽園を自分だけが追放されたと思い込んでいたGは、 PとピートBも強制送還され地元に戻っていると伝え聞いて安堵した。 しかしまさか 「親分」 ことJLもだとは思いもよらなかった。 Mと婚約者のおかげで元気を取り戻した僕は、 渡独前に一二回ほど演奏したスレイター通りの喫茶店 (当時のマネージャとはその店で知り合った) へ赴き、 Sからの手紙を取りに現れたGと鉢合わせした。 ハンブルクでの失敗を恨まれているにちがいないと僕は身構えた。 ところがGはそんな態度はおくびにも出さず、 無邪気に顔を輝かせて再会を喜んでくれた。 僕らは背中を叩き合ったり肩を小突き合ったりばかげたことをいい合ったりした。 そのあとは案の定しこたま怒られたけれど、 その理由はリーダーの力不足ではなく、 あんたの帰国を知っていればもっと早く活動を再開できたのに、 ということだった。 それから工場勤めのPを冷やかしに行った。 のちにリードギターもドラムも小器用にこなして口やかましく指図し、 GやRを怒らせるPだけれど、 世間一般のまっとうな労働にはまるで適性がなかったらしく、 職安で紹介された荷下ろしの仕事をすぐ馘になり、 次の工場でも同僚がコイルを八個から一四個も巻くあいだに一個半巻けるかどうかのありさまだった。 そこへ僕らがやってきて 「よっ真面目!」 とか 「労働者の鑑!」 なんてからかったんで、 かっとなったMは、 父親の苦言 (怠け者には悪魔が憑くのだぞ、 息子よ……) が一瞬頭をかすめたものの、 ええい知ったことかと巻きかけの銅線を投げ棄て、 僕らといっしょに塀を乗り越えて職場から逃亡した。
凱旋公演はその二日後、 前年に (僕の誕生日の前日だった) 報酬で揉めてそれきりになっていたピートBのお袋さんの店でやった。 PとピートBは別の出演者から楽器を借りた。 Sの代役にはピートBが元いたグループのリズムギターを勧誘した。 ピートBの親友でやがて異父兄弟の父親にもなるNが 「帰ってきた伝説のザ・B」 なる告知チラシを店内のあちこちに貼った。 友情の証のつもりだった。 ハンブルクでの活躍を知らないので、 いまだ素人臭い不良のおふざけにすぎないと決めつけていたのだ。 かつて僕らがペンキ塗りのバイトをした元石炭置き場の地下室 (モナBが競馬で当てた金で改装した) には、 異国情緒溢れるドイツ人グループを期待する客が詰めかけた。 僕らの田舎町じゃ外国の文化に触れる機会なんてそうなかったからね。 そこへ僕らが現れたんで、 なんだこいつらかよ騙された、 そりゃこんな店に大物が来るわきゃないよな……とでもいいたげな失望の空気が流れた。 でも僕らは去年の僕らじゃなかった。 僕が足を踏み鳴らして調子をとり、 PとG (及び店主の息子とSの代役) を従えて演奏をはじめると、 観客の態度が一瞬にして変わった。 飛び跳ねたら頭が天井を突き破るほど狭い地下室 (実際そんなことがあった) は熱狂した。 暴力団が睨みを利かせ水兵が殴り合う地獄で鍛えられるうちに演奏も、 客を盛り上げる手管も格段に向上していたのだ。 成長した息子をうっとり見つめるモナBの表情が忘れられない。 母がいたら彼女も僕をこんなふうに見てくれたろうか。 二階に下宿していたNはピートBの弟に呼ばれて慌てて降りてきた。 かれの目つきが変わるまさにその瞬間を僕らは見た。 週給二ポンド十シリング昼飯つき、 夜も通信講座で出世をめざす前途洋々たる会計士見習いが、 そのすべてを擲って僕らの運転手に、 やがて社長に、 ついには知的財産を護る語り部にまでなる人生は、 このとき運命づけられたのだ。
翌々日にはマネージャがクリスマスイヴの仕事をとってきた。 渡独の前月まで土曜夜に出演していたリスカードにある店だ。 かつて毎週末に集まる物騒な客への苦情が近隣住民から寄せられ (一度などワラジーとシークームの不良のあいだにザ・フーの映画もかくやという乱闘騒ぎが起きて、 Pはご自慢のエルピコ社製アンプを救おうと渦中へ飛び込むはめになった)、 取りやめになっていたロックンロールがその夜だけ解禁されたのだ。 ハンブルクに残してきた楽器や機材はこのときにモナBが船便で取り寄せていた。 彼女は息子とともに税関の倉庫へ向かい、 寒風吹きすさぶ岸壁で、 タクシーに乗せるために木箱を解体しなければならなかった。 馴染みの道具を取り戻したおかげでここでも僕らは大成功を収め、 さらに三日後のリザーランド市民講堂での公演はいまも語り草となっている。 あれからしばらくは街を歩くたびにサインをねだられ、 英語が流暢ですねと褒められたものだ。
この仕事はのちにBEとの仲を勘ぐったことで僕に公衆の面前で殴打されることになる 「お父つぁん」 ことボブWが手配した。 いい歳してロックンロール熱に感染し、 鉄道事務員からDJ兼司会者に転身した三十路のゲイだ (年齢は鯖を読んでいたし指向も巧みに隠していた)。 マネージャがハンブルクを真似て開店したばかりの店を、 かれは 「ソーホー通りの熱いスポット」 と宣伝した。 僕らも出演を楽しみにしていたのに、 その店は電気の使いすぎによる出火でたった六日で焼失した。 ちっとばかし熱すぎたってわけだ。 保険金目当ての放火を噂されたマネージャは胃潰瘍で入院した。 僕にいわせりゃ避妊具の呪いってとこだね。 邪悪なザ・Bよ、 次は帰国して地元の映画館に火を放て……みたいな。 マネージャは病床でボブWに無念を訴え、 ザ・Bの連中を頼むといい残してがっくり力尽きた。 ボブWはマネージャの名を叫んで号泣し、 マネージャはなんだなんだとびっくりして目を醒ました。
性的指向にかかわらず男気に溢れたボブWは一銭の得にもならぬのに奔走し、 顔なじみの興行主に僕らを売り込んだ。 あいにくこの興行主、 前年五月に契約をばっくれて先輩歌手とスコットランド公演へ行った僕らを恨んでいたので、 ボブWはひたすら拝み倒さねばならなかった。 すでに刷られていたチラシには 「ハンブルク直送!」 なる煽り文句が書き加えられた。 背広とネクタイ、 センターロールリーゼントで決めた男の子たち、 ドレスでめかし込んだ女の子たちが三百人、 足取りも軽く集まってくる。 もぎりのおばさんに三シリング払い、 男女が左右のクロークに別れて上着を預け、 番号札を受け取る。 両開きの扉を押してホールへ入場するとそこがダンスパーティ会場だ。 ここで僕らは客が踊るための伴奏を演ることになっていた。 前座の数組はもちろん注文通りの仕事をこなした。 悪いグループじゃなかったよ。 ただ当時の平均だったってだけの話だ。 ロバート・ゼメキスのSF映画を思い描いてくれたらいい。 あれは一九五五年の米国が舞台だけれど、 五年後の僕らの地元も似たようなものだった。 要は呑気で平和な時代だったということだ——このときまでは。
ついに僕らの出番となる。 打ち合わせ通りボブWが叫んだ。 ハンブルク直送、 センセーショナルなザ・Bの登場です!
Pのリトル・リチャードばりの高音に合わせて緞帳がさっと上がる。 黒革ジャケットに黒の細身ジーンズ、 銀のウェスタンブーツ、 センターロールリーゼントにピンクの帽子。 そんなド派手なドイツ帰りの奴らが 「のっぽのサリー」 を演りだした。 こいつでのんびり踊っていられるもんならやってみろよ……。 ゲイの夫が外でやっている恋愛を専業主婦に密告してやろう、 という悪意に満ちた歌詞を、 Pは中年男の若い女との不倫にわかりやすく改変して高く叫んだ。 当時は流行歌の歌詞を掲載するウェブサイトなんてもんは存在しなかったので耳と憶測に頼るしかなく、 僕らのレパートリーは大概どこかまちがっていたし、 まして性的少数派の機微なんてものは理解の埒外だったのだけれど、 Pが 「惨め」 を 「憂鬱」 に置き換えたのはわざとだと思う。 商売敵ストーンズの朧気兄弟ほどではないにせよ僕らなりに米国黒人文化には敬意があったわけだ。
センセーショナルってのはいい得て妙だったね。 観客は呆気にとられて動きを停めた。 それから舞台前へ詰めかけ、 押し合いへし合いし、 しまいには金切り声で叫びだした。 最後の 「ホワッド・アイ・セイ」 を演る頃には大騒ぎで収拾がつかなくなった。 だれもが僕らの真似をして狂ったように足踏みした。 Pなんかマイクをスタンドから外してギターを下ろし、 舞台狭しと跳ねまわっていた。 リズムを刻み仲間たちを煽り両脚を踏みしめて叫びながら、 僕はまんざらでもなかった。 それまでは自分らを悪くないと思っていた。 いいと思いはじめたのはこのときが最初だ。 やがて僕らは最高だと確信するようになる。
それが一九六〇年のクリスマスイヴに起きたことだ。 時代は変わりはじめていた。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)