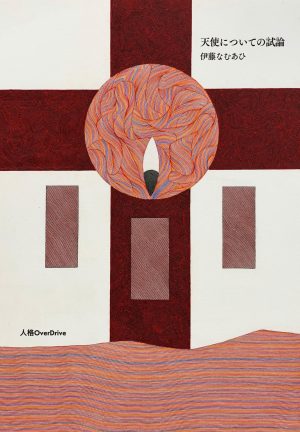僕は歴史家としては落第だ。 かつて幾度となくMが真顔で僕に伝えようとしてくれていたときには、 その戯言はもうよせよ、 酒が不味くなると遮り、 聞き流してしまった。 おかげでいざ書こうとしてみると何ひとつ思いだせない。 前章で書いたことはずっと後になってオルダス・ハクスリーの小説を読んだり、 のちのカリフォルニア州知事が出ている映画を観たりして、 記憶を掘り起こすというよりも捏造したにすぎない。 敗戦国の港町で武者修行をしたり大挙する女の子に髪の毛をむしられたり失言で音盤を焼かれたり外国で暴徒に殺されかけたりCIAに盗聴されたりしなければ僕ら四人の経験がわからないように、 戦場にいなかった人間にその戦場について語る資格は本当はないのだ。 しかし出版されたばかりの小説の数々を、 これは歴史に残る本だから絶対に読むように、 としょっちゅう押しつけてきて (粗雑な紙に印刷された両側から読むことのできるペイパーバックSFのこともあれば、 聞いたこともない南米の作家のこともあった)、 言葉遊びのおふざけじゃない物語を書け、 と僕にうんざりするほど薦めたMのことだ、 きっと許してくれるだろう。 いうなればこの本はかれとの約束を果たすための、 あるいは大きな負債を返すための物語なのだ。
Mは僕らにはよくわからない理由で急に激昂して手がつけられなくなることがよくあった。 戦争は支配層のための産業だとかれはしばしば口にした。 軍隊が護るのは民衆ではなく自分らの面子と権力の利益だとも。 深酒して口論した翌朝、 悪夢にうなされるMを僕は一度見たことがある。 冷凍七面鳥 (ヘロインの離脱症状) にそっくりだった。 その五年ほど前、 みんなでLSDをやっているときピーター・フォンダがくだらないことをクドクドといいだして、 それで思いだしたかのようにMが、 焼けて腐った屍体の山は独特の臭いがするんだよな、 と呟いたのを思いだす。 鼻腔の奥にこびりついて拭い去れずまだ臭うかのようだと。 僕はすぐさまあの大根役者を辛辣にやりこめたけれど、 楽しい気分は台なしになったものだ。 いっぽう僕ときたら十代のとき、 法律が変わって兵役を免れて心底ほっとしたし、 戦争体験といえばスーパーマンの続編で名高い監督とスペインで映画を撮ったくらいで、 まだ熱い銃の唄だって比喩でしかなかった。 僕の街で双子ビルが倒壊したときはいよいよ年貢の納めどきかと思ったし、 いまもウクライナやパレスチナ、 スーダンやコンゴの情勢は憂えているけれど、 僕個人は撃ちも撃たれもせぬまま生涯を終えられそうなのを神に感謝している。 Mがかれの世界で経験したことも、 二番目の妻が幼少時に東京で経験したことも本当の意味では理解できまい。 でもそれでいい。 僕はかれらの経験を理解できるような経験をしたくない。 家族や友人のだれにもしてほしくない。
気がかりなのはMの述懐が現実になりつつあることだ。 「人間の意思決定に影響を与えたり取って代わったりするための自動化されたシステム」 なるものについてかれは話していた。 かつてMとKそれぞれの母国がやったようなことが、 極めて効率のよい電子的手段で行われるようになり、 それによって世界が分断され民主主義が崩壊する……云々。 そうして政治家が地位に留まるため、 資本家が儲けるための戦争が永久につづくようになるのだと。 当時は一笑に付したものの、 晩年のティモシー・リアリーの楽観論で逆に不安になりはじめ、 最近はごく普通のひとたちが携帯電話に操られて米議会を襲撃したり、 ホームレス支援をしていた地元の図書館を焼いたりするようになり、 さらには知り合いの研究者が出自を理由に馘首されて国を追われ、 歌詞やMCで政府を批判した同業者たちが、 かつての僕のように海外公演からの再入国を拒まれ、 あげく蝋人形みたいな僕がニッコリ笑って政治家や資本家と握手する動画が出まわるに至って、 Mが話していた世界が近づいたのを実感しつつある。 Mと知り合わなければ僕だってきっと騙されていた。 自分で歌わなくていいから楽だとか雇わなくていいから節約になるなどと考え、 抗う連中を時代遅れと批判さえしただろう。 現にギターの名手で知られた友人はすっかり陰謀論に染まってしまった (かれの場合はMに毛嫌いされてかえって差別主義者になった節もあるけれど)。 でもハンブルクでジツゾン一派と出逢ったこの僕は、 Mが話してくれたことをまだ憶えている。 さすがにこの歳になると若い頃のような声は出ないし、 切れ者の妻もすっかり弱って、 ふたりで寝台に籠城したり袋に入ってどんぐりをプーチンやネタニヤフや習近平に贈ったりはもうできないけれど、 幸い僕にはまだ言葉があって、 だからこれを書いている。
ダンスフロアの前に離れて座るKとMのことは、 僕らも演奏中ずっと気になっていた。 元はストリップ小屋だった前の店で増えはじめていた女学生ファンも、 物騒なこの店には寄りつかなかった。 紫煙に霞む店内はならず者と売春婦ばかりで、 若きグラフィックデザイナーは明らかに異質だったし、 浮浪児めいた日本人はそれ以上に目立っていた。 かつての同盟国とはいえ有色人種を 「淘汰」 しようとした過去を持つ国でその存在は稀で、 まして敵国の寂れた港町出身である僕らにとっては、 故郷でもそれどころか映画のなかでさえも見たことがない人種だった。 西部劇の酒場での乱闘シーンみたいな大立ちまわりがしばしば演じられ、 シャンデリアに飛びついて跳び蹴りを喰らわす男さえ現実に目撃された店で、 どうしてあのふたりが喧嘩をふっかけられなかったのか不思議に思える。 Kの印象ではその夜のMは、 災いや厄介ごとそのものの臭いを発散していたのだそうだ。 それは船乗りや犯罪者らの腐ったチーズみたいな体臭に負けずに嗅ぎとれそうで、 だからこそ獣じみた屈強な男たちは、 その異邦人を本能的に避けるかに見えたのだという。 つまり、 のちに僕が感じることになる気配をK (とかれの主張によればほかの客) はその夜すでに嗅ぎとっていたということだ。 僕らの野蛮な音に惹きつけられて店に足を踏み入れたその瞬間から、 Kは理性の箍がはずれていた。 その禍々しさに逆に惹きつけられるかのように、 かれは何度も東洋人を盗み見た。 そのとき舞台に立っていたのが僕らではなかったせいもある。 そのグループは地元でこそ僕らよりずっと格上だったけれど、 一九六〇年十月のこの時点では、 猿みたいに動きまわる痩せた金髪男の派手さだけが売りで、 お揃いの背広やネクタイは、 格子模様のジャケットに細い灰色の安っぽいネルパンツに尖った靴、 といった僕らと較べると大人しく見えた。 見どころといえばリーゼントの髪にメッシュをいれた憂鬱そうなひげのドラマーくらいだった。 そのひげはもみあげとつながっていて、 九年後の喜劇映画で 『おまぬけ劇場』 のピーター・セラーズと共演する男と同一人物には見えなかった。
東洋人のほうでもこちらを意識していると見てとるやKは、 意を決して酒と荷物を手に立ち上がり、 近づいて話しかけた。 きみもあのグループが目当てなんだろう? そして答えを待つ前に隣に座った。 向かいに座らなかったのは舞台に背を向けたくなかったからだ。 内心では自分の度胸に驚き、 とんでもない冒険をしているかのようにワクワクしていた。 口が利けないのか、 それとも言葉がわからないのかと疑うくらいの間があって、 東洋人はエジプトの死の神アヌビスを思わせる目を糸のように細めて笑い、 例の発音しにくい名前とラテン語めいた苗字を口にして、 Kと握手した。 そのときのドイツ語は確かに片言に思えた、 とKはのちに僕に証言した。 ふたりはお目当てのヒーローたち (僕らのことだ) が舞台に上がるまで、 僕らのことやKの仕事について話して意気投合した。 Mは自分がどこから来たのか、 日々どうやって暮らしているのかをいいたがらず、 ここはいい街だねとだけいった。 治安の悪い歓楽街をそのように表現する東洋人にKは笑い声をあげた。 Mの訛りはすぐに消え、 話し下手な自分よりもむしろ流暢になったので、 最初の印象は気のせいだろうとKは結論した。
「急がば廻れ」 は知ってるかい、 米国の流行歌なんだけど。 ベンチャーズだっけ? となぜそれを自分が知っているのか訝るような顔でMはいった。 うん、 そいつをタイフーンズなる国内グループが吹き込んで、 そのジャケットを手がけたばかりなんだと説明してKが実物を見せると、 Mは目を丸くしてすげえといい、 画材や技法について熱心に質問した。 宮沢賢治が自分で描いた 『月夜の電信柱』 みたいだなともいった。 だれだって? とKが尋ねた途端に僕らの出番になった。 常連たちがマックシャウ! と野次るように囃し立てた。 元はナチあがりの興行主が僕らを鞭打つ 「もっと盛り上げろ!」 的な言葉だったのだけれど、 みんなが真似るうちに広まってしまったのだ。 KとMは高純度の麻薬でも打たれたかのように言葉をなくし、 体を揺すったり声をあげたり笑って拍手したりした。 僕らが 「豆ッコ」 や 「名誉戦傷章」 で目をギラギラ輝かせ、 着たきりの舞台衣裳をビール臭い汗でぐっしょり濡らして、 ビールの木箱に板を渡しただけの舞台 (わざと飛び跳ねつづけるうちにやがて壊してしまった) を降りる頃には、 グラフィックデザイナーと元兵士も自前の化学物質で目を輝かせ、 うっすら汗をかいていた (後者は黒い錠剤の離脱症状だったかもしれない)。 KとMは互いに考えを読んだかのように同時に顔を見合わせた。 Mが次に何をいいだすかKにはわかっていた。 あいつらにも見せようぜ、 そのために持ってきたんだろうとMはいった。 Kは決然と肯き、 勇気を奮い起こしてMとともに舞台前のダンスフロアのそばの席へ向かった。 水夫や犯罪者に奢られたビールを干している僕らに近づき、 ふたりは順番に自己紹介をした。 記憶ではKは画家を名乗ったがMはただ僕らのファンと告げたはずだ。 日本人であることは自分からいいだしたような気もするし、 僕かGが無遠慮に訊きだしたようにも思う。 かれが前世について口走るのはLSDの時代になってからだ。 このときのかれはなぜ自分がそこにいるかまだ知らなかった。
リーダーと勘違いするほどSに魅了されたにもかかわらず、 Kがまっ先に作品を見せたのが僕だったのは、 近い位置に座っていたからか声が大きかったせいか。 踵の高い尖った靴を履いてギターを弾く男の絵に僕は内心では感心したものの、 美術学校の落第生としては他人の画才を素直に認めるのも癪だったし、 仲間たちにタフガイで通している手前、 安易に気を許すわけにもいかず、 うちの芸術家に見せな、 とSを顎で示して冷ややかにいい放った。 Kという男は繊細に見えて鈍感というか図太いところがあり、 僕の拒絶をそれでこそロックンローラー、 とでもいいたげに興がるような態度を見せ、 すぐさまSをつかまえてぎこちない教科書英語で芸術論を交わしはじめた。 そうなると残されたMを前に僕たちは、 この東洋人はなんでここにいるんだとなる。 無口なのにやたら女にモテるピートBと相部屋にされて不貞腐れていたPは、 持ち前の如才ない愛想よさを発揮するどころか、 SやGに嫉妬するだけでは飽き足らず、 僕に近づくやつはすべて敵視するようになっていて、 案の定、 警戒心を丸出しにするし、 前途有望たる画業をなげうって僕らと運命をともにしたSは地元芸術家との交流に夢中。 まだ幼いGは生まれてはじめて見る東洋人に興味津々、 無口なモテ男ピートBだけが好みの売春婦でもいたのか、 退屈そうに救命艇席を眺めている。 Mは黙ってニヤニヤ笑うばかりだ。 この頃のザ・B (ピートB除く) はあまりにも一緒にいすぎて自分が感じているのがだれの気分なのかわからなくなるほどだった。 メンディップスの蔵書を通じて東洋の文化に関心があった僕は、 実のところGに負けないほど好奇心が疼いていたのだけれど、 Pの気分が感染して徐々に苛立ちはじめた。 拙い二カ国語が入り混じる会話が聞こえてくる。 ナインナイン、 リーダーはJだよ、 エ・イス・デ・アンフューラ、 僕ら五人はかれにひっぱられてこの国に来たんだ……とかなんとか。 するといきなり東洋人が僕にいった、 ベースのかれが画家ならリーダーのあんたは作家だね。
ずいぶんと突拍子もない台詞で、 僕らのあいだに張り詰めていた緊張がそこで切れた。 なんでそんなこと思うんだよ、 おれはロッカーだぜと僕はいった。 強面に威圧するつもりだったのについ笑ってしまった。 つられてPまで失笑した。 だってヨハネとかジョヴァンニってやつは作家の守護聖人だろ、 うってつけの名前じゃないか、 作曲して歌詞を書いたりもするのかい? 僕とPは弱り顔を見合わせた、 書いてるちゃあ書いてるが……。 じゃあなんで演らないんだ? 客が知らん曲を演ったってしょうがねえだろ。 僕とPは痛いところを突かれてちょっと自尊心を傷つけられた気分になった。 音盤も出していないグループが自作曲を演奏するのは当時まだ一般的な習慣ではなかったのだ。 するとMは節をつけて数えるようにいいはじめた。 J、 饒舌なる作家にしてリーダー、 ザ・Bの精神、 きみがいなくちゃ何もはじまらない。 そしてきみは (といって急にPを指さし) さしずめ演出家、 ザ・Bをまとめ上げ成功させるのはきみだ (これをいわれたPは冷ややかな態度を装いながらも、 まんざらでもない様子だった)。 そして (と今度はGに) ザ・Bに新しい風をもたらすのはいつだってきみだ、 珍しい和音や米国で発売されたばかりの音盤、 それに人脈……。 バーカウンターへ向かったピートBにだけはなぜか言及せず、 むしろ別の誰かを目で探すような素振りを見せた。 なんだよあんた千里眼か? と僕がいってやると、 当たらずとも遠からずだねとMは応じた。 なんだか最近、 昔を思いだすみたいにおかしな考えが頭に浮かぶんだよ。 ひねくれ者揃いの僕ら三人はちょっと狂ったやつのほうが好みだった。 次に何をいいだすのだろうと愉快になりはじめたところでSが振り向き、 新たな友人たちにザ・Bのメンバーを改めて紹介した。 いわば僕らにとって歴史の歯車が噛み合い、 動きだした瞬間だった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)