その日の朝、 アイムスビュッテラー通りの屋敷で慌ただしく身支度をしたAは、 寝たきりのSに屈み込んで行ってくるわと接吻した。 Sは痩せこけた顔に弱々しい笑みを浮かべ、 行ってらっしゃい気をつけてと見送った。 婚約者が出ていくのを待ってかれは笑みをつくるのをやめ、 目を閉じて壁へ顔を向けた。 その日も恩師の写真館は忙しくSの容態を思う余裕はなかった。 まだ若い彼女は自分のキャリアと画家の卵との幸福な未来を当然のように疑わなかった。 子どもが生まれ、 喧嘩したりともに悩んだりしながら育て上げ、 いずれ大成した芸術家夫婦として孫に囲まれる未来を信じていた——午すぎに電話で呼び出されるまでは。 半狂乱の母親の言葉は聞きとれなかった。 何? Sがどうしたの? 何をいっているの……? Aは恩師に事情を説明して車に飛び乗った。 心が麻痺したようだった。 これまでにもこんなことはあった、 いつだって取り越し苦労で翌日にはケロリとしてたと自分にいい聞かせた。 部屋に駆け込むとSは白目を剥き胃液にまみれて痙攣しており呼びかけに応じなかった。 救急車が近づくのを聞きながらAは婚約者の手を握りしめて名を呼びつづけた。 ぜいぜいと喘ぐSはようやくAの視線を捉え、 息も絶え絶えに呟いた——ごめん。 確かにそういってまた意識を失った。 サイレンが階下で鳴り響き、 数人の看護師が駆け上がってきて、 Aを無遠慮に押しのけSを担架に載せた。
病院へ向かう車中で担架の隣に座り、 手を握りしめる婚約者をSは認識していないようだった。 喘ぎが徐々に弱まって聞こえなくなり、 険しかった眉間の皺がふっと緩んだ。 病院の搬送口に救急車が横づけされるとAは担架が運び出されるのを待たずに飛び出し、 聴診器を下げた白衣の医師にすがりついて助けを求めた。 彼女に腕を引かれてつんのめるように救急車へ向かった医師は、 Sを見下ろすなり顔をこわばらせた。 そして弁解がましく脈を取り、 お気の毒ですがと首を振った。 Aは何を告げられたか理解できなかった。 看護師たちが担架を病院へ運び入れた。 職員はみんな忙しそうで、 Aの懇願はだれの耳にも届かなかった。 Sの手はまだ温かかった、 今朝だって行ってきます行ってらっしゃいの挨拶を交わした、 ごめんって何が? 何を謝ったの? 真意を確かめなきゃ、 きっとSは何か勘違いしているのよ……。 搬入口に茫然と立ち尽くす彼女に、 白衣の事務員が話しかけた。 書類を作成しなければいけないのでおいで願えますか、 さぁそちらへ座って、 亡くなった方とあなたのお名前を教えてください、 保険はどうなっていますか、 なんですって、 S? ああ亡くなった方ね、 はいはい、 もうご遺体はこの病院にはありませんよ、 搬送中の死亡は法的には路上死なんで解剖が義務づけられてるんです、 それであなたのお名前は? ペンを構えて辛抱強く待つ事務員の前で、 Aは言葉を喪った。 自分の名前が思いだせない。
駆けつけた従兄弟に手続を肩代わりしてもらわなければ、 病院の椅子で日が暮れるまで茫然としていたろう。 どのようにして家へ帰り着いたかAは記憶になかった。 お帰りなさいをいってくれるはずの婚約者の部屋には、 反吐で汚れた寝台と描きかけの作品を掲げた画架があるきりだった。 思い描いていた幸福な未来を奪われたのはAだけではなかった。 母親もまた、 あたかも居間に暗い渦が現れてそれを見つめてでもいるかのような目でソファに座ったきりだった。 Kはふたりにかける言葉もなく、 場違いな闖入者になったように感じさせられた。 Sの実家には電話がなかった。 電報を打って戻ったKは、 屋敷の女主が白い棺桶のことを呟くのを聞いた。 すぐにあの葬儀屋へ注文しなければ、 どんなに高くても構わない、 あの子の願いを叶えてあげるのよ……。 そればかり狂ったようにくり返す彼女を、 Aの従兄弟が宥めて落ち着かせようとしていた。 Kはこの従兄弟と役場へ赴いて遺体を故郷へ返す手続をするのだが、 蓋を溶接した鉛の棺でなければ移送が認められないと告げられ、 Aの母親を説得するのに手を焼くことになる。
深夜に電話が鳴った。 雑音の混じる遠い音に言葉にならぬ啜り泣きだけが聞こえた。 受話器を握るKは責められたかに感じた。 自分だって親友を喪ったのだといいたかった。 受話器が落ちるような物音がして泣き声が遠ざかり、 Sの妹が母親が飛行機でハンブルクへ来ること、 遺体を地元へ運んで葬儀を行うことをKに告げた。 リヴァプール訛りが兄に似ていた。 かれは別の状況で知り合えたならSの話題で笑い合えたかもしれない相手に、 遺体が解剖され法医学局に安置されていることを説明しなければならなかった。 教科書で学んだ英語はそうしたことに不向きだった。 不的確な単語を補う単語の数々。 どうにか伝わった。 悲鳴が上がり受話器がひったくられた。 どうして無断で息子を切り刻んだの、 ほんとうは何があったのと回線の向こうの女は叫んだ。 彼女はのちに法医学局の霊安室で遺体と対面したときにもこの疑問をくり返した。 葬儀は四月一九日、 リヴァプール近郊のハイトンにある、 かつてSが少年聖歌隊にいたこともある聖ゲイブリエル教会の支聖堂で執り行われた。 そのために渡英した長男の婚約者に対して、 この母親は面と向かって公然と、 人殺しと責めなじることになる。 息子をかつての敵国へ連行して殺したザ・Bを彼女は恨んだ。 とりわけいじめ加害者と目されたPはSの妹たちにまで憎まれた。 しかし僕らはまだしも英国人であり同郷の人間だった。 Aはそうではなかった。 Sの言葉は正しい。 戦争は終わらない。 爆弾や銃弾が切り裂くのは人間の肉や建物ばかりではない。 土地にひとびとの心に、 ずっと残り続ける。
一睡もできずに夜が明け、 KとAはSの母親を空港へ迎えに行った。 何もかも順序が狂っていた。 まずSの入院を報せるAの従兄弟からの電報は弔電のあとに届いた。 海軍勤務の父親は二日前に南米へ向けて出航したばかりで連絡がとれず、 三週間後にブエノスアイレスで牧師から長男の死を告げられることになる。 ボウリング場でSの死を予感した元マネージャはその的中をAに電話で報され、 妻と話し合って、 せめて息子を喪った母親とAとのあいだを取り持ってやろうと決めた。 玄関先でお悔やみを伝えるとSの母親は膝から力を失い倒れそうになった。 慌てて支えてやったところで呼び鈴が鳴った。 電信局員が電報を届けに来たのだった。 元マネージャはザ・Bのハンブルク公演へ発つ後任者に電話して、 交通費は負担するから彼女を連れて行ってやってくれと頼んだ。 着任早々こんな重責を負うことになるとは思ってもみなかったがBEに断る理由はなかった。 青年実業家は病み上がりのGを車で迎えに行った。 同行者に怪訝な顔をしたGは理由を教わって泣き崩れた。 そのようにしてかれは元ベーシストの死を最初に知ったBとなった。 マンチェスター空港までの車中Gは幼い子どものように泣きじゃくった。 憎い不良仲間の一員とはいえこのときばかりは、 息子の若い友人の慟哭がSの母親の正気をかろうじて保たせた。 BEは自分たちの到着時間に空港へ来るよう残りのBに電報を打った。 Sの母親も一緒だと伝えたがその理由までは書かなかった。 よもや僕らが訃報を知らぬとはかれには思いもよらなかった。
いっぽう僕らは尾羽を備えた流線型の大型車の座席で、 脚つきグラスを手にして幸福の絶頂にいた。 雇用主たる風俗王がその勢力を見せつけるためか、 わざわざシボレーインパラを出してくれたのだ。 革と樫材の車内には最新オーディオやカクテルバーを完備、 もちろん運転手付きだ。 そんなの映画でしか見たことない。 昂奮の余韻が醒めやらぬなか、 ぺちゃくちゃお喋りをしながらGとマネージャのふたりを空港で待っていると、 思いがけない旧友たちの姿を見つけた。 おお、 と僕らは懐かしさに胸を満たされて大きく手を振った。 近づくふたりの暗い顔や、 僕らの足許に幽霊でも見たかのようにぎょっとしたことなどが、 僕の近眼にはわからなかった。 豪勢な気分を引きずる僕は陽気に尋ねた、 Sは? 死んだよとKは不機嫌に答えた。 虚を突かれた僕はおいふざけんなと吼えてかれの襟首を掴んだ。 顔を背けた友人の目に涙を認め、 冗談ではないのを悟って振り上げた拳を寸前で下ろした。 そしてその場の空気にやっと気づいた。 俯くAにPが近づき、 そっと腕をまわして慰めた。 ピートBは無言で茫然と涙を流している。
伝説ではここで僕は急に笑いだしたことになっている。 AとKもそう思い込んだようでかれらのインタヴューではいつもそう説明されている。 そう単純じゃないと後年に弁護してくれたのはPくらいだ (Mはあの場にいなかった、 肝心なときはいつだってそうだ)。 畜生、 笑ったりするもんか。 分身みたいに思っていた一番の親友が死んだんだぞ。 自分の感情をどうしていいかわからなかった、 ただそれだけだ。 Kは僕らの親友が大量の脳出血であっという間だったこと、 原因はわからないが脳が頭蓋骨を歪めるほど膨張し、 圧迫された血管が破れたらしいこと、 遺体は法医学局の霊安室にあることなどを淡々と語った。 僕はベンチに力なく座って背中を丸め、 洩れ出る声をこらえながら、 勝手に慄えてじっとしていられぬ体を前後に揺するしかなかった。 正常な呼吸でなかったのは認める。 息の仕方さえわからなくなっていた。 脳裏には数々の思い出が渦巻いていた。 ろくでなしの父、 突然斃れた伯父、 母、 そしてついに大親友までも……。
Pは自分こそ僕とともにザ・Bをはじめた張本人だと思っている。 悪いが誤りだ。 バディ・ホリーに倣って駄洒落のグループ名を思いついたのはSで、 フランス風に気どった語尾を修正したのが僕だ。 世界を変えた僕らのグループは故郷リヴァプールのあいつの部屋で、 僕らふたりだけの与太話からはじまったのだ。 ずいぶん未練があったみたいで売り込みの手紙をあいつはフランス風のほうで書き送っていたし、 自分の芸名まで似たような感じにしたことさえあった。 そんなのだせぇよといってやったときの不満げな顔。 一緒に悪事をはたらいたときのくしゃっと笑うそばかす顔。 本気で殴り合ったときの互いの頬と拳の熱い感触。 互いの女について照れながら打ち明けた夜……。 僕がくだらん冗談を書き送ると倍の分量の美しい詩が返ってきたものだ。 正反対なのにそっくりだった。 僕がボケであいつが突っ込み担当。 落ち着きなく飛びまわる僕を諫める係があいつ。 あいつが優等生の高尚な抽象画家なら、 僕は下種な不良のロックンローラー。 海の向こうに別れてからも、 それぞれの世界で成功して両輪のようにやっていくはずだったのだ。
Sは僕の錨だった。 一九六二年四月にそれを喪った。 そして僕は五年後にも、 さらにその後二度までもおなじ過ちをくり返すことになる。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)

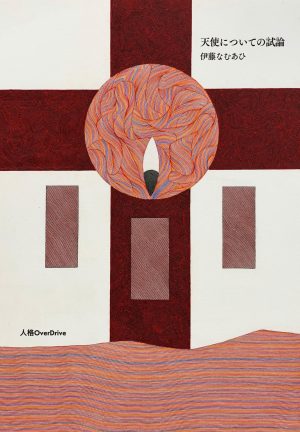








泣いた……って書くとネタバレになるからXでは書きたくなかった。新しい読者に先入観を持たずに読んでほしかった。ぐしゃぐしゃに泣きそうになって、仕事終わったばかりでまだ外にいたので我慢した。家に帰ってから泣く。Sのいた暗い部屋やからっぽの寝床がみえるようだ。JとSの過ごした時間の煌めきも。
杜さんはJの気持ちをすごく理解している。Jがどんなに友の死を悲しんだか。どれほど大切な存在だったか。
この章だけじゃなくここまで読んで、今Jが生きていたらきっとこんなふうでいただろうな、こんなふうに考えただろうな、と感じる。子どもや孫に不器用で、自分の若かりし頃の価値観の誤りを認めていて、戦争の経験なんて自分の大切な人達に経験してほしくないと願って。
うまくまとまらないけど、私は今すごいものを読ませて頂いている。
『Cloud9』“Peppermint Twist(4)”|人格OverDrive
https://ezdog.press/peppermint-twist-4.html