僕らは新しいザ・Bを見に来るようAを挟んでしつこく説得した (当時まだ珍しかったステレオ音響だ——ちなみにドイツはその先進国だった)。 夜になり幕が上がると渋っていたはずのAの姿が最前列にあった。 僕はいつもより張り切って、 配線が伸びきってプラグが抜けるほど舞台狭しと駆けまわってふざけ倒した (PとGには縄跳びを強いることになった)。 相方のPも意を汲んで調子を合わせてくれたし、 普段はおふざけには乗ってこないGまでもが、 珍しく両腕を広げて、 きーん、 と口で効果音を発して曲芸飛行の真似なんかを演じてくれた (僕の持ちネタ同様かつてMに教わったとかで、 本人は気に入っていたようだけど……G、 悪いけどあれ、 あまりおもしろくなかったよ)。 まだ幸せになる覚悟ができていないAの顔つきがだんだん明るくなってきた。 調子づいた僕は、 逆に傷つけてしまう危険を承知で 「やさしく愛して」 を歌った。 親友の真似ならお手の物、 あたかも黒眼鏡をかけているかのように彼女をじっと見つめ、 わざとちょっと調子はずれに。 元ネタを知らないほかの客はそっちのけだ。 案の定Aは泣いたけれど哀しみによる涙ではなかった。 元気を取り戻した彼女は 「九〇九号のひとつあと」 をリクエストしてくれた。 一七のときはじめてPと書いた曲のひとつで、 列車の唄を書こうぜ! みたいなその場のノリで、 紛らわしい別れの言葉にひっかかって厄介払いされた男の話をでっち上げたやつだ。 ばかげた歌詞だと思っていたけれど彼女のお気に召すなら俄然、 名曲に思えてきた。 そればかり何度もくり返して演奏した。 Aは笑い、 ほかの客はわけがわからずびっくりしていた。 仕事が終わるとAを楽屋に招いた。 彼女は現像した作品を渡してくれた。 僕とGは得意満面でみんなに見せびらかした。 Pは嫉妬に荒れ狂った (だったら一緒に来ればよかったのに!)。
この頃の僕らは地元ファンとの文通に熱中していた——少なくとも僕ら三人は。 無口なピートBが手紙で饒舌だったかどうかは知らない。 とりわけ最大の文通相手を喪ったばかりの僕は、 妹みたいな十代の子を相手に長文のおふざけを熱心に書き送っていた。 何せ会議アプリやソーシャルメディアどころか電子メールさえ存在しない時代だ。 親たちや婚約者たちからも大量の手紙が職場気付で届いた。 独語をほとんど解さぬ僕らは母語に飢えていたので、 こうしたやりとりやBEが送ってくれる地元紙は何よりの楽しみだった。 一週間で帰国したBEからは仕入れたばかりの輸入盤も続々と届いた。 毎朝向かいの建物へ赴いて回収してくる権利は宿泊所でいちばん早く起きたやつにあって、 五月九日水曜日にその栄誉を得たのはGだった。 寝ぼけ眼で出て行ったかれは何かに感電したかのような勢いで目を輝かせて戻ってきた。 握りしめた電報にはこう打たれていた——オメデトウ坊ヤタチ EMIヨリ録音ノ要請アリ 新曲練習サレタシ。 数日後には契約の詳細も手紙で届いた。 このお手柄にはさすがのPも満足したろう——渡独前、 新マネージャに反抗するあまり仕事を幾度となくばっくれ、 返金騒ぎを新聞に書かれる事態まで招いて、 僕らの将来を危うくしたかれであってさえも。
遡ること三ヶ月前、 「マイボニー」 と黒革ブロマイド数葉を名刺代わりに上京し、 音盤会社詣をして頭を下げまくったBEは、 EMIを含む幾社にも断られた挙げ句デッカで赤恥を掻かされ、 尻尾を巻いてすごすごと退散、 商談会で知り合ったオックスフォード通りの自称 「世界一の音盤店」 こと 「ご主人様の声 (HMV)」 店長に愚痴った。 聴く耳のあるひとが可能性に賭けてくれさえすれば、 かれらは大スターになれるのに……云々と。 不憫に思った店長は二階の古い設備を貸してくれた。 デッカがお土産にくれたテープ音源がそこで重いラッカー盤に刻まれ、 七八回転のアセテート盤ができあがった。 この音源には僕らの自作曲がいくつか含まれている。 だれも知らない曲を演ったって……と僕らは思っていたけれど、 BEに強く勧められたし、 初対面のMに意気地なし扱いされたのもずっと気にかかっていた。 未出版なのを知った店長がその場で口利きしてくれて、 その建物の最上階にあるEMI系列の音楽出版社へ売り込む運びとなった。 出版に興味を示してくれたベテラン担当者に対し、 BEは本人たちの歌唱にこだわった。 契約に助力してくれたら出版権をお譲りしますとBEは請け合い、 わたしに何ができるか考えてみましょうと担当者は応えた。 そこからコネがつながり、 新人発掘部門の担当者三名のうち、 たまたまひとりだけ休暇に出ていなかったGMに逢うことができた。 豪華な調度で向き合ったふたりは、 慇懃な笑顔と正しい発音の英語で和やかに会談した。 僕らが大好きなお笑いラジオ番組 『おまぬけ劇場』 の音盤を手がけたことで知られるGMは、 冴えない録音に内心で失望し、 聞いたこともない地方都市の青年実業家を田舎者めと見下した。 機会があれば連絡します、 といつもの聞き飽きた決まり文句が発せられ、 儀礼的な挨拶が交わされてBEは失望とともに退室した。 ……そう、 EMIとの縁はそこで一度は切れたはずだったのだ。
見る目がなかったのはデッカだけじゃない。 フィリップス、 パイ、 エンバー、 オリオール……ありとあらゆる大会社がBEの売り込みを無視し、 あるいは鼻で嗤って門前払いした。 代わりにレスラーとか中年主婦とか十歳の少年とかいった、 企画ものの泡沫タレントと契約した。 今日ではそれらの中古盤に一銭の価値もない。 大学出の高給取りたちがなぜ揃いも揃ってそんな愚かな真似をしたのか。 僕らがリヴァプール人だからだ。 GMがそうだったように僕らの港町が英国のどこにあるかさえ連中は知らなかった。 話を聞いてもらえてもせいぜいがグループの改名を恩着せがましく忠告されるばかり。 BEの一族内での立場は危うくなる一方。 家族は経費が出て行くばかりの酔狂をやめさせようとしていた。 なのに僕らの才能と成功を確信するBEは頑固に聞き入れなかった。 「洞窟」 の昼公演のあと連れ立って昼食をとりながらBEは 「お父つぁん」 に心底悔しげに苦々しくこぼした。 何がいけないんだ、 なぜ音盤会社の連中は反応しないんだ……。 この街まで来て女の子たちの大騒ぎを見てくれりゃ、 あいつらの価値がすぐわかるのになぁと 「お父つぁん」 は慰めた。 DJ兼司会者もまた内心では地方と中央の温度差に憤懣やるかたなかった。
ロンドンのユーストン駅から四時間以上かけて帰ってくるBEを、 僕とPはいつもライム通り駅を出て坂を下りたところにある薄汚い喫茶店で待ったものだ。 哀しげな顔で入ってくるBEにまたかよと落胆する日々。 ときにはGやMも加わった。 都会の大会社のお偉方は、 地方在住者の都合など一顧だにしない。 距離も時間も金もお構いなし、 呼べばすぐ来るのが当然と心得ていて、 碌に話も聞かず追い返すのになんの躊躇もない。 秘書が予定表を調べてこの五分間なら空いてますとかほざき、 こちらはその五分間に望みをつなぐ。 さんざん待たされ会合が六時過ぎまでずれこんだところで、 連中は一杯飲んで家族のもとへ帰るだけだが、 BEは八時四五分の最終列車に乗り、 クルーで乗り換えて帰り着くのは深夜一時四五分。 そんなとき僕らはデューク通りまで戻り、 終夜営業の店でカレーを喰いながら報告を聞く。 資産家一族の出で、 プライドの高い癇癪持ちのBEが、 鼻持ちならない都会の連中にぺこぺこ頭を下げ、 揉み手でお世辞をいって機嫌をとり、 それで何ひとつ成果がない。 どれだけ傷ついているか一目瞭然だったのに、 若くて愚かだった僕は、 おれらばかり働かせてあんたは何もしていない、 と残酷に責めなじった。 BEは返す言葉もなく意気消沈、 僕らの顔さえまともに見られない。 Gは俯きMは視線を逸らし、 新マネージャを認めていなかったPでさえ、 おいどうすんだよこの空気という目で僕を見た。 さすがに気が咎めた僕は手をぱんと打ち鳴らした。 よぉっし、 じゃ次はエンバシーだ! みんなどっと笑って緊張が解けた。 大手チェーン店ウールワースで投げ売りされている紛い物で、 最新流行曲をだれも知らない歌手やグループが吹き込んだ安音盤のことだ。 この手の商売はどこの国にもあったらしくて、 米国のピックウィックなる会社でサーフィンソングなんかを粗製濫造していた男の話を聞いたことがある。 そいつは風車ツイストならぬ駝鳥音頭なる新しい踊りを流行らせようとして見事に滑ったりしたそうだ。
僕もPも、 それに疲れ果てたBEも万策尽きてお手上げ、 なすすべなく脱力して笑うしかなかった。 Gだけが楽観的だった——それにMだ。 いつかきっといいことがあるよとGは自信満々に宣言し、 ねっ? と隣に同意を求める。 するとMは、 食欲のないBEが残した料理を頬ばりながら (まったく呆れた喰い意地だ) あの間の抜けた笑いで肯くのだ。 あいつときたら、 いつだって万事ご存じといった顔をしやがる。 そのお得意の千里眼が的中したのか、 Gとふたりして僕とPに請け合った 「いつか」 がこの日ついに訪れたというわけだ。 一度はすっかり立ち消えになり、 BE当人でさえ諦めて忘れかけていた話が、 三ヶ月も経ってから急にぶり返したのはなぜか。 謎といえば八年後に喧嘩別れするまであれだけしつこくつきまとったMが、 あの時期だけ姿を見せなかったのも不自然だ。 先日Pと逢ったとき冗談でそのふたつを結びつけてみせたら、 懐疑主義者のあいつが笑うどころか、 あり得る、 と苦々しく肯いた。 なんにせよ気味の悪いやつだったよ……と。 しかし未来がどうとかいうMのご託が本当なら、 時間と距離はあいつにはなんの意味もないはずで、 これはこれで筋の通らぬ説明に思える。 はっきりしているのは僕らが社内政治の道具にされたということだ。 GMはかれのいう 「お子様向けビートグループ」 の仕事なんか受けたくなかったし、 田舎の青年が持ち込んだ音像の不鮮明なアセテート盤のことなんか忘れていた。 でも秘書との不倫がバレて際どい立場にいて、 養育費や別居費用も稼がねばならず、 いくらヒット商品を生み出しても見返りがないのに不満を抱き、 賃上げ交渉をするも不首尾に終わっていた。 そこへ演奏できるタレント自体ではなくむしろ出版権の獲得のために、 煩雑で厄介な手続を押しつけられたのだ。 銃を突きつけられて脅されてでもいるかのような電話の声色にGMは不審を感じたものの、 上司の命令には逆らえなかった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)









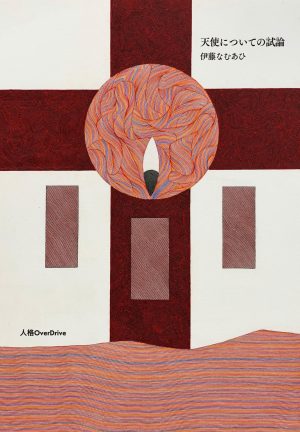
@ezdog AKよかったなぁ……と思いつつ、アラレちゃんと化したGには笑ってしまった。Gもいいやつだよなぁ。BEと食卓を囲むシーンもいい。
当時のレコード会社が地方出身者を全然相手にしていない様子には時代を感じたけど、こういう都会の人間の傲慢さってきっと今もありそうだ。めげなかったBEもBの奴らもたいしたものだなぁ。
そして密かにMが大活躍している!? なんだかどんどん工作員らしい仕事をしているような。この先のMがますます楽しみ!