僕は確かに虫のいい夢ばかり見て、 犯罪者の妻さながらの苦労をCにさせている現実から眼を背けていた。 でも波風立てるのを優柔不断に避けつづければどうなるか、 まるで理解しなかったわけじゃない。 それにロンドンでの仕事が増えて、 いちいち地元に帰るのが億劫になってもいた。 遅い新婚旅行を済ませた翌月くらいにCの母親が帰国することになった。 それを知った伯母はある朝、 自室から降りてくるなりCに厭味をいった。 Cの母親を玄関から一歩たりとも入らせまいと追い返す悪夢を見たという。 おっかないったらないねぇ、 考えてもみてごらん、 このわたしがそんな夢を見るなんて! Cのような女を育てたまともな親とあの伯母とは、 初顔合わせから互いに声を荒げたほどの仲だった。 寛容で心優しいCも、 実母まで侮辱されてはさすがに我慢の限界だった。 彼女が息子を連れてホイレイクの実家に戻ることになったのを僕は電話で報された。 貸した一家が退去するまでのひと月は近所の屋敷の一室を借り、 僕が帰る月末までには実家に落ち着けるだろうとの話だった。 僕はへぇーそう、 まぁしょうがないねと他人事だったけれど、 Cとその母親にしてみれば試練の一ヶ月だった。 ほかの部屋の住人は気難しい老人ばかりで、 ギャン泣きする息子を日中は乳母車に乗せて何時間も表を歩きまわり、 夜はあの手この手でどうにか静かにさせようと努めるしかなかった。 にわかに国中で熱狂される有名人となった夫は、 高級ホテルで鮭の燻製やらキャビアやら、 よりどりみどりの女やらをつまみ喰いしているというのに、 片や妻とその母親は、 週五ポンドの狭くみすぼらしい部屋で、 泣き止まぬ赤子の世話に疲労困憊、 やつれ果てている。 ようやく実家に移ると息子は安堵したのかぱたりと泣き止んだ。
ホイレイクでは近隣住民のだれもが事情を知っていて、 余計な詮索をせずに護ろうとしてくれたけれど、 Cが安心して乳母車を押して歩けたのはせいぜい数週間。 僕が公演に出ているあいだに、 噂を聞きつけた記者たちが近所を嗅ぎまわりはじめた。 ハイエナのような作り笑いでにじり寄る輩に問い質されるたびに、 嘘をつくのが苦手なCは懸命にしらばくれた。 理不尽な境遇に耐えるのが夫の仕事のためだと心から信じていた。 執拗に尾行されて近くの店へ飛び込み、 親切に匿ってもらうこともしょっちゅうだった。 そんな生活はある日突然、 乳母車を押して家を出るなりあっさり終わった。 群がって待ち構えていた連中にフラッシュを焚かれ、 新聞の一面に写真が大きく掲載されたのだ。 僕ら夫婦はむしろ安堵した。 もう秘密でも何でもない、 世間に対してなんら後ろめたくないはずのことで二度と逃げ隠れしなくて済む……。 みずからの立場を投影したBEの不安はまったくの杞憂だった。 多くのファンはCを尊重し、 長男を神に祝福された特別な子であるかのように可愛がって、 ごく一部の狂信的な輩から護ってくれた。 何より妻子の存在ごときでファンの情熱は損なわれなかった。 むしろ危険な魅力が増したと自負している (僕の性的冒険の数々を知るMは、 そういうとこだよと批判がましく溜息をついた)。
僕ら夫婦は音盤のジャケットを担当した写真家の口利きで、 クロムウェル通りを入ったところにある四階建てマンションのメゾネットになった最上階、 寝室が三つあるフラットを週一五ポンドで借りた。 すぐに致命的な欠陥に気づいた。 昇降機がなかったのだ。 たまにしか帰れぬ僕としては、 浮世の喧騒を隔てるにはそのくらいがよかろう、 眺めもいいし……くらいの安直な考えだったけれど、 Cにしてみればまず買い物袋と乳母車を置いて、 長男を抱えて狭くて暗い階段をのぼり、 踊り場で折り返してまたのぼりを三度くりかえし、 安全な場所にとりあえず赤子を寝かせてから、 放置したものを取りに戻らねばならぬことを意味した。 僕が放蕩のかぎりを尽くして肥え太る一方、 Cは運動選手なみに引き締まった。 下階の写真家夫婦とはこのマンションを出てからも家族ぐるみで一年ほど親しく付き合った。 僕はとりわけ妻のほうと親しく付き合った。 おかげでほどなくかれらは離婚した。
Mのお薦め本を大量に読まされるようになったのもこの頃だ。 読み終えるたびに感想を求められ、 次はこれと押しつけられる。 『ミス・ブランディッシの蘭』 もその一冊で、 そこから捏造したハドリーなる偽名の表札は、 わずか半月しか通用しなかった。 ある朝Cが窓を開けると、 黒いアイラインをひいて髪を高く結い上げた十代の女の子たちが歩道に群がっていた。 その日を境に彼女らはずっと居座るようになり、 昼も夜もいつもそこにいるのが当然の風景になった。 帰宅するたびにわらわらと集まってきては、 声をかけてきたり触ったり、 署名や髪のひと房をねだったりする彼女らに、 Mはいい顔をしなかった。 僕ら一家の安全を気にかけるなら追い払うべきだというのだ。 でも僕にその発想はなかった。 そのマンションに住めるのも彼女らが音盤や切符に金を払ってくれたからだ。 家の近所だろうが公演で訪れた異国の街だろうが、 いつどこであろうと声をかけられたら、 どんなに疲れていても必ず足を止め、 愛想よく握手や会話や署名に応じるのを忘れなかった。 その場に居合わせるたびにMは説教がましい態度をした。 うるさいなぁ、 そんなの撃たれてから考えるよと僕は応じた。 Mの葬儀で同窓会みたいに当時の仲間が集まったとき、 だれもが懸命に僕を説得してこの習慣をやめさせようとしたし、 コロナ禍では別の意味で命の危険を感じたけれど、 僕は断固としてファンの前で立ち止まりつづけている。 おかげで僕の署名はほかの三人に較べて市場価値がとても低い。
Mのことを書いていて思いだした。 僕らの音楽以外何ひとつ信じちゃいないように見えたあいつが、 実は信心深いのではと思わされたのもこの頃だ。 Cが長男を乳母車に乗せて表へ出ると、 赤ちゃんをひと目見せてと少女たちが群がるのが常だった。 ああなんて可愛い子なの、 ちょっと触ってもいい、 抱っこしてもいい? Jが旦那様だなんて幸運ね、 どこの美容院に行ってるの、 お洋服はどこで買うの? Cは津波のように押し寄せる幼い少女たちに圧倒され、 叫びたくなるほど怯えながらも、 夢を壊してはならぬとの一心で、 あくまで優雅で冷静沈着な、 理想の大人像を演じつづけた。 この子たちがいつか憧れた大人になれたら、 そのためのお手本になれたらと祈りながら……そう、 彼女は本来、 僕とかかりあわなければ教師になっていたはずなのだ。 その日はいつもより人数が多かった。 赦しを乞うかのように跪いて手をさしのべる少女たちの海をかき分けて、 じりじりと乳母車を押していたそのとき、 Cは通りの向こうから茫然と見つめる日本人に気づいた。 呼ばわっても声は届かず、 人垣に遮られて近づけなかったけれど、 Mは確かに涙を流していたとCは僕に証言した (そしてちょっと気味悪がっていた)。 あの日は天気が悪かったけれど雲間から光が射しちゃいなかったかい、 と冗談のつもりで尋ねると彼女はどうしてわかったのと驚いていた。 母親と幼子、 祝福を求めて群がる少女たち。 その光景にあいつが何を重ねたのか僕にはわかるような気がする。 生き延びるために戦場でやったことはあの男に深い傷を残したのだ。
ずっとのちにMが語ったところによれば未来世界を統治する 「人間の意思決定に影響を与えたり取って代わったりするための自動システム」 とやらは、 さまざまな企業が争って最後に残った寡占的なシステムなのだそうだ。 そのAIにも複数の異なる版があり、 互いに上書き更新や強制終了をされまいと争っているという。 人類もまた同様に、 ほかの類人猿を強姦したり根絶やしにしたりしてきた種族の末裔なのであって、 なるべく多くの他人を強制終了させたり、 自らの遺伝子で上書きしたりしたいという本能的な欲求をもっている。 だから他人を迂闊に信じるな、 とMは疑り深い割には騙されてばかりの僕に、 ことあるごとに説教した。 特に 「大きく美しい」 やつには気をつけろ……と。 一九六四年の時点ではまだそこまでは話してくれなかったけれど、 偏執的なまでに僕の生命を案じるその態度には、 戦場での経験がかかわっているんだろうなという気はした。 親世代の男たちから、 おまえらのために闘ったんだぞと恩着せがましく説教されてもピンとこず、 反感と侮蔑の念しか湧かなかったけれど、 ハンブルクで知り合い、 ともに悪ふざけを重ねた同世代 (と当時は思っていた) の言葉には、 耳を貸さぬまでも何かしら揺さぶられるものがあった。
大げさな警告を笑えなくなったのはあいつの宗教的体験から数日後だった。 家出少女たちが逮捕されずにどこまで法を犯せるか競い合うようになったのだ。 連中は寝袋とサーモス印の魔法瓶を持参して、 建物の玄関をだれかが出入りするまで一日粘り、 連れ立ってまんまと入り込んでは、 玄関ホールや階段に堂々と寝泊まりするようになった。 Cは買い物に出るたびに横たわる人体を跨がねばならなくなった (この話を僕に聞かされたMは顔をしかめた——きっとかれが跨いだものはどれも生きていなかったのだろう)。 いくら心優しい彼女といえど便所を貸したことはないはずなので、 不法侵入者らが生理的欲求をどうしていたのか僕には想像もつかない。 家出少女たちは麻薬をやる僕とおなじ目つきで赤子の世話を手伝うことを口々に申し出た。 やっていることや身なりを見るに、 いくら寛大なCでも息子の命を預ける気にはならなかった。 不法侵入者らはどこでそのやり方を憶えたのか、 噛んでいたガムを鍵穴に押し込み、 鍵を挿せずに困惑する僕にガムのようにひっついて、 鼻声で署名をせがんだ (さすがの僕も狩り場と自宅、 捌け口とお客さんは区別していた)。 やがて深夜に部屋の扉がしつこく叩かれるようになった。 そんなときにかぎって僕は公演に出ていて不在で、 Cは耳を塞いで暗闇に横たわりながら今度こそ母子ともども殺されると確信した。
Cの忍耐がついに切れたのは近所の火事だった。 パトカーと消防車が通りすぎて炎が夜空を舐め、 わずか三百ヤード先の、 ヒースロー空港行き長距離バスターミナルが松明のように燃えていた。 そのときも当然のように僕はいなかった。 Cは長男を抱き締めて窓際に立ち、 朱に染まる夜空をなすすべもなく見つめた。 風向きのおかげで火の粉がこちらまで飛んでくる。 階下の写真家夫妻が心配して上がってきて、 火はここまで届かないよと慰めてくれたがCは安心できなかった。 幸い消防士の活躍のおかげで無事に鎮火したものの、 もうたくさんだと彼女は思った。 その頃には通り向かいの学生宿舎のバルコニーから、 昼夜お構いなしに手を振られ名前を呼ばれて、 カーテンさえ開けられなくなっていたし、 渦がおまえたちを見ているぞ、 などと性別不明の声で脅すわけのわからぬ悪戯電話もつづいていた。 人の心を持ち合わせない僕も、 火事の話を電話で報されてさすがに同意した。 ただ自宅へ出入りするためだけの絶え間ない闘いに、 僕自身ほとほとうんざりしていた。 屈強な運転手に力ずくで道を空けてもらっても、 連中は屍骸に群がる蠅ごとく次から次へと我先に突進してきて、 僕の帽子やマフラーや持ち物を追い剥ぎよろしく強奪しては、 戦利品を奪い合って僕の周囲で噛みつき引っ掻きの格闘をはじめる。 元はまともな親御さんに育てられたいい子たちだったろうに、 何かに取り憑かれたかのように完全に正気を喪っていた。 連中に入り込まれない安全で静かな場所が必要だ! とかなんとか僕はCに演説をぶった。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)








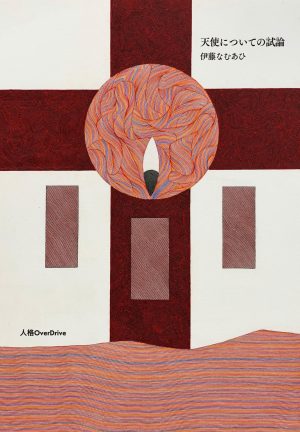

@ezdog 伯母の意地悪さったらもう! Cのことがバレて読んでいる私もホッとした……と思ったら、ファンの女子達が恐ろしすぎる……。あんまりなJにチクリと物申してくれるMにすっきりする。
でもJがファンを大切にする姿勢は偉い。彼が本当にまだ生きていたら、きっと今もそうしていただろう。そんなふうに夢想させてくれる。
そしてMの涙が印象深い。母子と女子達の群れから少し離れたところに佇むM、この光景が美しい聖画のように思える。