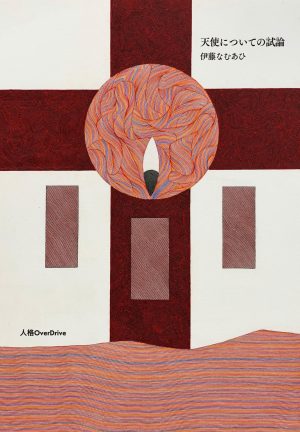口やかましい未来人に指摘されるまでもなく、 現代の公衆道徳に照らせば当時の僕は完全にアウトで、 いまだってキャンセルカルチャーの標的にされないのが不思議なくらいだけれど (若かりし頃の悪行の数々を婆さんたちに訴えられる夢にうなされる夜がある)、 未成年に飲酒を強要はしてもハンブルクの娼婦や踊り子にしたようなことをファンの子らに仕掛けたことは一度もない。 Mの主張によればひとは生まれ育った環境を再現しがちだそうで、 それを話してくれたときのあいつは、 戦場で人格形成したらひと殺しで生計を立てるしかないんだ、 とつづけて自分でウヒッと受けていたから信憑性はいまひとつにせよ、 もしきみがその説を信ずるならば、 実の妹たちを笑わせるのが大好きだった僕のいうことにも多少は耳を傾けてもらえるだろうし、 僕がやらないことを慎重派のPや若いGがするわけがなかったのもわかってくれるだろう。 僕が年下に手を出したのは秘書のメイPが最初で最後で、 それだって妻に仕向けられなければそんなことにはならなかった。 はじまりこそ妻のパワハラでも僕とメイPとは合意の関係だったし、 上出来の作品を生み出した生活すべてを搾取と決めつけられては、 彼女にだって失礼だと思う。 巻き添えを喰らった息子には気の毒だけれど、 モナBに対する僕らの仕打ちもそういう話として聞いてもらっていい。 独立独歩だったピートBの行状については知りようもないけれど、 少なくとも地元リヴァプールにおいては、 不純なことは何もなかったと思う。 なぜなら僕らはこのすぐあと、 「お父つぁん」 が調達した踊り子 (ハンブルクと違って健全な踊りだ) の一員と我らがドラマーが恋に落ちる、 魔法のような瞬間を目撃することになるからだ。
六五〇人のファンの前で、 僕らはモータウンやチェスそれにアトランティックの人気曲を立てつづけに演奏し、 ひたすら陽気に盛り上げた。 この夜の演し物は盛りだくさんだった。 僕らもファンも 「お父つぁん」 に感謝の気持ちを表明したかった。 そこで僕らはかれに一曲歌わせようとしたんだが丁重に辞退され、 代わりに経営者がエルヴィスの名曲 「好きにならずにいられない」 を披露した。 思いのほか美声で温かい喝采に迎えられたのに気をよくしたかれは、 調子に乗ってもう一曲 「夜はやさし」 を熱唱した。 僕らはこの曲を知らなかったので適当に合わせることしかできなかった。 それでも観客はみんな笑顔だった。 この男がいなければ僕らとファンのみんなが 「洞窟」 で楽しい時間を過ごすことはなかったわけだからね。 僕の悪戯心に感染したか、 Pの弟は舞台をうっとり見つめるボビーBに、 兄貴が楽屋へ戻ったら接吻してみろとしきりにけしかけた。 普段の彼女ならけっしてそんな愚行には及ばぬのだが、 生まれてはじめての酒が判断を狂わせた。 彼女は一世一代の蛮勇をふりしぼった。 Pの首っ玉に飛びついて両腕を巻きつけ、 頬をすり寄せたのだ。 詰めかけた女の子たちは目を剝いて叫び、 彼女の髪を引きちぎろうとした。 この子に何をしたんだという目でPが咎めるように僕を見つめるのと、 ボビーBが嘔吐するのはほぼ同時だった。
僕に近づく輩への嫉妬深さにかけては、 SやMや妻ばかりかBEに対してまでとことん厭な奴になれたPなのに、 さすがあの父親に育てられただけあって、 護るべき相手への接し方は見上げたものだといつも思う。 年老いた僕がふたりの息子や義理の娘と、 うまくいっていないとまではいわずとも微妙な間柄であるのに対して、 かれが血縁のあるなしを問わず、 目尻を下げて子どもや孫とベタベタな様子をソーシャルメディアで開陳する様子を見るにつけ、 人生最後にはこういうとこで差がつくよな、 と思わずにはいられない。 PはボビーBの上着と鞄を取ってきて、 便器に頭を突っ込んで泣いている彼女を見に行き、 あれこれと世話を焼いた。 きっと彼女は叶わぬ恋を諦めると同時に、 Pへの敬意がいや増したのではないか。 ばつの悪い思いで便所の戸口から眺める僕を、 Mはニヤニヤしながら横目で見た。 なんだよと肘で小突いてやると、 えっへっへとあいつは笑った。 Pはハンブルク時代から愛用してきた革ジャンを惜しげもなく丸めて屑籠へ棄てた。 僕とGもそうした。 古い僕らとはお別れだ。 ピートBが革ジャンを棄てるところは見なかった。 たぶん大切にとっておいたのだろう。
そしてついに 「お父つぁん」 が第二部の開幕を高らかに宣言する——ザ・B、 新しい背広で登場です! 舞台に出てきた僕らを地下にひしめく六五〇人の絶叫が迎えた。 一見すると無地のようだが細かな織柄の濃紺モヘア生地、 細い細襟シングル三つボタン。 上衣は寸胴な米国風で丈は短め、 くるみボタン、 イタリア風に中綿の少ない緩やかな肩。 パンツは屈伸すれば破れそうなほど細い。 シャツの短い丸襟はピンで留められ、 細い黒ネクタイの結び目を小粋に持ち上げてある。 そして足許はSとおなじフラメンコ練習靴、 舞台にいないあいつの独創性がともにあるって寸法だ。 仕立屋で試着したPがまるでミラクルズみたいだ! と歓喜の声をあげたのを思いだす。 ふん、 本場米国なんて目じゃないぜ。 今夜はおれらが奇跡を起こす側だ。 そして僕らは叶わぬ恋心を果敢に表明したボビーBに負けじと、 ついに観客の前で拙い自作曲を披露したのだ。 P作による 「風車ツイスト」 はいま振り返ればお世辞にも名曲とはいえず、 EMIでの収録のために準備まではしたものの結局お蔵入りにして、 二度と人前で披露しなかった。 Mは歌詞に苦笑いしていたし、 NAなんかミドルエイトで突然ワルツになるのが糞だといって毛嫌いしていた。 あの場にいた婆さん爺さん (まだ死んでいなければ) の記憶を別にすれば、 どんな海賊版にも収録されていないはず。 それはこんな唄だった。
いますぐ夜も昼も
(Pのかけ声——二、 三!)
腰や肩を揺らして前へ後ろへ
さあこんなふうに……
みんな風車ツイストだぜ!
……うん、 きみのいいたいことはわかる。 要はやがて 「昨日」 や 「なすがままに」 を書くことになる偉大な天才にもそんな時代があったってことだ。 幸いにも善良な観客は、 さすが本場米国の最新流行曲はひと味違うな、 と騙されてくれたようだ。 お粗末な曲はともかく背広のほうは賛否両論で、 黒革上下の僕らに恋していたファンのなかには、 まるで僕らがロンドンの大音盤会社に魂を売りでもしたかのように失望した子もいたようだけれど、 だれひとり席を蹴って帰ったりはしなかった。 舞台上の僕らは押し寄せる熱狂を感じ、 石壁や機材は観客の汗で結露するほどだった。
当時の僕らが好んで取り上げた楽曲に 「ツイスト&シャウト」 というのがあるけれど、 ツイストというのは七〇年代のハッスルや八〇年代後半のランバダのような流行の踊りだった。 発祥の地はマンハッタン四五番街にあった 「薄荷ラウンジ」 なるゲイ向けのディスコで、 一八〇人も入れないような小さな箱でありながら、 女優や作家といった有名人が通うヒップな場所として知られていた。 サム・クックが 「ツイストで踊りあかそう」 で 「とってもゲイ」 と歌ったのはこの店のことだ。 惨めなはずの叔父さんがのっぽの禿男と楽しむ意味と同様に、 二年後の初渡米で実際に訪れるまで、 英国の地方在住の僕らにそんな背景などあずかり知らぬことで、 この夜ピートBが、 汗で前髪を額に張りつかせたPにドラムを代わってもらって熱唱した 「薄荷ツイスト」 もまた、 僕らにはゲイ・アンセムでもなんでもなく、 NEMSで買い漁ったか 「お父っつぁん」 から借りパクしたかした音盤の一枚にすぎなかった。 無口なイケメンで鳴らしたピートBには、 この夜この瞬間がまさしく人生の絶頂だった。 僕らから見てもあのときのかれはじつに色男だったから、 背筋を電撃に打たれた女の子がいたとしても、 そしてその子とピートBの視線が熱く絡み合ったとしても、 そしてかれとのあいだに隙間風が吹いていた僕らでさえもが、 ちょうど 「やさしく愛して」 を歌うSとその婚約者にしたのと同様に、 つい引き立て役に徹してやったとしても不思議ではない。 ハンブルクの悲恋カップルとも、 のちにできちゃった婚する僕とCとも異なり、 見つめ合って踊るふたりはやがて生涯を共にすることになる。
すばらしい夜だった。 僕らは観客の親御さんたちが心配せぬよう、 最終バスを逃すなよと念を押し、 声援を鎮めてからお別れの言葉を伝えた。 ハンブルクで七週間演奏してくるあいだ忘れないでくれよ、 手紙をくれると嬉しいな……。 そして公演先の住所を教えた。 六五〇人のファンは接吻や抱擁や署名を求めて舞台に殺到した。 押し寄せるひとりひとりに言葉をかけながら、 僕らは今度こそ何かが変わりはじめていると実感した。 三日後の日曜の午後、 お眼鏡に適うようなファンふたりを厳選してメンディップスへ連れて行ったとき、 伯母はこの上なく上機嫌で、 ふたりがお茶とお喋りを楽しんで帰ったあと、 あんたのファンはほかのメンバーの軽薄なファンとは違って知的で活き活きとしているね、 とかなんとか感想をのたまった。 ものすごくまわりくどい表現だけれど、 伯母なりに僕のやっている仕事をついに認めてくれたのだ。 ファンといえばこの頃から常軌を逸した連中が僕らの実家のまわりをうろつき、 しつこく玄関扉を叩いたり、 どこで番号を知ったのか電話をかけてきたりして、 僕らの親たちを煩わせるようになる。 伯母などは誇りにしていたメンディップスを数年後に惜しげもなく売り払って引っ越したほどだ。
数日後にGは風疹にかかってモナBの店での最終公演を欠勤し、 ひと足遅れて渡独することになった。 僕とPはヘイマンズグリーン八番地にあるモナBの店で楽器を回収し、 ファンに口紅で落書きされたNAのヴァンに積み込んで、 リングウェイ空港へ向かった。 最初の渡独が船で三八時間、 二度目が列車と船で三六時間かかったことを思えば、 午後にはハンブルクに到着する文明の利器はまさしく驚異だった。 おまけに用意された宿泊部屋は湯の出るバスタブとシャワーつき。 便所裏の掃除用具入れからはえらい出世だ。 どういうわけかSと連絡がつかず空港での再会は叶わなかった。 募る話を一刻も早く語り合いたかったけれど、 髪を刈り込んで派手な背広と装飾具を身につけた雇用主と、 強面の用心棒たちに囲まれて酒とステーキをふるまわれては断れなかった。 僕は何度も席を外して電話をかけに行った。 きっと不安そうな顔をしていたのだろう、 PとGが僕を見てどうしたと声をかけてきた。 いや大したことじゃないと僕は応えた。 Aの屋敷につながらないんだよ、 ずっと呼び出し中でさ……。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)