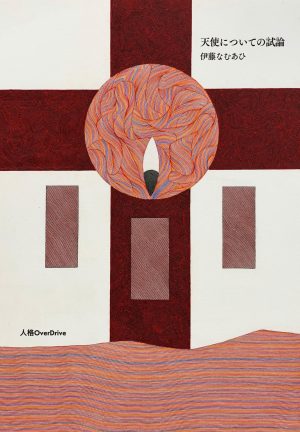前年末に地元での成功のきっかけになったリザーランド市民講堂で、 ちょっとした余興が地獄のような惨事を招いたのはその五日後だ。 Pが僕ら四人の名前を刺繍した赤サテンのハートを上着につけ、 プレスリーの映画主題歌 「さらばふるさと」 を唄い、 しかるのちPの接吻とこのハートが籤引きの景品になるという趣向。 たわいない演出だと思うだろう? 演者である僕らも運営側もみんなそう思っていた。 十代の持て余された体力を甘く見てたんだ、 当選者が挙手するまでは。 あたかもそれが合図だったかのように女の子たちが絶叫して舞台へ殺到した。 辛辣なタフガイで知られるこの僕が床に押し倒され、 硬い踵でどかどかと踏みつけられて、 仲間三人も揉みくちゃにされ身動きできなくなった。 『ブルックリン最終出口』 のトゥララの末路もかくやという騒ぎで、 店の用心棒ですらなすすべもなく、 ハンブルクで元ナチの犯罪者らや喧嘩っ早い水兵らに因縁をつけられたときでさえ、 僕らのだれひとりここまでの恐怖は味わわなかった。 Mが体当たり同然に突進してきたのはそのときだ。 むちゃくちゃな勢いで体重一五九ポンドの僕を引っぱり上げ——左手で女の子たちを押しのけていたから、 片手でだ——危うく身ぐるみ剥がれる寸前だったPと、 ファンの女の子たちを殴るわけにもいかず抱き合って慄えるしかなかったGとピートBとを救い出した。
この事件はいま思えばのちの常軌を逸した騒ぎの予兆めいたもので、 演奏を再開した僕らの目に観客はもうそれまでのようには見えなかった。 近視の僕にしてみれば翌日には薄ぼんやりとした印象しか残らず、 さして気にせずにいられたものの、 ひとりの女なら軽くぶちのめせる成人男性の僕らを、 絶叫し殺到する少女たちであれば好きなように慰みものにできるという事実は、 ハンブルクの物置で僕らに見守られて童貞を卒業したばかりのGにしてみれば、 かなりの恐怖体験として記憶に刻まれたようで、 ザ・Bがやがて公演をきらって録音技術に傾倒する遠因となる。 腕を脱臼しかけたことに僕があとで文句をいったら、 まぁ助かったんだからいいじゃないの、 とMはあの間抜け面で笑いやがった。 未来から訪れた工作員の片鱗をかれが見せたのはこのときがはじめてで、 この時点であの男はまだ、 ひょこひょことした頼りない歩き方やズレた言動から、 SやGのような貧相な体つきに見えていたけれど、 その印象は誤りだったと僕はのちに知ることになる。 あの見せかけは 「前世」 が実際にそんな男だった名残かもしれないし、 あるいは単に僕らを欺く芝居だったのかもしれない。
ザ・Bがいかに快進撃であろうと伯母とは相変わらず衝突ばかりだった。 真夜中に帰宅して下宿の学生らの安眠を妨げ、 午すぎに朝食をねだる毎日では、 頑固でお堅い彼女でなくたって堪忍袋の緒が切れていたろう。 ときにはMまで水を飲ませてくれといって僕の部屋へ上がり込み、 床で毛布にくるまって昼まで鼾をかいた挙げ句、 あなたがついていながらなんですか、 と伯母に叱られてしょげていたりした。 かれの正体を知ったいま思い返すと、 平然と大勢を殺してきたであろう残忍な兵士が……と噴き出しそうになる。 これまでにも書いてきたように、 はじめから親に応援されていたのはGとピートBくらいで、 Pなんかまっとうな就職よりも悪友の僕を選んだことで、 大事な父親を裏切ったかのような後ろめたさを感じていたようだ。 その父親は僕の伯母とちがって、 僕らの人気を渋々ながら受け入れざるを得なかったらしく、 辞めろとも堅気の仕事に戻れともいわなくなり、 押し寄せる観客を懸命に掻き分けて 「洞窟」 の楽屋へ近づき、 昼休みに買った肉をPに押しつけて、 帰ったらオーブンの目盛りを四五〇に合わせろとかなんとか、 家の用事をいいつけるだけになっていた。 ファンや仲間の前で恥をかかせんなよとはPもいえない様子だったし、 僕らとしても独りでPとその弟を育てたアマチュア音楽家を、 口には出さぬまでも尊敬していたから、 多少冷やかしはしても心からばかにする気にはなれなかった。 そして僕の見たところ、 たぶんPがいまだ己を恥じていたこの時点で、 すでに当の父親は息子を誇りに思いはじめていたのだ。
たしかカサノバ倶楽部やリザーランド市民講堂にも掛け持ちで出演した日だった、 「洞窟」 の客席にAを認めたのを憶えている。 舞台上の恋人をうっとりと見つめるAを、 大きなベースギターを抱えたSが見つめ返す……じつに絵になる光景だ。 あいつの演奏はいつも通り冴えなかったけれど、 このときばかりは恋路を引き立てる伴奏役に僕らは進んで甘んじた。 虐め倒していたとはいえ大切な仲間だし、 Aのことも僕らみんな憧れていたからね。 ふたりには絶対に幸福になってほしかった、 いがみ合っていたPでさえあんな結末は望まなかった。 空爆の経験からすべてのドイツ人を憎まざるを得なくなったSの母と、 いかにもアーリア人風の容貌を持ち、 親世代の罪を理解していながらどうにもできないAとは、 当然ながらうまくいかなかった。 仲裁してくれそうな父親は海軍の二等機関士でいつも家を空けていた。 ひたすら反抗ばかりしていた僕とちがって親孝行のSは、 母と婚約者の板挟みで、 おまけに末の妹まで嫉妬するので実家に居づらくなり、 この頃ではすっかり影が薄くなったマネージャの家に、 Aを連れて転がり込むはめになった。 伯母と険悪だったCとAはおかげで話が合ったようだ。 二度目のハンブルク滞在中、 CがPの彼女とともに遊びにきたとき、 さすがに店の屋根裏部屋でむさくるしい男たちと雑魚寝ってわけにもいかないので、 屋敷に泊めてもらったり、 Aの運転でバルト海沿岸の避暑地にある別荘にダブルデートに出かけたりしたことがある。 黒ずくめの寝室や砂浜で、 女たちが互いの男をどんな風に惚気たり腐したりしていたのか僕は知らない。
ふたりは襟なしや黒革のお揃い上下で、 芋を揚げる匂いの漂う市場の雑踏やリヴァプール美大の近所やマージー川流域や煤けた下町をそぞろ歩き、 ペアルックなんて概念には三〇年早い地元民の視線を集めた。 汚れた顔をした子どもたちの一団が笑い声をあげて路地から飛び出してきた。 自転車のゴムチューブを転がして遊ぶ悪童どもをAは屈んで撮影し、 立ち上がって婚約者のほうを振り向いた。 その笑顔が凍りついた。 Sは青ざめたものすごい形相で、 きみたちハンブルクでも逢わなかったかい、 ほら憶えているだろうと執拗に尋ねつづけた。 親が近くにいたらまちがいなく通報されていたろう。 子どもたちは怖がって逃げていったそうだ。 その翌々日にSから打ち明けられた話をAが僕に教えてくれたのは六〇年後、 彼女が亡くなる数年前だ。 生涯の恋人が狂っていたのが怖ろしく、 話せばその事実を認めるかのようで、 たとえ相手が僕や実の母親であっても告げる勇気がなかったのだと、 会議アプリ越しの彼女はいまだ狼狽するかのごとく心細げに弁解した。
Mは僕とタメを張るほどの酒好きで、 僕らとさんざん飲んで別れたあとも、 よくひとりで飲み歩いていた。 そのことを知ったSは、 普段は公演を終えるとすぐAと帰るのに、 あすの面接が気になって落ち着かないといって、 珍しく僕らと遅くまでつきあった。 早く帰って勉強でもしろよとPが批難し、 僕とGは酒で度胸をつけろとSを煽り立て、 そのやりとりを肴にするかのようにMはエジプトの死の神のような目を細めて酒を干した。 ぐでんぐでんの僕をGが支えて先に歩き出し、 Pが別れを告げて僕らを追ってから、 SはMのあとを尾けた。 明け方のゴミを漁るカラスに上機嫌で挨拶したり、 屈んで野良猫に話しかけたりする東洋人の様子に、 とんだ見込み違いだった、 見かけ通り間抜けなお人好しにすぎないんだとSは思いかけた。 その安堵は長続きしなかった。 Mは心許ない足取りで薄暗い路地裏へふらふらと迷い込んだ。 立ち小便でもするのかと思いきや、 Sは己の目と正気を疑うはめになった。 黒い渦が煉瓦壁やゴミ缶の前、 何もない空間に滲み出るように現れ、 Mを呑み込んで掻き消えたのだ。 その一部始終を見届けるなり、 甲高い音で鼓膜が圧され、 烈しい頭痛とともに世界がぐんにゃり歪んでSは卒倒した。 気づけば陽が高く昇っており、 倒れたゴミ缶から溢れた塵芥にSは大の字に横たわっていて、 例の子ども版ザ・Bに顔を覗き込まれていた。 Sが呻き声をあげて上体を起こすと、 悪童どもは悲鳴をあげて逃げ散った。
当然ながらSは落第した。 リヴァプール美大の教職課程は夢と消えた。 首席の優等生だったかれが学生委員会の役員だった頃、 徴収した会費で行事用に購入したアンプを僕に借りパクされたせいだと噂するやつもいる。 事実がどうあれ、 画家として名をなしていたはずの人生が、 ザ・Bと関わったために致命的に狂ってしまったのはまちがいない。
三月なかばSは世話焼きのAとともにハンブルクでザ・Bを迎える準備をした。 Gの年齢は時が解決してくれたけれど、 PとピートBの件は厄介だった。 国外退去となったお尋ね者が再び出稼ぎに訪れるには、 連邦刑事局に嘆願書を提出するなど、 やたら煩雑な手続が必要だった。 国際熱愛カップルが奔走してくれたおかげで四月に僕らはどうにか海を渡れた。 出迎えのかれらが高級店ハンブルガー・レデルモーゲンで仕立てた革パンを穿いているのを見て、 僕らはさっそく真似をした (Rがうまいことをいっていた……ファッションにせよ音楽にせよ、 仲間内の流行が僕らをザ・Bらしくするというのだ)。 といっても当然おなじものには手が出ず、 シュナイダーなる店の安物で間に合わせた。 黒革上下にセンターロールリーゼント、 先の尖ったブーツという初期の僕らのスタイルはこうして完成した。
日本流のギャグをMに教わったのもこの頃だ。 ぐっと一歩踏み出すとともに、 寄り目で顎を突き出し不定冠詞を叫ぶ (楽器を抱えているので省略したけれど、 ほんとうはナチの敬礼を胸の前で倒したみたいに、 手を水平にして肘を突き出しもするらしい)。 ドイツ人たちに大受けで、 リヴァプールでも笑いがとれる鉄板ネタとなり、 成功してからも写真記者の前でよくこの顔をした。 嘘だと思うなら 「Jの変顔」 で画像検索してみたまえ、 忘れられる権利もザ・Bには通用せず、 若き日の愚行がいまだ晒し者にされている。 出し惜しみする場末のストリッパーの形態模写とか、 シャイセピーデルズなんて文句も同時に教わったけれど、 そっちは不発だったので二度とやらなかった。 次男の育児中、 軽井沢の旅館のテレビでそっくりな顔を披露する芸人を見たことがある。 僕の持ち芸が盗まれたってことを妻はどうしても信じてくれなかった。
僕らが出演した店は前のよりずっと格上で、 場所柄もあって客は荒くれ者ばかりではなく、 ジツゾン一派に加えて上流労働者や中産階級の十代後半、 学生や若い会社員が目につき、 わざわざ僕らのために市外からやってくる贔屓客までいた。 要するに 「洞窟」 のドイツ版みたいな客が増えはじめていたのだ。 とはいえ夜が更けると喧嘩騒ぎが起きるのは相変わらずで、 そんなとき僕らはわざと烈しい曲をやって煽り立てた。 ひっきりなしに元ナチの犯罪者らに酒を強要されるので、 舞台上は空き瓶や空グラスのほうが機材より多いありさま。 いくらでも手に入る豆ッコや名誉戦傷章を、 僕とMは競い合うようにむさぼった。 睡眠時間を削って描くためにSも依存していたようだし (Aが母親の化粧箪笥から盗んで供給していた)、 GやKもそれなりに嗜んだけれど、 石橋を叩いて渡らぬPは臆病者呼ばわりされるのが怖くて渋々つきあう程度、 独立独歩のピートBに至っては、 踊り子の彼女との熱戦でどんなにくたびれていても断固拒否するので、 演奏中に居眠りして僕やPや先輩歌手に怒鳴られるありさまだった。 最初の晩、 当然のような顔でシュナップスを干しながら上機嫌に手を叩くMを客席に認め、 僕らはいささか薄気味悪く感じた。 Sなど終演後に青ざめて口許を押さえながら前屈みに便所へ飛んで行ったほどだ。
この頃からSは体調不良を理由に仕事をサボりがちになる。 そのほうが演奏の質が向上するのでだれも心配しなかった。 AによればSは今日こそ辞めるぞと決意したり、 もうすこしがんばってみようかと翻意したりのくり返しだったそうだ。 PとSが舞台上で殴り合ったのも確かこの頃。 そもそものきっかけはSが何かの勘定で、 よせばいいのにPから五〇ペニーを借りたことだ。 案の定Pは何かにつけて執拗にその金に言及した。 おいS、 五〇ペニー。 おやっ財布に五〇ペニー足りないぞ、 なぜだろう。 あの五〇ペニーはまだかなあ……。 舞台でもやめなかった。 おー五〇ペニーうー五〇ペニーいぇー五〇ペニー。 しまいにはピアノを弾きながら、 おいヒモ男、 五〇ペニーの小遣いをAにもらえよと声をかけ、 決して怒らない温厚な平和主義者と思われていたSは、 それでついにぶち切れた。 大きくて重いベースを下ろし、 ピアノへ歩み寄るとPの襟首を引っ掴んだ。 ザ・Bでもっとも高身長のPの足が宙に浮いた。 おれはともかく彼女を侮辱するなとSは一喝し、 鍵盤めがけてPを放った。 騒々しい音が鳴り響いてPは床に落ちて倒れた。 Sはむっつりと元の位置へ戻り、 ベースを肩にかけ直して演奏を続行しようとした。 チャーミングな笑顔で女にも犯罪者にも媚を売ることで知られたPは、 鬼の形相で起き上がりSに飛びかかった。
マックシャウ!
客席から爆笑と悲鳴と囃し立てる声が沸き起こり、 大抵のことには慣れっこの僕らが茫然と演奏を中断するなか、 ふたりは床で上になり下になりして取っ組み合った。 しまいにはどちらも大の字になって照明を仰ぎ、 ぜえぜえはあはあと喘いで勝敗はつかなかった。 言葉を変えれば、 あれだけ莫迦にしていた華奢でひ弱なそばかすジェームズ・ディーンに、 Pは腕力で勝てなかったのだ。
屋敷に出入りしていたKにのちに聞かされたところでは、 この頃のSが揉めたのはPとだけではなかったらしい。 僕の前では決してそんな様子を見せず、 映画みたいな理想の恋人同士にしか思えなかったのだけれど、 Sはやたら気が短く暴力的になっていて、 お嬢様育ちゆえ高圧的になりがちなAと、 しばしば食器が飛んで壁で砕けるような烈しい口論が起きたのだそうだ。 さすがに僕と違って手が出るようなことはなかったと信じたい……でもそれにしたってKが奥ゆかしく口を噤んだだけかもしれない。 Aなど痴話喧嘩の件でさえ亡くなるまで一度も認めず、 Sはすばらしい恋人だったとくり返すばかりだった。 どうも彼女にはその後の男運があまりに悪すぎて、 Sとの思い出を美化しすぎるきらいがあった。 最後まで僕のことを人前で悪くいわなかったCのことも含めて、 当時Mがいわんとしたことが最近になってようやく理解できるような気がする。
連載目次
- Born on a Different Cloud(1)
- Born on a Different Cloud(2)
- Born on a Different Cloud(3)
- Get Off Of My Cloud(1)
- Get Off Of My Cloud(2)
- Get Off Of My Cloud(3)
- Obscured By Clouds(1)
- Obscured By Clouds(2)
- Obscured By Clouds(3)
- Cloudburst(1)
- Cloudburst(2)
- Cloudburst(3)
- Over the Rainbow(1)
- Over the Rainbow(2)
- Over the Rainbow(3)
- Devil’s Haircut(1)
- Devil’s Haircut(2)
- Devil’s Haircut(3)
- Peppermint Twist(1)
- Peppermint Twist(2)
- Peppermint Twist(3)
- Peppermint Twist(4)
- Baby’s in Black(1)
- Baby’s in Black(2)
- Baby’s in Black(3)
- Baby’s in Black(4)
- Hello, Goodbye(1)
- Hello, Goodbye(2)
- Hello, Goodbye(3)
- Hello, Goodbye(4)
- Hellhound on My Trail(1)
- Hellhound on My Trail(2)
- Hellhound on My Trail(3)
- Hellhound on My Trail(4)
- Nobody Told Me(1)
- Nobody Told Me(2)
- Nobody Told Me(3)
- Nobody Told Me(4)
- Paperback Writer(1)
- Paperback Writer(2)
- Paperback Writer(3)
- Paperback Writer(4)
- Anywhere I Lay My Head(1)
- Anywhere I Lay My Head(2)
- Anywhere I Lay My Head(3)
- Anywhere I Lay My Head(4)
- Anywhere I Lay My Head(5)
- Crippled Inside(1)
- Crippled Inside(2)
- Crippled Inside(3)
- Crippled Inside(4)
- Crippled Inside(5)
- Mother’s Little Helper(1)
- Mother’s Little Helper(2)
- Mother’s Little Helper(3)
- Mother’s Little Helper(4)