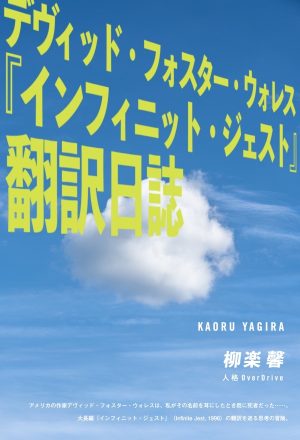「ザムザは本当に勉強が好きね」
家族の食事会であきれたように母が言う。 あなたたちの教育方針に従っただけなのに、 と私は裏切られた思いになる。 私の勉強習慣を作ったのはあなたたちではないのか。 幼少時、 遊びに行きたくて泣き叫ぶ私を机に縛りつけて勉強させたのは誰だったのか。 しかし、 老いて軟化した両親にはかつての厳格で教育熱心な若親の面影はない。
「ザムザちゃん、 本当にすごいね。 おじちゃんにはとても無理。 解体業の資格だって薄いテキスト一冊読むだけだったしね」
祖母のお焼香のために訪れた叔父の家で、 焼香を終えてお茶を飲んでいる私に叔父は言う。 母方の叔父は、 母と違って小さい頃から勉強が嫌いで、 会社勤めをすることもなく、 建物の解体業で身を立てている。
しかし、 私は本当に勉強が好きなのだろうか。 地下鉄新御茶ノ水駅の長いエスカレーターを上りながら自問する。 エスカレーターははるか頭上の出口に向かってゆっくり進む。 改札と地下深くのホームをつなぐ古いトンネルは核シェルターを想起させる。 それも一時代前のシェルターを。 とても徒歩では上れないこの長い急坂のエスカレーターを、 かつての私はひたすら歩き上ったものだ。 それほど時間が惜しかった。 それほど急きたてられていた。
エスカレーターはおとなしく立つ私を聖橋口改札に降ろす。 改札を抜けてもまだ地上には出られない。 もう1階分階段を上らなくてはならないのだ。 しかし、 この朝の私は、 地上に出ず、 そのまま改札の左側の地下通路を通って新お茶の水ビルに入った。 メガネ屋、 レストラン、 雑貨屋など開店前の店舗がならぶ薄暗い通路を左に曲がると正面から光が差しこみ青空広場が開ける。 広場の奥のエクセルシオールカフェを目にしたとき懐かしさが頂点に達する。
受験生時代、 家と予備校の通り道にあるこのカフェを何回利用したことだろう。 最初の口頭試験失敗の忌まわしい記憶もこのカフェと結びついている。 自暴自棄になって受験会場を出た記憶も今となれば懐かしい。 結局、 受験生時代は私の青春だったのだ。
受験といっても大学受験ではない。 社会人になってからの国家資格の受験だ。 新卒で就職した企業を退職し、 特許事務所で働き始めた私は、 四十路手前で弁理士試験を受けようと決めた。 出産の期限が迫りつつある中で私は試験勉強をすることを選んだ。 そうせずにはいられない理由が私にはあった。 東日本大震災の記憶がまだ鮮やかな 2011 年秋のことだ。 企業退職から 10 年以上が経過していた。
数年ぶりにエクセルシオールに足を踏み入れる。 席と席のあいだに透明シールドが据えつけられている以外は何も変わっていないように見える。 所々に参考書を広げている人がいることも変わらない。 私はかつての指定席、 中央の集合テーブルに座り、 本を取り出してのんびりと外を見た。 今の私は寸暇を惜しんで勉強する必要はない。 それは気楽であり、 寂しくもある。 受験は私の単調な人生に明確な目標を与えてくれた。 決められた試験日に向けて講義と模擬試験のスケジュールが組まれ、 最終ゴールに向けて一つ一つ目標を達成していく受験生活には否定しようのない充実感があった。 他の受験生同様私も、 こんな生活もうやだ! 早く自由になりたい! と思いながら、 一方で受験生活を楽しんでいたのも事実だ。 スケジュールを立て教材を工夫し隙間時間を利用して勉強する時の 「勉強している」 という満足感は、 自己満足に過ぎないとしても甘味なものだった。 その意味で私は確かに 「勉強が好き」 なのかもしれない。
カフェを出て御茶ノ水橋口側の交差点を渡り、 JR中央線と平行して走るかえで通りを水道橋に向かって歩き始める。 エクセルシオールカフェ、 スターバックスなどの一般客向けの店を過ぎたあとは緑に囲まれた静かな街路が続く。 道端には池坊東京会館や古びた研究施設、 目立たない記念図書館など時間の流れを感じさせない建物がならぶ。 さらに進むと、 右側の建物が途切れて視界が開け、 線路を直接見下ろす形で道が急降下する。 この辺りを歩いていると、 東京は勾配の多い町であることを実感する。 坂の途中にはアテネフランセもある。
かつてここで小川紳介のドキュメンタリー『圧殺の森 高崎経済大学闘争の記録』 を見たことを思い出す。 受験勉強を始めるずっと前のことだ。 その頃の私はドキュメンタリー映画だけでなく、 舞台や踊りも見、 美術館にも行った。 社会運動の末端にも参加した。 自分でも何がしたいか分からず、 何かを求めて歩き回っていた。 外に行けば何かがあると信じていたのかもしれない。 あるいは、 社会が変えられると。
しかし、 それは遠い過去の話だ。 そのような文化活動や社会運動は受験勉強を始めるときにすべて止めた。 それだけではない。 受験のために他のすべてを諦めた。 飲み会などはことごとく断ったし、 友達と会うことも止めた。 旅行も諦めた。 それまでの活動仲間との関係も途絶え、 社交生活を失った。 それは社会的透明人間になるようなものだった。 私はあらゆる人のレーダーから消えた。
そこまでする必要があったのだろうか。
答えは YES だ。 その確信は当時も今も変わらない。 自分を社会から隔離しなければ受験勉強はできない。 受験期間を刑期と呼ぶのは理由あってのことだ。 普通の生活を営もうとする人はいつまでたっても合格できない。 それは高校生だろうと社会人だろうと変わらない。 高校生の場合、 周囲の人すべてが受験生であるのに対し、 社会人は周囲の人すべてが受験生でない点が違うだけだ。
そのような生活は簡単にできるものか。
答えは NO だ。 他の人が遊んだり、 仕事で活躍したりしている中で、 社会的に引きこもって机に齧りつき、 いつ終わるか分からない勉強を続けることは孤独で惨めで辛い。 皆が盛り上がっているところに加われずに取り残されたような気持になる。 気持ちになるだけでなく、 実際、 忘れられ、 取り残されていく。
しかし、 勉強とはそもそも孤独なものだ。 他の人が遊んでいる間に机に齧りついて勉強する、 その孤独に耐えられる人しか結果を手にすることはできない。 結果が試験の合格であれ論文の完成であれその事実に変わりはない。 勉強を開始したばかりの頃、 私はいくら勉強しても内容が理解できないことに焦り、 落ち込んだ。 でも投げ出して逃げるわけにはいかない。 相談相手だった知人に何度も泣きつき、 その度に 「我慢しろ」、 「勉強しろ」 と叱咤され、 泣く泣く勉強に戻った。 実際、 彼の言うとおり、 我慢して勉強する以外に道はなかった。 内容の理解を他の人に肩代わりしてもらうことはできない。 そうであれば、 自分のなかに理解が生じるまで努力を続けるしかない。 例えその期間、 耐えざる自己嫌悪に蝕まれるのだとしても。 勉強を始めた最初の時期に、 他のすべてを諦めて勉強に集中するしかない、 と観念できたのはよかった。 予備校の講師から、 平日2時間以上、 週末7時間の勉強時間を確保するように言われたが、 そのためには勉強をすべてに優先させるしかない。 仕事帰り、 山手線を一周して勉強したとか、 仕事の合間、 お手洗いに行くときも暗記カードを持って用を足した、 という受験生もいた。 普通の生活と両立させようとしていたら、 何年経っても合格することはできなかっただろう。
アテネフランセを過ぎ、 坂を降り切った私の前に大きな通りが横たわる。 水道橋だ。 景色は一変して殺風景なものとなる。 白山通りを渡り、 何の風情もない道を奥に進んで予備校の前に立ったとき、 胸がどきどきするのがわかった。 普段なら多くの受験生が出入りしているであろう受付にはスタッフしかおらず、 建物から人の気配はしない。 受験生のいない建物は抜け殻のようだ。 その意味では予備校は元来一つの通過点に過ぎず、 愛校心の対象ではない。
それでもその日の私が興奮していたのは、 模試を受けるためにこの建物に通った時の興奮を思い出したからだ。 アドレナリンが噴出して闘志に満ちた当時の心境を。 ライバルである他の受験生と机を並べて試験用紙に向かう緊張感は特別な感覚だった。 試験の緊張感は、 その時間だけ、 私の小ささを忘れさせてくれた。 その瞬間だけ私は自分を超えたものとなれた。
受験勉強は長い時間を必要とする。 短くて 1 年、 通常は 2 年または 3 年、 場合によってはもっとかかる。 身につけなければいけない知識がそれだけ多いからだ。 それは、 アウトプットを禁じられたインプットを長時間続けなくてはいけないということであると同時に結果の分からない不安を長時間耐えなくてはいけないということでもある。 模試はそれまでの長いインプットの成果を試す絶好のチャンスだ。 ワクワクしない理由があるだろうか。
受験勉強はクラスの級友などの目の前の相手を超えた 「遠い」 ものを意識させてくれる、 と教育者である芦田宏直は言う。 「遠い」 ものへの意識を 「遊動」 と置き換えて彼は説明する。
“「できる学生」 は意味のない受験勉強で、 多少の遊動経験があります。 「意味のない」 とは、 近親者 (家族、 地域の人間環境、 学校の教員やクラスメートなどとの人間環境など) との関係を超えた “非” 人間的な基準=偏差値に初めて出くわす 「遊動」 のことです。 目の前の人間を殴って勝てばいい、 目の前の人間を納得させればいい、 目の前の人間から賞賛されればいい、 目の前の人間を大切にすればいいといった関係を超える遊動性を 「できる学生」 は受験勉強で経験するわけです。 受験勉強は、 小さな自室の孤独で内閉的な経験のように見えますが、 そこで彼らは、 ある種の 〈社会〉 ——非人間的な圧力——に出会っている。” 1
つまり、 受験勉強とは、 狭い人間関係を超えた広い世界を意識させてくれるものであり、 その広い世界と対峙させてくれるものなのだ。 それを明確に意識するのが模擬試験というわけだ。 だから、 試験用紙に向かうとき、 緊張感を覚える。
試験用紙に向かう私は、 目に見えず、 実際に会うこともない全国の受験生と向かい合っていた。 私たちは皆、 通俗的なちっぽけな自己を離れて同じ目的のために持てるベストを尽くしてそこにいた。 個々人の人間的な属性を超えた 「お主できるな」 というコミュニケーションがそこにはあった。 自分が努力してきたからこそ相手がどれだけ努力したかも分かるという類のコミュニケーションだ。
そのようなコミュニケーションは孤独の果てにしか得られない。 そこに参加できるのは自分を越えようと努力を続けた者だけで、 目的の異なる者ややる気のない者が入る余地はない。
私は、 口頭試験に失敗したため試験の最終合格まで 4 年かかった。 大学に入学してから卒業するまでと同じ年月を社会的透明人間として受験勉強に費やした。 始める前はそんなに長い期間勉強を続けるなんて無理だと怖気づいていたが、 気がついたらどうにか成し遂げていた。 そこには、 秘訣は何もなかった。 予備校の講師や先輩受験生のアドバイスは勉強方法を知るために有益だったが、 最終的には自分がつらさを我慢して続ける以外の道はなかった。
今この連載を書きながら、 書くことも受験勉強に通じるものがあると思う。 私の連載は原稿用紙 10 枚程度の短さで、 期限も 2 週間であり、 4 年間の受験期間に比べて非常に短いが、 それでも空白の画面に向かってから記事が形をとるまでの間は、 受験勉強の時と変わらないつらさに投げ込まれる。 それは、 書くという行為が、 実際に書き上がるまで本当に書けるかどうかわからない不確かなものであるからかもしれない。 もっと長いものを書くとなれば、 より長い期間を結果の見えないつらさの中で過ごさなければならないだろう。 場合によっては 1 年、 2 年、 あるいはもっと長い時間を。
エッセイや小説などの文章に限らない。 仕事も同じだ。 何かを作り出す過程には必ずこのつらさを耐えなければいけない期間がある。 そのような 「変化を担ったり、 変化を耐える能力」 を 〈根性〉 と芦田は呼ぶ。 受験勉強は、 年に一回の試験で合否が決まるという一回性によって身体性を伴う 〈変化〉 の体験となる。 そのような大きな変化の体験が 〈根性〉 を見出す契機となる。 2
図らずも、 数周遅れの受験勉強によって私は自分の 〈根性〉 を見出す機会を得た。 現在の私にとって受験勉強は過去の話だが、 生きるための戦いには終わりがない。 これからの私は文章を書きながら、 仕事をしながら、 自分の 〈根性〉 のありかを問い続けていくしかない。