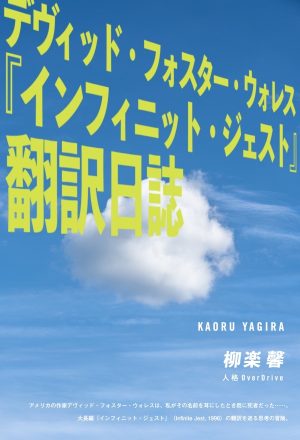私は一つの部屋にいる。 今そこで生活しているのは私だ。
数年前から私はこの部屋で起床し、 着替え、 食事し、 就寝している。 以前は別の部屋で起床し、 着替え、 食事し、 就寝していた。
部屋は正確には三つある。 いわゆる 2LDK 住宅。 ファミリータイプの住居だ。
この箱の住民は私一人。 言ってみれば、 一人ファミリーだ。 最新型家族としての一人家族。 人類の進化の最終形態。 しかし、 これは語義矛盾だ。 一人で家族を構成することはできない。
箱は見るからに昭和の産物だ。 リビング以外は和室で、 収納は押入れのみ。 台所/リビングは仕切りのない同一空間で、 配管は剥き出し。 他世帯が水を流すと、 ごうごうと響く。 動線や使いやすさへの配慮とは無縁だ。
しかし、 この地上四階の空間はまぎれもなく私の家だ。 私の生活の拠点であり、 憩いの場であり、 城塞だ。 鉄の扉と四方を囲む壁が私を守る。
この部屋に移り住むとき、 ここに自分の家をつくると決めた。 約束の地にたどり着いたユダヤ民族の父アブラハムのように。 この地に私の家を建てる、 と。 そして、 この無記名の空間が私の 〈家〉 となるように心を懸けてきた。 文字通りの意味で。 たとえ単独の生活であっても。
部屋は、 そこに人が住みさえすればひとりでに 〈家〉 になるわけではない。
部屋は誰かがそこに住まい、 命を吹き込むことによって初めて 〈家〉 となる。 自分の育った家を思い出すとき、 そう実感する。 幼少時、 家の中心には母がいた。 母が家に命を与え、 家をつなぎとめていた。 家のなかに置かれた雑多なものを気にかけることによって、 それらに存在の意味を与えていた。 母はいつも手を動かしていた。 座っている時でさえ、 何かを磨き、 床にローラーをかけ⋯。 見慣れた影が家のなかを動きまわる音、 掃除機をかけたり、 洗濯をしたり、 食事の準備をしたりする音は私に安心感を与えた。 家は狭く、 家具も高級ではなかったが、 それらはみな手入れされていた。 みな家に馴染んでいた。
ポール・オースターに 『孤独の発明』 という作品がある。 そのなかで、 金のない主人公 A はオフィスビルの一室に住む。 そこは見るからに殺風景な部屋で、 家具もマットレスくらいしかない。 その部屋についてオースターは書く。 「この部屋に長時間止まることによって、 たいていの場合彼は空間を自分の思考で満たすことができる。 そしてそれが荒涼さを霧散させてくれるように思える」 と。 母とは異なるレベルで A も 〈思い〉 が空間に命を与えることを知っていた。
部屋は、 そこに人が住みさせすればひとりでに 〈家〉 になるわけではない、 と私は書いた。
学生の一人暮らしの部屋を家とは呼ばない。 独身寮の部屋を家とは呼ばない。
遙洋子が、 いつか結婚する将来のために十年近く三段ボックスで暮らし続けていた彼女自身について、 「結婚が 『予定』 だとすれば、 現在のすべては準備段階であって、 私は仮に生きていることになる。 ——恐怖が襲った。 もし永遠に 『予定』 が実現しなければ、 私は仮の人生を生き続けることになるんじゃないか!」 と書くとき、 その言葉は 〈家〉 を持たない私たちの心の洞に響く。 彼女の言葉のなかに自分の姿を見たのは私一人ではないだろう。
私の場合ゴールは 「結婚」 ではなかったが、 将来の完成形のために仮の人生を生きていることに変わりはなかった。 それは 「家づくり」 をしないという態度に現れていた。 三段ボックスですませる遙洋子のように私もすべて安物ですませていた。 特に、 現住居の一つ前に住んでいた狭いワンルームアパートではその態度が徹底していた。 その部屋は職場と当時通っていた大学との近さ及び家賃の安さのみから選んだ籠で、 日当たりも景観も悪く、 収納が小さいので物がほとんど置けず、 冷蔵庫は流しの下に備えつけの超小型のもの、 風呂はぎりぎり体が入るユニットバスだった。 ちょっと動くだけで物にぶつかるので、 体の動きには常に注意しないといけなかった。 それは落ち着いて生活できる空間ではなく、 長時間過ごしたい空間でもなかった。 いわば、 戦いの合間に睡眠をとるための兵舎のようなものだった。 兵舎の方が体を伸ばすスペースがあるだけまだマシかもしれない。 その籠で過ごした数年間は気の滅入るものであり、 最後にはちょっとした物音にもパラノイア的反応を示すほどひどい精神状態に陥っていた。
今では遠い夢のように感じるが、 そのような日々は本当にあったのだ。 ゴキブリにおびえ、 小さな音にも追い詰められる日々が。 怖くて寝床の中で身動きをせずに固まっていた日々が。
あの日々がなければ、 仮の人生をやめようとまで決心しなかったかもしれない。
仮の人生をやめること、 それはひとりで生きることを 「完成形」 とみなすこと、 先にある目に見えない 「予定」 のために生きるのをやめることだった。 その決意を象徴するのが 〈家〉 だ。 物件を購入する必要はない。 ただ、 自分ひとりで生きていくための生活の場としての物件を選び、 生活にふさわしく整え、 そこで 「本番」 の人生を始めるのだ。
住居を決めることは必ずしも快い作業ではない。 自分の収入を明確に把握しないといけないし、 自分の住む地域、 住む家を固定しないといけない。 それはそのまま自分の属する社会的階層を突きつけられることでもある。 社会的成功者でない者にとって社会的枠組みに自分を組み込むことは気が重い。 しかし、 結局はどこかに所属するしかない。 一定の枠組みをつくり、 収入を計算し、 予算を立て、 そのなかで生活という事業を執り行っていくしかない。 自分の生活レベル (予算の枠組み) に応じて快適に暮らすための必要条件をビジネスライクに割り出さなくてはいけない。
本番の人生を始めるために私が選んだのは現在の住居、 都市再生機構 UR (旧日本住宅公団) の団地の一室だ。
一人暮らしで 2LDK は贅沢と思われるかもしれない。 でも、 仕事に集中するために、 食事/休憩の空間、 仕事/勉強の空間、 睡眠の空間を分離させたかった。 一人暮らしの人間には頼れるものが自分の労働力しかない。 労働力を維持し続けるために心身の健康を保つことは最優先事項だ。 分離された空間を確保することは私にとって、 精神的なバランスを保つための差し迫った要請だった。
私は UR の団地に住むことを選んだ。 独身者のボヘミアンな生活とはほど遠い、 この施設に住むことを。 団地ほど地味で個性の乏しい物件はないだろう。 それもそのはず、 団地は戦後の住宅難を解消するために国が設営した標準化住宅なのだ。 狭い面積の中に最も効率的に 「家族」 を収容するために 51C1という型が考案された。いわゆる 2DK だ。 公団は、 この 51C から始まり LDK へと拡張された標準的な型をコピペすることによって住宅を量産した。 かくして、 標準家族が住むための標準住宅が出来上がった。 この標準住宅は標準パターンのライフコースの一環として存在した。 団地は、 都市流入者の標準的なライフコースにおける通過点となった。
しかし、 社会上昇という標準的なライフコースの夢をもたない私にとって、 団地はそのままひとつの終点だ。 大量の都市流入者の住宅難解消というかつてのミッションを終えた団地は、 「自分探し」 をしなくてはならなかったと団地愛好家・大山顕23は書く。 それは団地があくまでも 「インフラ」 であり小洒落た 「商品」 になりきれないからだと大山は分析する。 小洒落たマンションに場違いな感じを受けた私には、 大山の分析が私のことを語っているように思える。 標準的なライフコースから外れた私にキラキラしたマンションは似合わない。 無骨なインフラとしての姿をさらす団地こそ、 私が住む場所に思える。
現在私の住む団地は、 単身または夫婦の高齢者、 子どものいない中高年夫婦、 子持ちの若い夫婦、 アジア系・欧米系外国人と多様な人々が住む。 親世代と子世代が隣り合う部屋に暮らすことも多い。 仕事を終えて帰宅し、 階段を上がると、 異国の香辛料の匂いが漂ってくる。 ドアベルが鳴るので誰かと思えば、 部屋を間違えた老婦人が立っている。 地上階に降りれば公園で子どもたちが走り回り、 週末には同じ公園でゲートボールに打ち興じる高齢者の姿が見られる。
公園で駆け回る子どもたちを見ていると古い記憶の断片が蘇る。 かつて私はある団地の横のアパートに住んでいた。 中央通路を挟んで数十の棟が並ぶその団地は一つの町のようだった。 町の住人である親友二人と、 毎日のように棟の間を駆け回ったものだ。 公園、 棟間の通路、 階段室——団地は巨大な秘密基地だった。
二人の友だちの家に遊びに行くのが好きだった。 団地の居室にはアパートにはない特別な雰囲気があった。 幼い私は心の底で団地に憧れていたのかもしれない。 その佇まいに魅せられて。
今、 私は一つの部屋で生活している。 都市再生機構 UR の団地の一室だ。 「自分探し」 に失敗した団地に 「自分探し」 に失敗した私が住むのはいかにも似つかわしく思える。 どのようにしてこの場所に辿り着いたのか、 分からない。 偶然としか言いようがない。 長い時間を経て、 偶然の結果、 私は幼少時の原風景に戻ってきた。 ここに私の 〈家〉 を築くために。