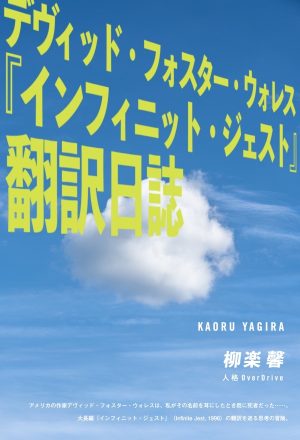オークション会場でのシュレッダー・テロの話題で関心をもち 『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』 を観た。 娯楽性の強い起伏ある筋立てといい、 MF Doom さながらの語り手をはじめとする個性豊かな登場人物といい、 アメコミ原作の空想的アクション映画のようでおもしろかった。 エンドロールの象のギャグに至るまで愉しめた。 後半だれが録っていたのかという謎の答えも明かされる。 バンクシーとは単独アーティストというよりもチーム・プロジェクトなのだろう。 同じ歌詞がオープニングとエンディングでまったく違って聞こえる。 ソーシャルメディア時代のコンテンツの寓話であり優れた風刺だと感じた。 アンディ・ウォーホルの 15 分間が現実になるとここまで醜い事態になる。
インターネットでうまくやる才覚がなければ売りようがない時代だ。 「インターネットでうまくやる才覚」 はいいものを書く才覚や技量とはまったく関係がない。 むしろ真逆であることが多い、 なぜなら 「インターネットでうまくやる才覚」 は世渡りの才覚であり、 そこには 「本物でないこと」 「もっともらしく取り繕うこと」 が含まれるからだ。 社会的な立ちまわりの手段として読書を用いるひとたちにとっては、 上っ面を取り繕っただけのもののほうが扱いやすい。 独創は 「わかりにくい」 として憎まれる。 さんざん使い古された実績ある既存イメージをあく抜きして提示すれば共感され、 ソーシャルメディアの話題となり 「画期的」 と賞賛される。 それがアルゴリズムの雪だるま現象を誘発し、 唯一絶対の価値として固定される。 インターネットで喜ばれる才覚はそのようなものだ。
それは読書とは対極にある。 そうしたものと取次や Amazon のような権利ビジネスとは残念ながら相性がいい。 読みたい本が出版されにくくなったのはそのせいではないか。 金をかけられなくなれば出したい本が出せなくなる。 多くを持っていく連中の発言力も増える。 本来であれば読者に望まれる本が出版されるべきだし、 収益は出版に関わったひとたちにその貢献度合いに応じて還元されるべきだ。 たとえば著者、 編集者、 装幀者、 校正・校閲者、 オーサリング者⋯⋯といった順番で。 ところが実際に彼らが得るのはしゃぶり尽くされた骨だけだ。 取次や Amazon だけがやくざのように上前をがっぽりさらっていく。 「売れる」 と 「読まれる」 は異なる。 読まれれば売れるが売れれば読まれるとはかぎらないし、 読まれないのに売れるものを売りつづければいずれ客からはそっぽを向かれ何も売れなくなる。 現在はその末期に近づきつつある。
権利ビジネスにつけこまれないためには Mr. ブレインウォッシュのような紛い物とは較べ物にならない魅力を提示する必要がある。 つまらないもののほうが 「わかりやす」 く受け入れられやすいのは確かにどうにもならない事実ではある。 しかしそんなことなど問題にならない魅力を本物は提示できるはずだ、 正しい手段を見出しさえすれば。 現状はソーシャルメディアの世渡りを上まわる訴求力を何ひとつ提示できていない。 Amazon ランキングをしのぐ指標を提示することが重要だ。 加えて顧客情報を Amazon に握られてマーケティングに基づく商品開発が阻まれていることも著者や出版社の問題かもしれない。 海外の著者のあいだではメールマーケティングで顧客のニーズを把握し、 顧客に直接訴えることが何よりも重要だという認識が一般化している。 ストリーミングメディアが普及して円盤で稼げなくなった音楽ビジネスにおいてもしかりだ。
著者や出版社が自信をもって送り出した本を紹介する信頼性の高いサイトはないものか。 メール登録を伴うそうしたサイトを成功させられないものか。 結局はソーシャルメディアでの立ちまわりに帰結する。 使い古された中身のない 「わかりやすい」 代物でないかぎり成功はあり得ない。 堂々巡りだ。 孤独に根ざした読書という行為は 「淘汰」 され、 出版は死に、 Mr. ブレインウォッシュさながらの世渡りだけが残るのだろう。 グーテンベルクが一部の特権階級からひとびとに取り戻した言葉の自由は、 権利ビジネスという特権階級にふたたび奪い返された。 インターネットで発言力のあるひとびとはそれをよしとする。 読書の可能性はこのまま死に絶えるのだろうか。